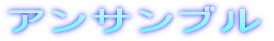
-blind summer fishXXX-
その①−【聖・バレンタインの場合】
「いや、今回も一位! 流石だねー」
「いや、ぎりぎりですけどね」
トークも兼ねた音楽番組の出演の日。四人揃って出演したその番組の司会者の言葉は流れ上おかしくない。
つい先ほどランキング(その番組の)が流れたところだった。
謙也たちのグループ「柊」の順位は相変わらずの一位。
「ああ、紫と売り上げ結構近かったらしいですしね」
「そうそう」
「でもそれを押さえたんだから、やっぱすごいよ!」
「ありがとうございます」
いや、実際ホンマすっごいぎりぎりなんやけどな。
と謙也は外面スマイルの中で突っ込んだ。
従兄弟、忍足侑士と梶本貴久、そして新しく入った不二というメンバーでなる「紫」という同じ事務所のグループはかなりの人気で、下からの追い上げがかなりきつい。
侑士も人気は相当高いし、梶本も根強いファンがいる。そして新しいメンバーの不二はどうやら、人気タレントの不二周助の弟らしい。
「そういえば、そろそろバレンタインですよねー。
四人は誰かにもらいます?」
「事務所に一杯来るんじゃなかか…っ」
余計な発言をした千歳の口が背後から塞がれた。財前だ。
流石の白石も、その発言を番組でいうのはまずい、くらいはわかる。苦笑を浮かべたままもがく恋人を諦観した。
「そうですね。真心こもったもんなら、欲しいですわ」
全く構わず小さな笑みつきで言った財前に、観客から黄色い悲鳴が飛ぶ。
番組では寡黙なキャラらしい財前は、一言喋っただけで悲鳴が飛ぶ。実際、すごい口数多いけど。
「俺も、可愛い女の子からなら嬉しいです。ちゅーても、可愛くない女の子なんておりませんけどね」
謙也の言葉に、やはり黄色い悲鳴。しかし、財前の視線があからまさに「このカッコつけ」と語っているのが、流石の白石にもわかってきた。
「白石くんは?」
「え、あ」
急に振られてびっくりしたが、白石は視線を微かに彷徨わせた後、
「欲しいチョコ、とかあります? それとも、お付き合いしてる人以外のチョコはもらいません、な派?」
「……いえ、そうやないですけど…でも」
そもそも嫌われて育った中高生時代。チョコなど無縁だったから、もらうのは純粋に嬉しい。最初は答えられないのに、とも思ったが「この業界の人間に送るチョコに、答えなんか期待する馬鹿はいない。もらってもらえるだけで向こうは満足」と言われて、それもそうかと頷いた。今は純粋に、それだけ沢山の人に見てもらえているんだ、と嬉しい。
「…好きな人からもらえたら、嬉しいですね」
照れたように言って笑った白石の発言直後、観客が悲鳴を上げた。しかし、黄色い、ではない。むしろ「イヤー!」的な。
(あ、アカン。失敗したかも)
今頃そんなことに気付くが、既に遅い。
「あれ? 白石くん、付き合ってる人いるんだ!?」
「い、……いえ! 付き合ってないですよ? ただ、俺が片思いしてて」
「あー、そうなんだ。白石くんみたいな男の人に好かれたら、誰だって即オッケーな気がするけどねー」
奇特な女の子もいるんだねー、と言う司会者と、あからさまに安堵する観客の空気。
その場はうまく切り抜けられた、と思った白石が、別の『付き合い』の難しさを悟ったのは、収録終了後。
「ほな、いつも通りの場所で飯食って帰るかー」
楽屋で、謙也の声に財前が最初に頷いた。白石もはい、と頷く。
しかし、着替えも終わったのに、グループ一の長身は返事がない。
「………? 千歳さん?」
不思議になって白石が覗き込み、見上げる。
「行かへんのですか? なんか、用事なら、俺も」
「……あ、ああ…。………っ………」
答えた直後に、陰鬱な空気で「ふ〜〜〜〜〜〜〜〜〜」と長い溜息を吐いた千歳に白石はますます困惑した。
「千歳さん…? あの、ほんまどないか…」
「……ごめん。俺は先帰る。白石は付き合うて来なっせ」
「……え、え…あの…っ」
戸惑った白石がそれでも引き留めようと追うが、その前に楽屋の扉が相当乱暴にバタン!と閉じた。
「……………………」
扉の前で真っ青になる白石を余所に、財前が謙也の耳を引っ張る。
「あれですかね? 白石さんが咄嗟に『付き合うてる人おらん』とか言うた…」
「…確実にな」
「………っ………千歳さん……」
扉の前で真っ青なまま右往左往した白石は、やがて財前たちを振り返って涙目になる。
「…どないしよう。わからんけど…怒らせた……っ」
「いやいやいや! あいつもホンマのとこはわかっとるから!」
「…基本、心狭いだけっすからあの人は」
項垂れてほとほとと泣く白石を宥める謙也を見ながら、財前は一応進歩しているけどと思った。
前なら、「怒らせた」じゃなく「嫌われた」ってところだろう。白石が思う方向は。
いや、千歳もそこを誤解させる心配が今はないから、不機嫌になれたのだろうか。
「……ノロケ?」
「は? なにが?」
「イエ」
いつも収録の後に行く、行きつけのレストランはどちらかといえば女性に人気で、理由は部屋が個室なこと。
だが、謙也達には有り難い。注目されながらの食事は結構肩が凝る。
「ほらほら、お前の好きなジャスミンティー。飲んで落ち着けや」
「……はい」
まだ意気消沈した白石を宥めつつ、謙也は運ばれて来た自分のハンバーグ定食に手をつける。
「…なんや? 光?」
じっと自分を注視する後輩に謙也が居心地悪そうにすると、後輩はふ、と笑って。
「カッコつけの癖に好きな食い物『ハンバーグ』。そら個室やないと頼めんわなぁ」
「馬鹿にしとるかお前…! ハンバーグのどこが悪い!」
「いえいえ。可愛いっすわぁ…て」
「じゃかあしゃあ!」
「け、謙也さん、光、落ち着いて」
この辺は恒例だ。財前がなにか言って謙也がキレて、白石が宥める。
ただ、普段なら最後に千歳が台無しに余計なことを言ってまた誰かがキレる、という流れだが。
そこまで思い出して、またズゥンと沈んだ白石に謙也も財前ももめてる場合じゃないと佇まいをなおした。
「大丈夫ですって」
「そうそう。あいつ、怒ったんやなくて、ちょっと嫉妬した?だけやねん」
「…嫉妬? 誰にですか?」
「お前が『付き合ってる人いない。片思い』て言うたやん。
千歳的には『俺と付き合ってるのに、付き合ってないって言われた』てショックなんや」
「………」
謙也の説明に首を傾げたあと、白石はまだ若干青ざめた顔にきょとんとした表情を浮かべてコクン、と首振り人形のように頷いた。
「あ、そうやったんですか。…そうなんや」
あっさり納得する白石に、千歳のことをどうこう思う暇は謙也と財前にはない。
ホンマ毎度毎度、こいつは可愛いなこの野郎…!
と揃って同じことを考えている。
「…わかりませんでした?」
気を取り直して財前が訊くと、白石は軽く考えて、
「やって、そもそも誰かと付き合ったことあらへんから、こういうことで付き合ってる男の人が怒ったの見たことなくって」
「見たことなくてええ。見たことあったら千歳が泣く」
謙也の言葉に、財前もこくこく頷く。
「…どないすっか。千歳も多分、ホンマはわかっとる筈やけど…」
「…あ、ええアイデアがありましたわ」
「え、なに?」
財前が手を打って、白石の耳に耳打ちをする。
聞こえた謙也が「ああ!」と手を打つ。白石は対して真っ赤だ。
「……するん?」
「「うん」」
「……したら、千歳さん、喜ぶ?」
「「うん」」
二人に揃って頷かれ、白石は赤い顔で頷いた。
『い、……いえ! 付き合ってないですよ? ただ、俺が片思いしてて』
あの場で白石が答えられることとしては、在る意味上出来だ。
しかし、気に入らないというか、ショックな自分は情けない。
「……男らしくなか。俺は…」
どんと構えてやれていれば、いつも不安になんかさせないのに。
風呂からあがって下にズボンを履いたままでそう呟いていると、背後で玄関の扉の閉まる音。
「あ、ただいま千歳さん」
帰ってきた白石に「お帰り」と返して、もう大丈夫だというように笑ってやる。
「あ、千歳さん! 上も着てください! 風邪ひくやないですか!」
しかし、白石の感覚もたまにこうずれていて、千歳は押され気味に「ああ、うん」と頷いた。
(暖房効いとるとに…。てか、ちぃとは帰ったら抱けるん期待して着てなかったとよ…)
わかってくれ、と念じるもわかるはずがない。
「あ、あの、千歳さん」
「ん?」
葛藤していると呼ばれて振り返った。すぐ白石の両手に引き寄せられて、驚く間なく唇が重なる。
ドキっとして、もしかして大丈夫かと期待した千歳の口の中に、不意に甘い味が広がった。
(…え、甘い…これ、)
唇が離れると、息を荒くした白石が拭う唇に微か、溶けたそれがついている。
「…チョコ…?」
「…はい。あの、あれはその場しのぎの嘘で…、俺は千歳さんと付き合うてること、なんも恥ずかしないですから」
「……あ、ああ…俺も」
ごめん、と言いたいが、何故キスにチョコが、と考える程顔が赤くなって、なにも考えられない。
「…でも、俺、千歳さんからもらえるなら嬉しいけど、俺もあげたいから。
ちょっと早いけど…、もっと食べてくれますか?」
「……え、あ」
白石が手に持っていたチョコの箱から、一個とって含むのは自分の口。
「はい」
それで、そんな風に手を伸ばされたら、我慢なんか効くわけがない。
深く唇を奪って貪って、そのまま身体を抱き上げる。
「…イヤやった?」
「まさか。たいが興奮した。…ばってん、…チョコの数じゃ、足りん」
「……、じゃ、…」
抱えられた白石の手が首に回されて、耳に囁く声。
もっと、キスして。
バレンタイン明けの番組で、「幾つもらいました?」という共演者の問いかけに顔を見合わせる。
「沢山?」
「せやけど、ホンマに欲しい人からももらいましたから」
謙也と財前の言葉に、「え?」となる共演者と司会者に、千歳と白石も顔を見合わせて笑う。
「俺達、全員、付き合うてる人がおるんです」
その後日、いろいろな雑誌で『柊』の熱愛発覚だとか、色々書かれていたが本人たちは気にしていない。
「ま、誰か一人が口滑らして勘ぐられるくらいなら、全員おるって言えばええんですわ。事実やし」と発端の財前がそう言った。
その① END