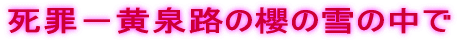
epilogue-【冬の桜でもう一度】
どこかから大阪に帰ってきてからずっと、部屋に引きこもったままの甥を叔父は咎めなかった。
千歳の叔父の家は大阪にある。それが、千歳が大阪に行くのを許された理由の一つだろう。
千歳のいたアパートは叔父が引き払ってくれただろう。
仮として宛われた部屋で、ただ寝て過ごすだけの日々を過ごして、季節はすっかり変わった。
今は、冬だ。
叔父が今朝、雪が積もっているぞ、とだけ言いに来た。
学校にも行っていない。学友からの電話は最近、おとなしい。
白石もいないから、なにか察してくれたのかも知れない。
ふと見上げた窓から、雪が見えた。
『なあ、そこのでっかいお前』
あの声が蘇って、起きあがった。
白石はもう、この世界のどこにもいない。
それでも、雪は桜のようで、自分を期待させた。
「千里。どこかに行くのか?」
「うん」
「そういえば、こっちに来る前、どこに行ってたんだ?」
「……」
居間で問いかけてきた叔父に、どうせ言ってもわからないと思いながら口にする。
「千里堂って里」
言ってすぐ、下駄で家を出た。
「千里堂…あの里に?」
残された千歳の叔父の言葉に、叔母が知ってるのかと聞いた。
「ああ、…義兄さん…千里の父親の生まれ里だ」
義兄さんはその里の人柱として生まれたそうだ。そして九州に逃げたが、連れ戻された。
その後人柱として殺されたが、気付けば逃げた時住んでいた九州の家で目覚めたそうだ。
人柱の印は、どこにもなかったらしい。
人柱は十五年しか生きられない身体で生まれるから、だから神様に捧げられるのは、もしかしたら儀式じゃなくて、十五年しか生きられない身体で生まれた子供に長い人生を与えるための、神様の祝福の儀式なんじゃないかって言ってた。
義兄さんにとって、千里堂の神様は本当の神様なんだそうだ。
だから、息子に『千里』と名付けたと言ってたな。
だから千里の決めたことはなんでも許すって。自分で決められる人生を、息子に与えたいんだと。
千里は昔から不思議なことが出来たのも、
自分が千里堂の人間で、その息子だったからじゃないかって。
寒いと思った。
上着くらい着てくればよかった。
(…ごめんな)
それでも桜が、まだ散るんだ。
(ごめんな)
桜が散るんだ。
白石が、死んだ後も。
彼が泣いていると言うように。
白石は、死んだのに。
彼の命は散ったのに。
(…散るな)
「…白石は…死んだと…っ」
それでも、愚かにも期待して、自分は白石を追えなかった。
死ねなかった。
散る桜に、期待して。
どうしようもなく、期待して。
桜が散るから。
桜は彼の涙だから。
桜が散る限り、彼がどこかで生きている気がして。
泣きながら、自分が傍に来るのを、待っている気がして。
死人のような歩きがたどり着いたのは、あの公園。
桜は、雪の中でも咲いていた。
「…散るな」
それでも、やっぱり白石はいないんだ。
「…散らんでくれ」
白石がいないのに、泣かないで。
「…………っ……白石…」
雪は桜のようで、桜は雪のようで。
桜と雪が散る、空の下。
「……会いたか…っ……」
もう一度、会いたい。
何一つ、諦められないんだ。
お前の心も、命も、一緒に生きる未来も。
お前が、もういなくなった後ですら。
会いたい。会いたい。会いたい。
「……会いたい……」
頬を涙が流れて、ぽたりと雪に落ちた。
ここにいたって、二度と彼は罰ゲームなんやって、来てくれない。
もういないのに。
求めて、すがって、望んで。
こんなにも、愛している。
不意に見た、あの日彼が座っていたブランコ。
雪が、片方に積もっていない。
「…?」
こんな雪の日に、こいだ人間がいるのか?
不思議に思って近寄った。その時、その上に散った桜の花弁が落ちた。
背中で、人の足が雪を踏みしめる音。
柔らかい、声が響く。
「なぁ、そこのでっかいお前」
それは、何度も聞き慣れて、何度も夢にまで願ったテノール。
目を見開いて、震えながら、心臓が痛い程鳴ってそれでも振り返った千歳の先で、コートをまとって立つ、銀灰色の髪と、翡翠の瞳の男が微笑んだ。
「俺と雪合戦してくれへん?」
その声に合わせるように雪が、桜が散るのは、彼が泣くから?
それとも、彼が微笑むから?
「今度は罰ゲームやないで? 今、冬やし。雪、降っとるし」
「……し、…」
「ん? なに、千歳」
「………」
千歳。
「…しら、いし?」
「……他の誰に見えんねん、アホ」
「……、っ」
走り出した足下で、雪が鳴った。
差し出された彼の手を掴んで、骨が軋む程抱きしめる。
閉じこめるように、もう離さないように。
その身体は、とても暖かかった。
「…しら…っ……白石―――――――――――――…!!」
「……千歳…やっと、出てきたんか、アホ」
「……っ……ほ、ほんに…ほんに…白石…っ?」
「…俺以外の誰が、…お前を待つんや? …好きやなかったら、…誰があんな風に…」
お前を待って、毎日、ここに来て。
あの台詞、思い出して。
その言葉に涙が何度も溢れる。
覗き込んだ彼の瞳も濡れていて、惹かれるように唇を重ねた。
桜が散る。
桜は、今も散る。
桜は、彼の涙だから。
桜は、―――――彼の命だから。
『 例え、一度離れても巡り会うだろう。桜が散る限り、…命は続くから 』
それは、あの家にいつの間にかあった、昔の誰かの、残した言葉。
2008/10/24 THE END