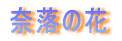
-blind summer fishⅣ-
前編-【月の遊迷】
消さないで
「……?」
不意に聞こえた声に耳を澄ませたが、なにも聞こえない。
(気のせい…?)
首を傾げた白石は、下で聞こえた寝言に視線をうつして笑う。
ベッドに横になって眠っているのは千歳だ。
「…千歳さん…寝てると可愛え」
くすくす笑って言ってから、光が聞いたらものっそう否定するんやろか、と呟く。
「あ、そういえば…飲み物昨日切れたっけ」
ベッドから降りて冷蔵庫を確認する。食品はあったが、綺麗に飲み物がない。
「…ちょっとそこのコンビニまで買いに行ってこよ。…大丈夫やんな」
書き置きしようとも思ったが、最寄りのコンビニは行き帰りを含めても十五分だ。
いらないな、と判断して財布を持つと家を出た。
コンビニで自分と千歳の好きな飲み物を数本買って道路に出る。
背後できゃーという悲鳴。多分、俺がこの辺に住んでいるのは知っている筈だから、もう馴れた。
家まであと数分、というところで声がかかった。
「はい?」
見知らぬ、男の人、だと思う。
“思う”なのは、知っている気もしたから。
(なんやろ…? 知ってる気が…けど…思い出せへん…?)
「すいません。時計が故障してしまって。
時間を聞いていいですか?」
「…ああ」
自分の腕時計を見て現在時刻を告げる。
「ありがとうございます」
「いいえ」
「ほら、これがおかしくなってまして」
男が手元から懐中時計を取り出した。開かれた文字盤を見て、首を傾げる。
「…これ、あってますけど…」
そう言った時だ。視界が歪んだ。
「……あ…れ……?」
途端真っ暗になった視界で、意識も遠ざかったと気付く術はなかった。
ふ、と意識が戻る。
寝起きで寂しい思考で、傍の身体を抱き寄せようとしたが、いつまで経っても傍の身体に手が触れない。
「……」
おかしい、と目を覚ますと、隣は誰もいなかった。
それも、そこのシーツは暖かくない。いなくなって、結構経っている。
「白石?」
呼ぶが、返事はない。
「白石!?」
繰り返し呼んで、部屋中を探すがどこにもいない。
玄関に靴はなかった。
千歳は急いで靴を履くと、家を飛び出す。
片手に持った携帯で、謙也に電話をかけながら。
「ほな、いつもどっか行く時はここの道しか通らないんやな?」
ものの数分で来た謙也(家は徒歩五分のところだ)は財前も連れてきてくれて、いつも通る道に立って言った。
「ああ」
「…どないしたんやろ」
「謙也くん、千歳先輩、これ」
遠くから走ってきた後輩が手にコンビニのビニール袋を持って、二人に見せた。
「これ」
「買ったばかりのジュース。水滴浮かんでるから間違いない。
あと、中に入っとった財布、これ白石さんのですよね?」
「…っ」
「どこ落ちとった!?」
「向こうの…」
指さした道の方に向かい、そこから見えた普段使わない道に入ってみる。
「…白石…?」
視界の隅に倒れているのは、間違いない。
「白石!」
駆け寄った千歳が青ざめて抱き起こすが、怪我もなにもなく、ただ意識を失っているだけだった。
部屋に連れ帰って、ベッドで眠っている白石を見遣って、心臓酷使した、と謙也。
「だけん、ただ貧血っぽくてよかったたい」
「ただ、なんであんなとこに倒れとったかが疑問ですけどね…。
ジュースの袋はもっと離れたところに落ちとったし」
「不安煽るなや光…」
「すいません」
財前が謝った時、ベッドの白石が呻いた。
「白石!?」
謙也の声に、数回瞬きした瞼が開いて、のそりとベッドの上に起きあがる。
「…あれ、謙也さん?」
「心配したで? 貧血かいな」
「…ええと…すいません。覚えてない」
「しっかりしてください。まあ無事でよかったけど」
「ごめん光…」
「千歳なんかほんま真っ青になっててなぁ。な?」
謙也に振られて、千歳は傍にしゃがむと笑った。
「ばってん、ただの貧血ってわかったけんよかったと。
ただ、今度からは出かける時はちゃんと俺起こして……、白石?」
最後まで言う前に、白石がただ自分を凝視していることに気付いた。
…気付いてしまった。
「…白石?」
呼びかけた千歳を見つめて、白石はただありのままのように言葉を紡ぐ。
「…あなた、誰?」
空気が、止まった気がした。
(………え?)
「…白石?」
「…誰? 謙也さん、この人…誰ですか?」
「白石!? 千歳や! 千歳千里!
俺らのグループのメンバーでお前の先輩で、お前の…………恋人」
「………え」
びっくりした白石がすぐ謙也を見て笑った。
「ちょ、やめてくださいからかうん。知らん人やし。
それに恋人て…男やないですかこの人…。そんな……あり得へんし」
「…白石?」
「……え、………光までそんな目……え……ホンマ………に?
俺が……覚えてへんだけ………? この人を………?」
茫然とした白石が初めてのように千歳を見上げた。
「……しら、いし?」
千歳の呼ぶ声が、遠い。
「……白石? 嘘…やろ……? 俺んこと……嘘…」
いつも、近くで聞こえていたような気がするのに。
「……白石? …忘れとると…?」
今、もの凄く、遠い。
「…俺に、あんなに好き言うてくれたこともキスも、なにもかも…全部覚えてなかと…?」
わからない。
「……やけど…俺は…あなたをしらん」
そう答えた瞬間、肩を掴まれてもの凄い力で引き寄せられた。
なにか発する前に唇を塞がれる。
思わず彼の服を引っ張ったが、力は強く離してくれない。
大きな手が服の中に入り込んで肌を撫でた瞬間、背筋をなにかが走った。
「…っやめろ!!」
渾身の力で腕を振るう。それが顔に当たったのか、千歳の腕が緩んで抜け出せた。
彼の顔に赤い筋が出来ているが、それすら構わず彼は茫然と自分を見下ろした。
ただ、信じられないと。
「…なんでこないなこと……。俺はあなたなんかしらんし、会ったことない!
…気持ち悪い」
「……しら」
掠れた声が千歳の唇から漏れる。
聞きたくない。
「…しらいし」
けれど、その声は今すぐ泣きそうだ、と思った。
あの後、白石は謙也のアパートに泊まっている。
数日ぶりに全員で集まったスタジオで、彼はいつものように笑った。
記憶が戻ったのかと期待したが、違った。
「…えと、この前、ごめん。ホンマにあなたも柊のメンバーやてみんなに聞いて。
俺が忘れとるだけなんやってわかって。
ごめん」
「……いや、…よか」
「ごめんな。…あ、と…あなたの名前」
胸が、痛い。
「千歳、や。千歳千里」
謙也の気遣った声に、ああ、と白石は気付かず笑う。
「千歳」
「…白石っ」
「…よか」
「…」
「ほな、千歳。ごめんな」
「…うん」
自分の席に座りながら、胸が斬りつけられたように痛んだ。
“千歳さんは? どう思ってます?”
使われない敬語。
呼び捨ての名前。
俺を知らない笑顔。
…全部全部、痛かった。
不意にスタジオの扉がノックされた。
「はい?」
マネージャーだろうか、と謙也が声をかけると、見知らぬ青年が入ってきた。
栗色の髪の、整った美貌の青年だ。白石ほどではないにしろ。
白石が、びっくりしたように椅子から立ち上がった。
「こんにちは。ええと、柊の忍足くんに、財前くん、千歳くん、であってますか?」
「あ、ああ。お前は?」
「近々デビューするユニットのボーカルの、梶本貴久と言います。
急にすいません。ただ、白石くんがいると聞いたので」
物腰は丁寧だが、口から出た白石の名に千歳が顔色を変える。
「白石が…? なんや?」
この間の一件を覚えているだけに過敏になる謙也たちに笑って、そう警戒しないでくださいと言う。
「僕はただ、昔の恋人に会いに来ただけです」
「……え」
「僕は、白石蔵ノ介の元恋人ですから」
「……………」
白石は言った筈だ。全部、自分が初めてだ。と。
なのに。記憶を失ったショックも引きずって、混乱しそうになる千歳を遮ったのは白石本人だった。
「違う!」
「白石…?」
「なに言うてるん…? それは、梶本とは中学一緒やったけど。
ちょっと話する程度やったやんか。付き合うてなんか絶対ない」
「…そうですか? でも、僕に好意があると思ってましたが」
「それは侑士以外で俺とまともに話してくれる人があんただけやったからや。
多少好意持ったって仕方ないやろ。
他はみんな…病気で俺を嫌がったし。
…とにかく、俺は付き合うたつもりなんか全然ない」
「…そうでしたか。誤解したようで、申し訳ない」
「……別に、わかってくれたならええけど」
「でも、今、白石くんには特別好きな人はいないんですよね?」
「…は?」
「僕は今でもキミが好きなので。…いないなら、立候補しようかと、改めて」
「冗談やめてや」
「冗談じゃなく本気で。…キミが好きです」
謙也たちも流石に止めようとした。
「まあ、キミに恋人がいるなら諦めますが…」
胸が痛むのは、彼の頭の中にそんな存在がいない事実。
それでも、渡せるわけがない。
千歳が白石を庇うように彼の前に立とうとした時だ。
「…おる」
耳を疑ったのは、千歳だけではない筈だ。
「恋人は、おる。やから諦めてくれ」
白石がそう言い切ったからだ。
「誰ですか? 白紙領収書は証明になりませんよ」
「…っ…ここにおる」
強く言った白石が千歳の服を掴んだ。
「俺は千歳と付き合うてる」
「……しら…いし」
「千歳が俺の恋人や。…他に好きな人なんかおらん。
やから、」
「……」
梶本もかなり驚いた様子で、しばらく唖然としていた。
「…なるほど。千歳くんと、…わかりました。
負け犬は退散します。では、今度は音楽番組で」
踵を返した梶本がいなくなって、落ちた沈黙を破ったのは白石だった。
「……ごめん」
千歳に、そう言った。
「……この前、あんなに否定しといて。あり得へんとか、気持ち悪いとかひどいこと言って傷付けて…なんに、こんな時ばっかり…利用して。
…ごめんなさい」
「…白石」
「…………」
忘れてごめんなさい。
落とされた言葉に、胸に宿るのは間違えようのない喜びで。
そっと抱きしめた。白石は今度は拒まず、少し恥ずかしそうに見上げてくれる。
「…よか」
「…え」
今度は、心からいいと言えた。
「白石が、覚えてなかのに、俺を真っ先に選んでくれた。
俺を恋人って、言うてくれた。また選んでくれた。
…俺は、そいだけで嬉しか」
嘘はなかった。
嬉しかった。
忘れてなお、彼が自分を“愛している”と選んでくれたことが。
…嬉しかった。
痛んだ傷が、癒されていくような心地だった。
「……………俺、思い出すから」
「え?」
「千歳のこと、頑張って思い出すから…。
…待っとってくれる?」
そう、見上げて言われて、笑うことが出来た。
「…うん」
呼び捨ての名前。
使われない敬語。
でも、いい。
彼が俺に微笑むなら。
それで今はよかった。
→NEXT