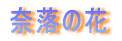
-blind summer fishⅣ-
後編-【終わらないキス】
「なぁ、謙也さん」
謙也の家に泊まり込んで、一週間経つ白石が不意に言った。
ベッドに座ってクッションを抱えた彼の声に、謙也はフライパン片手に顔を傾ける。
「ん?」
「…俺、千歳と住んでたんやんな?」
「…ああ、そりゃな。恋人やし」
「……いつから?」
「え?」
白石から千歳のことを滅多に聞かないので、謙也は驚きながらも、これはチャンスかもとダイニングを出た。
「いつから住んでたん? 学校の同級生? 中学? 高校?」
「…いや、千歳は俺と光と同じ中学や。一年の時からな。
九州から来た」
「……じゃ、違いますよね」
白石にも謙也と財前の記憶はある。謙也や財前と同じ中学に通っていなかったことはわかる。
「うん。千歳とお前は、一年前に会った。俺らと一緒に。
あの、お前がデビューしてすぐの、音楽番組。
お前の記憶にはないやろけど、光がお前の楽屋見つけて、…出てきたお前と、…初めて会った」
謙也の言葉に、感じるのは懐かしい色彩。
確かに覚えている。謙也たちと初めて会った日。会えて舞い上がっていろいろ話して。
「……次、…事務所の部屋で…俺が…病気起こして…せやのに、…一緒にやろ…言うてくれた」
「…うん」
「……そこにも、あそこにも…千歳もいた……?」
「うん」
「…………」
「俺達の中学の昔話をするたび、お前は遠慮していなくなった。
お前を連れ戻すのは千歳の役目やった。
ある日、嫌がらせでお前が閉じこめられて、千歳が…助けに行った。
扉をけ飛ばして壊したらしくて、お前がものっそうびびってたって千歳が言うてた。
…お前の素直なとこが大好きやけど、たまに苛めてる気分になって困る、とも言うてた。
…ある日、連れ戻した時、お前は初めて俺達のことを自分から聞いたらしい。
…俺達の通ってた学校は、大阪? 九州? って…」
―――――――――――忘れてはいけない記憶。
思い出せないのに、なのに、痛くて、苦しくて。
「…白石?」
言葉なく泣き出した白石に驚きながら、謙也は抱きしめて話し続けてくれた。
翌日、スタジオに集まった千歳を見つけて、白石が駆け寄ってきた。
「千歳」
「ああ、白石。どげんかしたと?」
「あのな、俺考えたんやけど」
「うん?」
「“親友”になってくれへん!?」
白石の言葉に、財前が持っていた本をどさっと落とした。
どうやら真剣らしい白石は気付かない。
「…あ、いや、……その…千歳から色々聞いたら、思い出すかもしれへんから。
やけど、千歳は俺んこと恋人って実感あっても、俺はない。
否定する意味やないねん! ただ、俺にも千歳との確かな絆っちゅーか、なんか欲しいねん。そしたら、多分安心して傍おれる…。
から……」
白石なりに必死なのだ。気付いた。
「白石」
「え?」
「抱きしめてよか?」
「へ?」
「スキンシップみたいな感じにしかせんから」
「………うん」
ゆっくりと腕の中に囲い込んだ。
いつもとは違う抱擁だけど、背中に回される手はないけど。
俺を覚えていないことは、白石だって怖かったんだ。
「うん」
「え?」
「うん。よかよ。親友」
「…ホンマ?」
「うん」
「…よかった」
少しずつ、近づけばいい。
謙也の家への帰り道だった。
謙也が少し遅れると電話があって、待ち時間に傍の公園に入った。
「…うわ、懐かしい」
「ブランコが?」
「うん」
聞いた千歳に、無邪気に微笑んで白石がブランコに駆け寄る。
「学校では…あ、千歳、俺の学校の話、俺から聞いた?」
「ううん。あんまり聞いてなか」
「そか。
あんな、俺の学校、大きくてブランコとかもあったんや。中学やのに。
やけど、俺はみんなに嫌われとったから、授業が終わったらすぐに帰ってた。
侑士と……梶本が一緒におるときだけ、学校に残ってられた」
“梶本”
白石の口から落ちるその名前に、胸がざわめいた。
白石を好きだということも、白石が親しそうに呼ぶことも。
なにより、彼にはなにか不信を感じて。
「…梶本は…優しかった。
俺が病気何度やっても、笑っとってくれた。
親の都合で三年に進級する前に転校してまうまでずっと三人でおった」
ブランコに立って乗って、きぃとこぎ出した白石が懐かしそうに言う。
「…やからびっくりした。この前。俺を好きとか、…元恋人とか。
…あんなこと言うヤツやなかった。俺の気持ち、無視したりせんかった。
……梶本は…っわ」
「っ…白石!」
考えごとがまずかったのだろう。バランスを崩して動くブランコから足を踏み外した白石に駆け寄り、咄嗟に抱き留めて抱えた。
夕闇にやけに、ガン、という音が響いた。
「~~~~~~~~!」
白石を無事キャッチして抱きしめたまま、呻く千歳を見上げて、白石はぽかんとしていた。
「…千歳? …ありがと…やなくて…ぶつかったん?」
「…うん。お前受け止めたら後ろからやってきたこいつ(ブランコ)に頭がつん…って」
「っはは……いや、ごめん。おおきに」
「いや…よか」
至近距離での笑顔にどきどきしながら、今はキスなんか出来ないから。
離れようとした。彼がその前に笑った。
「昔、梶本もおんなじように俺、受け止めてくれたわ」
「…」
言うな。
「そんで、やっぱり今の千歳みたいに頭、ぶつけて呻いとった」
言うな。
「そんで、俺はやっぱり笑って、梶本に“笑い事じゃない”って言われた」
他の男の話を、俺の腕の中で言うな。
「…でも、」
ふ、と微笑んだ白石が軽く伸び上がった。手が、千歳の肩に触れる。
「…梶本には、絶対こんなことしたいなんて思わん」
伸び上がって近づいた白石の顔が、もっと近づいて、唇にふわりと触れた感触。
すぐ離れた彼の顔が、照れたように笑った。
「……覚えてへんのに、…今お前の顔みてたら、…キスしたなった」
それでやっと、白石がキスをしてくれたと気付く。
一瞬泣きそうに歪んだ千歳の顔が、すぐ見えなくなった。
千歳が自分を抱きしめたからだ。
「……千歳? ごめん…。痛かった?」
「…ううん」
「千歳?」
「…ううん…。嬉し…かった…。嬉しかったと…」
「……千歳」
急に吹いた風が公園の砂を巻き上げる。
「そろそろ、謙也帰ってくる。行こう」
「うん」
身体を離して、立ち上がると手を引っ張って白石を立たせた。
また、風が砂を煽る。
「…っ」
「あ、千歳? 目に砂入ったん?」
「うん…」
しまった。左目だ。
「アカンてこすったら!」
「ばってん…痛か」
「右目事故で見えへんのにっ…残った左目に傷ついてしまうやろ!」
―――――――――え?
千歳の当惑に気付かない白石が千歳を屈ませると、伸び上がって、瞳をぺろりと舐めた。
「そこに蛇口あるから、洗って…千歳?」
「…白石。俺ん右目、見えなかって…誰から聞いたと?」
「え? いや、千歳が言うたんやんか。入ったばっかの頃、自分も問題児やとか言う……」
言いかけて、白石ははた、と口元を押さえる。
「白石…、思い出した…と?」
「……え、あ…いや………そこ、だけ」
白石自身困惑して言った後、不意に千歳を見上げて驚く。
「な、なんで泣くん!?」
「……あ、」
瞳から溢れる涙を拭いながら、千歳は「ばってんしょんなか」と言った。
「…たいが…嬉しかもん」
笑いながら泣く千歳を見上げて、白石は困ったように頬を染めたあと、慰めるように頭を抱き寄せてくれた。
謙也の家に白石を預けた後、徒歩十分ほどの家までの散歩を千歳は少し楽しんだ。
寒い風が身に染みても、胸は暖かかった。
白石の記憶は少しずつでも、戻るのだと実感出来た。
それが、今はただ。
「こんばんは」
不意にかかった声に、自分のマンションを見上げると、その入り口に壁に背を預けて立つ男。
「……梶本」
「キミに呼び捨てにされる義理はありませんが、まあいいでしょう」
「なんね?」
「千歳くん、喜び一杯のところ悪いですが、白石くんの記憶は未来永劫戻りませんよ」
「……は?」
「確かに時間が経てば戻る。キミが傍にいるならなおさら。
でも、戻り出すたびに術を重ねてかけ続ければ?
…催眠の繰り返し。…やがて解けない程強固になる」
「……なに、言うとーと…?」
梶本は手の平で遊んでいた懐中時計を開く。
千歳に文字盤を向けて微笑んだ。
「この懐中時計は僕の催眠術の道具です。
…これで白石くんからキミの記憶を奪ったんですよ」
理解は遅れた。理解より、怒りが早かった。
「…っ―――――――――――――」
勢いのまま梶本の胸ぐらを掴み上げる。
「なん…なんでそげんこつ…っ!」
「わかるでしょう? …彼が好きだから」
梶本がそう言葉にした瞬間、身体から力が抜けて地面に崩れ落ちてしまう。
「…っ?」
力をいれようとしても指に力が入らない。
「怖いでしょう? 催眠術は身体の自由も奪えます。
キミは僕を止められない」
「…白石…に…」
「…しぶといですね」
「…白石を傷付け…たら……泣かせたら…許さなか。
…………殺す」
「これは怖い。
…長期戦はやめた方がよさそうだ。
…催眠術で、跡形なく人の記憶を根から消す方法があります。
ですが僕はそれを使わなかった。使うことは出来た」
「……?」
「その術の使用は対象の人間から深く根付く記憶全てを奪う。
しかし、催眠術は便利ではなく、ある一個人の記憶のみを完全消去することは現在不可能。
僕が知るその術は、対象の人間の記憶“全て”を根元から消去する非常に利便性に悪いものです。その術の使用は――――――――その人間の心そのものを跡形なく破壊する」
「…っ!!!?」
「それでも、僕は彼にそれを使うでしょう。
…僕の記憶すら彼がなくしても。…彼を得るために」
言い終えると、梶本は踵を返した。
「ま…待っ…!」
術が抜けきっていない。まだ身体が動かない。
それでも足掻くようになんとか身体を起こした時には、彼はどこにもいなかった。
「梶本!? あいつが!?」
翌日、事務所に来た謙也に昨日のことを話した。
謙也はテーブルを叩いて、自分の頭をかき回す。相当怒っているとわかったが、自分も否定はできない。
いや、怒りより勝っているのは恐怖だ。
白石を失ったら――――――――――という底なしの穴に落ちるような恐怖。
「あれ、二人してどないしたん?」
「光! あんな…………お前、白石は?」
「え? 白石さんならさっき、携帯の電波が悪いって公衆電話…」
言いかけた財前の傍を突き飛ばす勢いで走っていった千歳に、財前は謙也の顔を見て、すぐ千歳の後を追う。彼も一瞬で、事態を把握した。
「…侑士、心配しとったな」
幼馴染みに電話をかけた後、白石は深く考えず通路を歩いていた。
身体は道を覚えているもので、考え事をしながらでもいつも行く部屋につく。
「…そんな心配かなぁ……………」
考え込んだ時、視界に映ったものに、白石は一瞬で思考から覚めた。
薄暗い。
どこかのスタジオだ。
何故、こんなところに来ている?
背後で扉が閉まった。
「…っ」
明かりがぱっと点く。
「……梶本?」
扉の前に立っているのは彼だった。
「なに…?」
梶本は無言で手に持っていた懐中時計を開く。
その開かれた文字盤に、見覚えがあった。
(あ………)
そうだ、あの日、あの日、買い物に出かけた自分に時刻を聞いてきた人。
思い出せなかったんじゃない。思い出せないようにさせられた。
あれは梶本だ。
自分の記憶を奪ったのは―――――――――――――!
「気付いてももう遅かった。
文字盤を見てしまったあとでは」
「……あ」
身体が、動かない。
膝が勝手に折れて、床に手をつく。
「キミから千歳くんの記憶を普通に奪うことが出来ないのはよくわかった。
だから、…キミの記憶全てを消去する。忍足くんのことも、財前くんのことも、…あの忍足侑士のことも、…僕のことも、…全て忘れてください。
…それで今度こそ、キミは彼を忘れ去れる」
「…や、………いやや」
目が、文字盤から逸らせない。
時計の針がこちこちと動く。
「……あ」
“うん、よかよ、親友”
消えていく。
つもった雪の上につけた足跡のように。
“…うん。お前受け止めたら後ろからやってきたこいつ(ブランコ)に頭がつん…って”
消えてしまう。
初期化されたパソコンのデータのように。
“いや…よか”
消えないで。
要らないメモリのデータのように。
“たいが、嬉しかった”
失いたくない。
かけなくなった電話番号のように。
“白石”
消さないで―――――――――――――。
「いや……や……っ…ちと……千歳…千歳………とせ…………」
耳を両手で塞いでも、涙で視界を塞いでも、どうしようもない。
意識すら、遠のいていく。
いやだ、なくしたくない。
意識を失ったら、きっとあなたを忘れてしまう。
「…ちと…千歳…千歳……さ…千歳さん…っ…千歳さん…!」
「……」
「ちと…せ…さ」
そう最後に嘆いて、倒れ込んだ身体を受け止めたまま、梶本は言葉を発さなかった。
靴音が響いて、すぐ扉が蹴破られる。
「っ…貴様!」
低く呻いて駆け寄った千歳が有りっ丈の力で振るった拳が顔を殴ったが、梶本は血を吐き出すと無言で白石の身体を彼に渡した。
「……………、…」
「気を」
「……」
「気を失わせただけです。…あの術は使ってません」
「…なんで」
白石を抱きしめて見上げる千歳を立った姿勢で見下ろし、笑った。
自分を。
「気を失う瞬間まで、壊れるようにキミの名を呼んだ人間の、キミの記憶を奪えるわけないでしょう?
“千歳さん”と…“千歳”ではなく、そうキミを呼んだ彼を、壊せるわけがない」
「…梶本?」
「……僕は本気で彼が好きだったんだから」
誰より愛しい人の心を、この手で壊せるわけがない。殺せるわけがない。
そんなこと、わかっていた。
梶本は手に持っていた懐中時計を床にたたきつけると、足で踏んだ。
文字盤が割れて壊れて破片が散る。
「…もう催眠術は使いません。…使いたくもない。
……心配しなくても、もう白石くんになにもしません」
言って梶本は千歳に背中を向けた。
「このゲームはキミの勝ちですよ。千歳くん」
「梶本…お前」
「もう会いに来たりしませんよ。…敗残者にその資格はない」
最後に振り返った顔に浮かぶ笑みに、もう言葉をかける意味がないと悟って、千歳はやめた。
方法も、許せたことではないけれど。
彼はそれでも、本気で白石を愛しく思っていた。
だから時計を手に取った。
だから、心を壊せなかった。
否定するには、自分にも覚えのある思いばかりだ。
「……ん」
「…、白石?」
「………」
ふと開いた瞼が、ぱちぱちと瞬きをして、千歳をはっきりと認識する。
信じられないように千歳を見上げた顔が、やがてふありと微笑んだ。
「……今度こそ、あなたを忘れて、わからなくなると思ったんです」
「…しら」
「でも、覚えてる。思い出せる。初めて会った日も、あなたに歌ったうたも、…初めて抱かれた日も。
…心配かけて、ごめんなさい。……ただいま、千歳さん」
「……」
“千歳さん”
呼ばれる名前は、初めて会った日と同じ敬称。
話す声は、聞き慣れた敬語。
向けられるのは、綺麗な笑顔。
「………っ………。」
きつく抱きしめて、髪をそっと撫でる。
背中に回される腕。
「…お帰り、白石」
腕の中で、彼がやっと、いつものように笑った。
「ちゅーか、梶本が」
数日後、楽屋で口にした白石に、いぶかしげに謙也が彼を見た。
「あいつが?」
「デビューするやないですか?」
「ああ…」
「あれ…謙也さんしらんのですか」
「…?」
「…二人グループやったらしいんですけど、もう一人飛び入りで決まって」
「それが?」
財前が興味なさそうに聞くと、白石が今日会うやろけど、と言って。
「もう一人が…」
その時コンコンっとノックされた楽屋の扉が開いて、姿を現したのはその梶本だ。
「お前っ!」
「ストップ忍足くん。喧嘩売りに来たんじゃないよ」
「なにをいけしゃあしゃあと! 全部聞いたで!」
「だからもう敵意はない」
「信用ならん!」
「というか僕は彼のお供です。いわば助さん」
「…は?」
ばんっと開かれた扉からよく見知った黒髪眼鏡が顔を出した。
「よ、ボ謙也」
「ゆ、侑士!? お前なんでテレビ局に!」
そこにいたのは白石の幼馴染み兼謙也の従兄弟。今は一人で暮らしていると聞いたが。
「デビューしたから。今日」
「は?」
「やから謙也さん、…梶本のグループの三人目の飛び入りが…侑士」
「そう、僕は侑士のお供だと言っただろう?」
ぬけぬけと言う梶本の横で侑士は笑って、そゆことやから覚悟せえと手を振る。
「とりあえず、ランキング一位は俺らがもらうから」
「……」
「ん? 喜びのあまり言葉ないん謙也?」
俺を誘ってたん蔵ノ介やなくお前やもんな。
「…んで」
「え?」
「なんでこうなるんや―――――――――――――!!!」
「あ、ボ謙也火山の噴火や。行くでー梶本」
「はいはい」
「二度とくんなー!」
「あはははは」
思わず笑っていると、不意に千歳に手をぎゅっと握られた。
「…心配せんでも、もう忘れたりせえへんです」
「…ばってんそんでも……傍おってくれ」
「……はい」
約束のように右目の傍にキスをした。
だから消さないで。
消えないで。
この絆だけはどうか。
決して溶けない雪の結晶のように。
THE END
→後書き