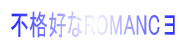
-blind summer fishⅢ-
前編-【それが彼の思考回路】
人を好きになるって、どういうことなんやろ。
「お、光! これええんやない?」
久々の休み、謙也と一緒に出かけた財前は気もなしに、はぁと頷いた。
普通の相手なら気分を害してはっきり返事しろと言うところだが、謙也に限ってそれはない。
「そっか。やけど、これ…白石にはちょお派手過ぎるかもなぁ…」
「…あー…あの人には、確かにちょお派手かもしれんですね。
あの人の中身がテレビにしか出てない部分そのまんまの性格なら別に似合うんやろけど…」
謙也の取った服は綺麗な柄シャツだったが、白石には多少華美かもしれない。
彼の中身が外見から連想される通りのクールな性格なら、文句無しに似合うだろうが、彼の中身は実際、とても素直で純真無垢という言葉が似合うので。
そんな白石を知っている謙也と財前には、派手かも、と思えるのだ。
「千歳先輩がおったら猛烈に反対するんやないですか?
“そげなもん白石には似合わなか!”…て」
「…ああ、うん、めっちゃ予想でける…」
遠い目をした謙也が服を畳んで棚に戻そうとした時、背後で声がかかった。
見れば店の女の店員が、目を期待に輝かせて見ている。予想はお互いについた。
「あの! 『柊』の謙也さんと財前さんですよね?」
やっぱり。
『柊』――――とは千歳、白石、謙也、財前のグループの名前だ。
滅多に声はかけられないが、外見をそんなに隠さず出かけるため、見つかるのは仕方ないといえる。
そして、見つかったからと言って、嫌な顔をしたり、逃げたりするタイプでは、謙也も財前もない。
「ああ、そう」
「やっぱり! お買い物ですか? いつもここ来ますか?」
「買い物。ほら、白石がうち入ってもうすぐ一年やから、記念にプレゼント探してんねん」
「白石さんへのですかー。綺麗だから選ぶの気を遣っちゃいますよね。
あ、謙也さんも財前さんも綺麗ですよ!」
「おおきに」
謙也が愛想よく笑うので、店員は顔を見合わせてきゃーと声を上げる。
「謙也くん、これは?」
財前もこういう場所であからさまに嫌な態度はとらない。或る程度の常識的態度はわかっている。あくまで自然に、謙也と店員の会話を断ち切ったが、この言い方ならば邪魔された、とは店員も思わない。
なにより。
「うわっ…財前さんの声聞けた…っ! かっこいいー!」
柊のファンは現在、五割が白石、残りの二割は財前ファンであるため(残り三割は千歳・謙也ファンだ)(なにより白石が入る前は不動のナンバー1人気は財前だ)、番組では寡黙な財前は口を一言利くだけで騒がれる。
「ああ、これか。ええんやない?
柔らかい色味やし。似合う思うわ」
「なら、俺はこれにします。あの、お会計、お願いしてええですか?」
「は、はい!」
素っ気ない口調に多少笑みを乗せて言うだけで店員は頬を真っ赤に染めてレジの方に移動する。
(流石、光。うまいわ…)
さりげなく決まっていない謙也を店員から解放してくれたと理解しているので、本当に隙のない後輩だ、と感心する。
一方で多少、俺を放置するくらいそいつの方が好きか、と思うが、謙也もあまりそんなことはどうでもいい類なので、やはりほんのちょっとの感情だ。
結果、気にせず服選びに戻った謙也を視界の隅で見遣って、財前はひっそり息を吐いた。
ことは、三日前に遡る。
「ほんま千歳先輩と白石さんて仲ええなぁ…」
謙也がたまたま席を外していた昼食、そんなことを急に言った財前に、二人はきょとん、と視線を向けてくれた。
「なんね、光、今更」
「いや、確かに今更っていったらものっそう今更なんすけど…ちょっと白石さん笑わんでください…。
いや、…仲ええなぁ…って」
「それこそなんね。光、そげんこと気にばせんくせに」
この人に『癖に』とか言われたらお終いだ、と思いつつ口にはしない。
「いやぁ…人好きになるとそんな変わるもんなんやなぁ…て」
「…光? どないしたん?」
「…や、…………白石さん」
白石の言葉に、一度否定しかけて、呼んだ。
「ん?」
「千歳先輩、好きってどんな感じ?」
「え? そらしあ…ってなに言わせるん…」
気付いて真っ赤になった白石に、いや、と淡々と言う。
「率直に」
「…そら、…幸せっちゅーか、…一緒におりたいっちゅーか、…おったら幸せっていうと…それも違う」
「違かね…?」
「…う、そら…おるだけや寂しいから…触って欲しいとか…抱きつきたい…とか色々あるやないですか」
千歳に食いつかれて、白石は赤くなりながらぽつぽつと口にする。
途端可愛か!と抱きつく千歳を普段ならはいはい勝手にどーぞと放置する財前だが、今回は違った。
「好きになった時、ちゅーか瞬間、って覚えてます?」
「…え? …覚えて…へん。気付いたら、あ、俺好きなんや…って思って。
……光? どないしたん?」
「千歳先輩は、あの時ですよねぇ…」
「光?」
二人にいぶかしがられて、財前ははぁ、と溜息。
「…俺、人に興味あらへんかったからわからんねん」
「…なにが?」
「…人好きになるって、どういうことなんやろ」
「「……………………」」
二人分の沈黙って結構重いな、と財前が思った時だ。
「光、人好きになったこと…ないん?」
「ない」
「…そういえば、付き合うた子って光はおらんね」
「ないんですか? 光」
「俺や謙也は多少あったけん、光はなか」
「あんたがばっさり否定することやないけど事実ですわ」
「…そうなんか…。…え? 誰か好きな人がおるかもしれんくて悩んでるん?」
「ちゅーか…人好きになるってどうなんやろ…って二人見たら思ったんですわ。
二人見てたら意外と悪ないことかもしれへん、て興味沸いたちゅーか、人好きになってみよかな…って」
「光…意外とお前お手軽やけんね…」
「…やけど、俺興味ある人三人しかおらん」
「…それ、俺ら?」
「うん」
「…俺と白石は論外にしてな?」
「言われんでもするし」
「……え、それって光…」
白石が気付いて止めようとしたのかどうか、しかしその時に謙也が帰ってきて、どないしたんー?と暢気に笑った。
「あ、謙也くん」
「ん?」
「明々後日、暇?」
「暇」
「付き合ってや」
「ええよ、どこ?」
「服巡り」
「ああ、あー…ああ、わかった」
「流石謙也くん」
謙也は白石へのプレゼントか、と深く考えなかったが残された千歳と白石は思わず顔を見合わせる。
「…千歳さん、千歳さんまずいこと言ってしもたんや…ないんですか?」
「俺も今、そげん思った…」
まさか、グループきってのノーマルを自負する二人が、そんなことはないと思う。
しかし、先ほどの財前は限りなく本気だった。付き合い短い白石にもわかるほどにわかりやすく。
「……大丈夫、なんかな」
「…ああみえて、謙也…光に甘かしな…」
もう一度顔を見合わせ、二人は乾いた笑いを浮かべるしかなかった。
店を出て、二人で歩くと風が吹いてきた。
「うわっ…寒」
「もう秋ですからね」
「光、はよ行こ!」
手を握られて、走り出す謙也を自然追って、心臓が鳴ったのは三日前の会話の所為だ、と思いこんだ。
「ここまで来ればあとは地下から行けるしー……光?」
それでも、相当思い悩んだ顔をしていたのか、覗き込まれて驚いた。
「どないしてん…」
「…いえ」
びっくりした。
いや、ここ三日、謙也のことしか考えてなかったから。
思ったら、口にしていた。
「謙也くん」
「ん?」
「…俺、この間、ふと『人好きになるってどういうことやろ』って思い出したんです」
「…えらいいきなりやな」
驚いて、それでも付き合ってくれる謙也は、いい人だと思う。
「白石と千歳の所為か?」
「まあ…。で、あの二人見て、『人好きになるんも悪ないな』『人好きになって見ようかな』て」
「…お前はどんだけお手軽なんや」
「それ先輩にも言われた…。
で、…でも、俺が今までの十七年で興味持った人、三人しかおらんかった。
千歳先輩と、白石さんと、あんた」
「ふうん。…ん?」
「でも、千歳先輩と白石さんはアカンから。
そしたら、あんたしかいなくて。
……この三日、ずっと謙也くんのことしか考えとらんかった」
「………………………」
「…謙也くんなら俺、好きになれるんかもしれん。
でも、どこからが恋愛の好きなんかな。どこまでが後輩の好きなんやろ。
わからんねん。わからんだけで俺、ほんまは昔から謙也くんのこと、ちゃんと好きやったかもしれへ――――――――――」
「ちょお待て!」
「………?」
ストップをかけられて、財前は言葉を止めたものの、不思議そうに見てくる。
「お前、…自分の言ってることわかってんか?」
「わかってますよ?」
「人好きになる、ってのはええ。
やけど、それが俺て…。男同士やぞ?
そんな簡単なもんちゃうねんぞ?」
「千歳先輩と白石さんかてそうやんか」
「あの二人はええねん! ちゃんとわかってやってるんや。
けど、お前はただ人好きになってみたいって好奇心で言うてんちゃうん?
本気で好きになった後考えてん? 無理矢理俺のこと好きになろうとしてるだけみたいにしか聞こえへん。
……そんな風に好きになられても嬉しないわ」
奇しくもアーケードの下、降り出した雨は謙也は濡らさないのに、そこからはみ出た財前を濡らした。
「…謙也くん、俺、冗談で言うてません」
「……そうやろな。冗談やないやろ。冗談とは思うてへん。
お前が、本気てわかるから止めてんや」
「…どういう意味スか」
「…お前、錯覚してるだけちゃうん?
俺が昔、お前を必死に止めたりしたから。
ほんで下手にずっと付き合い続いとるから。
おまえ、絶対いつか、他の普通の女の子好きんなる。
……今のお前の『本気』につられて付き合うて、…マジになったら俺が疲れる」
雨が強くなる。大粒が頬を叩いた。
彼は、なにを言っているのか。何を言っているんだろう。
自分はただ、思ったことを言っただけなのに。
そうしろと言ったのは、あんたやないか。
「……謙也くんは、俺をどう思てん」
「生意気で頼りんなる後輩や。今も昔も、大事な後輩。
…今は、大事な仲間。誰にも換えられん…仲間や。
けど、…今は」
「今は、ちょっと…お前が怖い」
雨は、強くなったまま夜まで降った。
風呂上がりにかかってきた電話に、白石が手を伸ばして取る。
「白石、誰?」
「んー待ってください…。もしもし…、光?」
「光? 珍しかね…」
そうだけ言って料理に戻った千歳のスリッパの音を聞きながら、白石はどないしたん?と聞いた。
『…白石さん』
「ん?」
『俺…、別にすぐ付き合うてくれとか、好きなんです、とか言うたつもりやないんですよ』
「……謙也さんに?」
『うん。ただ、…俺、謙也くんのこと好きやけど、これってどういう好きなんやろ?って思ったこと口にしただけやねん。
俺、思ったことすぐ口にするし。それだけで…ほんまそんだけ…。
謙也くん、そういう俺に一番馴れてんのに…』
「…どないしたん?」
『………怖い、て』
「…え?」
『…俺が怖い、て言われた。…俺、正直、謙也くんが好きかどうか、別にどうでもよかったんです。
ただ、たまたまそのことがずっと気になっただけで。
……なんに』
電話の向こうの声が、涙に滲む。
『…怖い言われて……今、…滅茶苦茶悲しい…』
「……光。今どこおるん? 今、外?」
白石の焦った声に、向こうで雨音に紛れて響いた声。
『……どないしよ。俺、ほんまはずっと謙也くん好きやったんや。
それこそ止めてくれた時から…。
気付かんかっただけで…。
…気づきたなかった…。
怖いて拒絶されんなら、ずっとあのまんまがよかった…』
「光!? どこおるん?」
『…………駅前の橋』
→NEXT