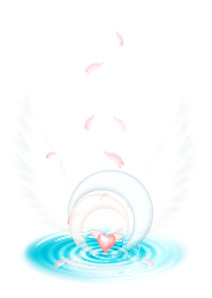 誓い去りし夢 第一話[堕ちた満月] 雪の中で、映える黒い翼を初めて美しく思った。 「なにがあろうと、必ず、キミの元に帰るから」 キミの翼だから、きっと綺麗なんだと、そう思った。 「一人にしないから」 黒く染まってなお、キミは美しいのに、 僕が愛した翡鳥〈スチュリティア〉はいない。 「待っていて」 雪に消えるように、見えなくなる姿に手を伸ばした。 空から降る雪は最期の景色で、 もう死ぬのだと知っていた。 帰れないと知っていて、帰ると約束をした自分を 憎めないキミを一人、俺達は遺していくのか。 幻に手を伸ばした。 指に、優しい手が触れる。 そこにいるはずのない、翡鳥〈きみ〉がいた。 窓から見る景色が、雪に変わっている。 雪が降る、今は寒い季節。 出先から帰る主人を待ちわびる白石の耳に、廊下を歩く二人の足音と、大好きな二つの声が聞こえた。 喜色一杯の笑みを浮かべて、白石は駆け出し、見つけた二人の片方に抱きつく。 「お帰りなさい! 無事でよかった。ご主人様」 「ただいま、蔵」 くしゃりと髪を撫でる橘の手に心地よさそうにすり寄った白石の頬に、横からキスが落とされる。そこにあった長身の上の顔に、白石は嬉しそうに微笑み、彼にも抱きつく。 その背中を抱く千歳の手が、今は翼のない場所を撫でた。 「お帰りなさい」 「ただいま」 「…ご主人様…怪我した?」 触れていればその天使の状態、気持ちがわかるのが世界でたった一人美しいとされた翡鳥〈スチュリティア〉だ。それは黒く染まってなお健在なのだ、と千歳と橘は早々に気付いた。 「うん、ばってん治してきたけん…」 「嘘や。まだ痛い…」 無垢とさえ感じる表情に辛さを浮かべて白石はそっと千歳の頬を両手で包み、キスをせがむ。すぐ降りてきたキスに奪われた呼吸と、吸い取られていく力。むしろ惜しみなく自ら千歳に与える身体を抱いていると、腕の中で彼が笑って言った。とても幸せそうに。 「俺のこと、全部食べてください。ご主人様。そうすれば治るやろ?」 「…うん」 その頬を撫で、髪をくすぐる千歳の腕から奪わないまま、橘がその手だけを取って口付けた。 「俺も少し疲れた」 「はい」 それが請求する行為に嫌な顔一つしない、嬉しそうな無垢な顔。 墜ちたから。彼は黒く染めた自分と橘にひたすら盲目に愛情と身体を捧げる。 それが、墜ちた天使が墜とした主に持つ、刷り込みの心。 「蔵。今日、俺も桔平もたいが疲れとうけん、多分かなり手荒くすっけん…ごめんな?」 「ううん、…嬉しい。ご主人様にされるの、好きや」 ただただ、無垢な子供のように答えて笑う姿を千歳が一瞬辛そうに見たのを、橘だけが気付いていたがなにも言わなかった。 桔平だけが気付いている。 自分が、墜ちた彼に言いようのない後悔を抱えていること。 もう、自分が愛した翡鳥〈スチュリティア〉じゃない。もういない。 そうしたのは自分。世界で一番美しい、自分が愛した天使を殺したのは、自分。 汚して墜としたのは、自分だ。 自分に、橘に盲目に尽くし、疑いすら持たず身体を毎晩預け、力を喰らわせる。 そんな淫らな、それでいてなお無垢な顔をした彼を、見るのが辛くて、多分仕方がない。 もう、自分自身の心で俺達に語りかけ、笑う彼はいない。 「千里」と俺を呼ぶ、彼は、いない。 あの日、俺と桔平が殺したんだ。 傍にいたくて、自分から望んで殺したのに、こんなに苦しい。 もう、あの天使はいない。 噴水がかかる庭に、彼はいた。 共存を最初に選び出したのは、翠と蒼の天使たちだ。 けれど、差別は当たり前にあり、翠の天使は蒼の天使を認めたが、それ以下の天使たちは認めなかった。 「謙也」 呼びかけると、生気のない顔が侑士に向けられる。 「聞いた…今」 一年近く前から、行方の知れない翡鳥〈スチュリティア〉。 いや、多くは死んだと思っている。 「信じとんのやて?」 傍に腰掛けた侑士に、謙也は白い顔のままで頷いた。 「…生きとる。白石は、絶対」 「……お前が言うなら、そうなんやろうけどな」 手をきつく握りしめた謙也のその手を、上からそっと握る。 「黒の奴らや…あいつらが…白石を!」 「……」 憎しみを一杯に浮かべた従兄弟に、侑士は辛そうに目を細める。 いつからだろう。この従兄弟が、そんな顔しかしなくなったのは。 「……そない、黒って悪いん?」 言った途端、謙也にきつく睨まれ侑士は首を左右に振る。「否定しとるわけやない」と。 「白石へのテロは兎も角、や。なにもしてへん黒もおるやろ。 …黒ってだけで悪いんか?」 「……しらん。しらん! あいつらはおったらあかんねん!」 ただ、そう憎悪だけを掲げる従兄弟に侑士は諦観したのか、なにも言わなくなった。 館に戻ると、館の主が侑士を出迎える。 「どうだった。従兄弟は」 「……どうもこうもない。最悪や。あれ」 侑士の言葉に、跡部は肩をすくめた。 「黒との同盟を結ぶ考えだっつったらなにするかわからねえな」 「翠がそうするわけやないんや。もう構えへん」 「…あいつだって、最初から黒を盲目に悪く思ってねえだろうさ。 今、翡鳥〈スチュリティア〉のことで過敏なんだろ」 「わかっている」と答える。跡部は一瞬沈黙しただけでなにも言わない。 「……別に、謙也が悪いわけやない」 自分も、跡部も、普通の天使ではない。 自分は蒼と交わり、蒼に染まった翠の天使の息子。 ハーフの天使は多い。だが、翠と蒼以外のハーフは、認められず隠れて生きるしかない。 自分と跡部が自由なのは、同じ翠と蒼のハーフだから。 天使は抱く側の色に染まる。 ハーフなら、二通り。 翠の天使を父親とし、母親を翠に染まった蒼の天使とするか。 蒼の天使を父親とし、母親を蒼に染まった翠の天使とするか。 前者なら、生粋の翠と蒼の中間の地位を持つ天使が生まれ、後者なら生粋の蒼と白の中間の地位の天使が生まれる。 自分は後者で、跡部は前者だ。 そして、この同盟が持ち上がったのは身内になった仲間の中に、黒く染まった蒼の天使との子供が、―――――――――――――黒い翼の仲間がいるから。 「……誰かが、悪いわけやない」 寝台にシーツを巻き付けた姿で眠るその髪を、そっと撫でた。 言葉通り手荒く自分たちに抱かれ、力を喰らわれた彼は糸が切れたように眠るだけだ。 「……千歳?」 白石の頭を自身の膝に乗せてその寝顔を見る千歳を、橘が見上げて呼んだ。 「ん?」 「………なんでもない」 「そうか」 言えることが、ない。 千歳は後悔している。 自分は、そんなに後悔していない。 彼はもう刷り込みの言葉と愛情しか表さない。 それを、千歳が辛く思うのは、仕方ない。 けれど、いつしか気付いた。 その刷り込みの表情、声、気持ちの底に、変わらない翡鳥〈スチュリティア〉の心があることに。 彼はここにいるんだ。変わらず。 彼は翡鳥〈スチュリティア〉のままで、生きてるんだ。 そう気付いたから、自分は後悔をしなくなった。 気付かない千歳だけが、辛く後悔したまま。 言っても、信じないだろう。都合のいい妄想だと、吐き捨てられるのが自分は怖い。 自分だって、その確信は誰かが馬鹿にすればすぐ消える、ろうそくの炎のように頼りないものだ。 千歳に馬鹿にされるのが怖かった。それによって折角得た、幸せな確信が揺らぐのが怖かった。 この天使を、永遠に失うのが怖いから、言わなかった。 →NEXT |
||