恋すてふ
わが名はまだき立ちにけり
人しれずこそ思ひそめしか
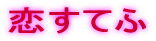
seasonⅠ-僕の優しいお姫様
第一話-【うたかたの姫君】
「ほな、俺は出して来るわ」
「ああ」
そういう小石川の声に見送られて、白石が教室の外に出た。
季節はもう冬だ。
あの暑い夏は過ぎ、秋も去って早い。
気の早い家がイルミネーションを飾り始める街が輝く、十一月の始め。
「白石、引退しても忙しかね」
「まあ、あいつはあれで四天宝寺『伝説の部長』やから」
「それは言えてるたい」
受験が余裕なのもあるが、ああやって引退した部の雑務を引き受ける白石は、やはりいい部長だ。
四天宝寺テニス部全員が、進路は附属の高校。謙也も楽に受かる成績と暢気だから、あわてているのはとんでもなく成績の低い連中だけだろう。
ちなみに、学校のレベル自体は高い。謙也は、あくまで白石に比べたら平均的な成績ではあるが、他の“平均的”生徒から見れば余裕で頭のいい部類である。
彼をいじる財前や小春がうっかり学年トップだったりするので、目立たないが。
「千歳せんぱーい。今、部…白石先輩行ったとこですか?」
「噂をすれば光。今行ったとこたい」
「は? 噂? …あ、曲がり角におる」
眉をひそめた現テニス部部長、財前光が廊下の向こうを見て遅かったと一息。
「元部長に仕事取られてんなや光」
「んな他人事な小石川先輩…。あの人滅茶苦茶作業能率ええん知ってんでしょ?
俺、最近やっと鍵当番もこなせるようなったんに、最初からそれはもちろんメニュー作成からいろんな雑務やっとった人ですよアレ。
比べんでください。俺が二つこなす間に六つくらい一足飛びしとるような人の速度に追いつかへんし」
「ハンデもろてもか」
「テニスはともかく、そっちはハンデもろても無理」
「テニスの方が無理やろ…」
「断ったらどげんね」
千歳の言葉に、あんた暢気やなと財前。
「俺もまだ教わらないとメニューとかわかれへんのです。
そんで一緒に作業しとればあの人勝手になんかやるし、迷惑やないし有り難いからっちゅーかなにより善意百%の行為に迷惑やとか言える神経や俺はない。
流石に受験入ったらあの人の方が気を遣わせるんに遠慮するやろけど」
「それ愚痴と? 光」
「一応愚痴ですわ」
「はぁ…」
「困らへんから困るんですわ。残る全員が白石部長離れできんくて」
「お前も含む?」
「ええ。俺達は入部した時っから部長のあの人しかしらん。
あの人が部長やったんや。俺んこと部長って呼びながら、白石先輩が来るとみんな“部長”ってあの人呼ぶん知ってんでしょ」
「嫌か?」
「俺も“部長”てあの人呼びますよ」
嫌やないから困る、と言い置いて財前はいなくなった。
「うちは、部員が部長離れ出来んのが悩みかもな」
「それ、桔平が言うとった。うちもて」
不動峰はしょうがない、という小石川から離れて、不意に窓から見える連絡通路に目が留まる。
そこに立つのは―――――――――――――。
(……白石?)
近づくと、謙也の通りのいい声が聞こえた。
「…いい加減フってくれや。なんでそない宙ぶらりんなん」
「……」
白石はその整った顔になんの感情も乗せず、謙也を見返す。
「…告白して三日経って、返事もくれんと…態度も普通って…なんでや」
「…謙也」
「…」
「お前、俺になんて告白したか…覚えとる?」
けれど、その時の白石の声は、僅かに辛そうだった。
何故かなんて、千歳にわかりようもないけれど。
「…え?」
「…覚えとる?」
「…そら…、『お前が好きや』て」
「…その後」
「……『男同士でもかまへん』…」
眉をひそめた謙也の言葉に、白石はあからさまに嘆息を吐いた。
「…白石?」
「……伊達に幼馴染みなんかやってへん。お前の、そういうとこも、好きやった…」
そういえば謙也と白石は、家が隣で幼馴染みだったと聞いたか。
「…好きやで。謙也」
「しら…」
「…その言葉、聞くまでは…」
喜びかけた謙也の声は、最後まで彼を呼ばなかった。
え?と呆けた声がここまで聞こえそうだ。
「…好きやった。謙也が。
けど…、もう、嫌いや」
拳を握った白石の声は、いっそ淡々と謙也を突き放した。
「お前、俺に言ったらいかんこと、二回も言うた。
…もう、嫌いや。…それが答え」
すい、と謙也の脇を通り過ぎた白石の手が、強引に謙也に掴まれた。
「なんやねんそれ…どういうことやねん!」
「それはこっちの台詞や!」
白石の強い語調に言い返され、謙也が一瞬怯む。
「謙也だけはって思ってたんに…お前全部裏切っといてふざけんな!
…しばらく、顔なんか見たない」
「…し」
するりと謙也の腕からすり抜けて歩き出した白石の姿が近づいたが、咄嗟に階段に隠れた千歳に白石は気付かなかった。
そのまま通り過ぎていく背中を、ぼんやりと見送ってしまった。
あの時の、ずっと辛そうな白石の顔がリフレインしている。
向けられたあの顔は、俺にではないのに。
白石を部長以上に、仲間以上に見たことはなかった。
男になんて、冗談じゃないから。
けれど。
そんなことを考えていたら、風呂上がりの裸のまま寝てしまって、翌日風邪を引いたのは自業自得なのかなんなのか。
「…大丈夫か?」
見舞いに来た白石が、冷凍庫から出したアイスノンを持ってきて寝台に横たわった千歳の傍にしゃがむ。
「…あんま、大丈夫じゃなか」
「医者行くか?」
「いや、大丈夫」
「どっちやねん。…頭、ちょい上げられるか?」
「ん…」
少し上げた頭の下にタオルにくるまれたアイスノンが置かれて、頭を降ろすと心地いい冷たさが触れた。
前髪あげとけ、と言われて片手であげると、白石が剥がした冷えピタを額に貼ってくれる。
「レトルトやけど、お粥あるから。
少し寝て、下がったら食べて薬飲め」
「…すまん」
「ええて」
小さく笑った白石の気配に、少し安心した。
「薬出しとくし…」
声が不意に途切れる。千歳の熱い手がその包帯に巻かれた手を掴んでいた。
「…ちとせ?」
「……言うたら、いかんことて?」
「………?」
主語を抜きすぎてわからないのだろう。首を傾げた白石の気配に、なにを聞く気かと自分を笑ってそのまま意識を手放した。
眠りは、すぐ訪れた。
するり、と糸引くように意識が戻る。
ずしりと重い身体は、それでも眠るよりは軽い。
大分熱が下がった証拠だろう。
汗まみれで気持ち悪く、シャワーでも浴びるかと起きあがって驚き、苦笑した。
ベッドに寄りかかって、眠っている元部長の姿。
「…伝染るとに…」
帰れと言った記憶がそう言えばない。言うべきだった。
とりあえず、なにかかけた方がいい。このままでは彼の方が風邪をひく。
千歳が起きあがって傍のシーツを白石の肩にかけると、ぴくりと指先が動いた。
「……ん…?」
「起きたと? そげん格好で寝とると伝染るったい」
「……あ」
熱下がったん?と寝起きで多少絡んだような声で問われた。
大分、と答えてベッドから降りた。
「ちょっとシャワーだけ浴びると。白石、ベッド使うて寝てよかよ?
もうこん時間やと朝まで電車なかし」
「…え、けど…お前が出たあと、寝る場所なくなるやん」
「……そうたいね」
自分はそれでもいいが、白石的にはそうもいかないだろう。病人のベッドを奪うなんてこと。付き合いが他より短くてもそのくらいはわかる。
「じゃ、せめて寝直すなら押入から布団出して寝なっせ。白石に逆に風邪引かせたら光たちに怒られったい」
「なんで財前?」
「あいつら『白石部長』フリークやけん」
けらけらと笑って着替えを持つと、風呂場に消えた千歳を苦笑と一緒に見送って、白石は軽く、自分の裸足の爪先を見下ろした。
なんの飾りもない爪も、足も年中走っている所為で普通のそれより大きく太いが。
とうてい、謙也にすら及ばない小さい足に、小さく溜息が零れた。
不意に風呂場から千歳の声がした。
具合が悪くなったのかと慌てて風呂場の扉に近寄った白石に、シャワーに紛れた声が響く。
「すまん! シャンプー、そこになか?」
「…え? あ、これか…」
入ってええ?と許可をもらってから風呂場の戸を開ける。
シャワーのノズルを持った千歳の髪はほぼシャンプーの泡に濡れていたが、どうやら途中でシャンプーがキレたらしい。
仕方なく俯いている千歳の手の届くところに新しいシャンプーを開けて置いた。
「すまん。ありがと」
「いや、ええて。ほな部屋におるから」
「ん……っ……た…」
「…え?」
『た』?と疑問符を浮かべた白石が問う暇もなく。
方向を誤ったノズルはお湯を勢いよく出したまま、白石の方を向いた。
「…っわ!」
千歳が慌ててお湯を出す勢いで床を這うノズルを押さえて止めると、大丈夫かと聞いたが、既に白石の服は全身ずぶぬれだ。
「…すまん」
「いや、ええ。…着替え鞄にあるし。どないしたん」
「いや、シャンプーの泡が左目入って」
「ああ…」
見える方の目に。と納得した白石が見えるか?と心配そうに聞いた。
普通、ずぶぬれにされて怒るだろうに彼はそうしないで心配する。
そういうところが、強いていうならみんな好きで、謙也が男同士でも好きになった理由。
「大丈夫」
「……そか」
また、背後で小さく笑った気配。
ぱたんと閉まる戸の音。
そういえば、白石が小さく笑う時の意味を考えなかった。
そういう時、彼はいつも『大丈夫なフリ』をする時じゃないのかと。
気付いて、すぐ雑に泡を落とすと立ち上がった。
千歳はまだ出て来ないだろうし、大丈夫だと濡れた服を脱ぐ。
下着の下の一枚も降ろすと、出しておいた着替えの一枚を取った。
「白石…」
語尾に疑問符がついていいんじゃないか、という声のトーンにハッとした時には遅い。
そこに立つ下半身に下着だけ身につけた千歳の眼にさらされている自分の全裸に、咄嗟に持っていた一枚で下を隠したが、多分遅かっただろう。
「……白石……?」
「……なんや」
「……気のせい…と…ね?」
「……………」
決まり悪く目を落とした白石は、すぐ隠したまま手近なクッションを掴むと千歳の顔目掛けて放り投げた。
「気のせい言いたくなるほど困ることならまず部屋を出るなり後ろ向くなりしろ!」
そうでした。ごめん。と返して後ろを向く千歳の耳が赤いのは気のせいではない。
失敗した。
(ちゅーか、千歳なんか経験多そうで…今更『女』の裸なんか…照れるもんやないやろに)
そう思ってしまったのは、多分それでも普通のリアクションをされずに済んで、安堵したからかもしれない。
「つまり、…遺伝上は『女性』ってこつ?」
お互いにきちんと着替えてから状況を整理することになって、卓袱台を挟んで向き合う千歳に、ちょっとまだ風邪治ってないんだから寝て聞けばいいのにと思う。
「まあな」
白石はどういうわけか、上半身が男性なのに、下半身は女性という身体らしい。
子供も産めるだろうし生理もある。けど胸はない。
「したら、男として通った方がええやろ。声もこんなやし」
「…まあ、そう、たいね」
一応声変わりもあったらしい。
「…誰もしらんとか」
びっくりしたが引きずっていても仕方ないという思考で生きている千歳はそう言っていたが、白石も同じ思考らしい。うん、と普通に頷いた。
「で、お前は吹聴したりするタイプやないから、問題ない。以上」
「…あっさりしとうね」
「ほな、お前、俺が女やって知って態度変える?
女の子扱いして、今までの俺がやったこと、なしにするか?」
「いやまさか。なんでそげん阿呆なこつ」
やろ?と笑うと思った。白石だから。
どこまでも真っ直ぐで、相応の自信家だから。
けれど、彼、いや彼女は一瞬吃驚したように千歳を見て、軽く俯くとぽつりと零した。
酷く頼りない笑みを浮かべて。
「…よかった」
その響きがいつもの『白石蔵ノ介』とかけ離れていたからなんて理由になるだろうか。
瞬間、跳ねた鼓動に一番びっくりしたのは千歳自身。
(…え)
「…千歳?」
「…あ、いや、なんでんなか」
「…そか」
声も、調子も自分が見て来た『彼』となんら変わりない。
自分が忘れでもして、普通に接せばいいだけだ。
けれど。
「…ちとせ? あ、…」
「え?」
不意に立ち上がった白石がひょいと卓袱台に乗って、千歳の髪に手を伸ばした。
「ちゃんと拭かんと…。また風邪悪化する」
タオルで拭こうとしている手より、なにより眼前に見える服の隙間の白い胸や、短いズボンから覗く足が。
「っ」
「…え」
両肩をいきなり掴まれて、座らされて白石がきょとんとする。
掴んでそうした千歳を見上げる顔も、自分に対する警戒なんかまるでない。
それでも、よく触れれば細く頼りない肩も腕も、小さい足も。
「…いや、よか」
「…?」
意味がわからないとコトリと首を傾げる仕草すら。
(…全部、在る意味拷問たい…!)
普通なら全く気にならないことが、女だと知って意識した途端、全て目にちらついて心臓がどきどきする。
「白石…」
「ん?」
「…そげん、無防備におるといかんよ」
「?」
「…白石を男って思っとう奴らやって白石を好きになるヤツ多かろ?
いつ襲われて知られるかわからんけん、もうちょい男に警戒持ったらんといかんよ。
少なくとも男の一人暮らしのとこに来たらいかん」
「…けど、千歳やし」
「…どげん意味ねそれ」
問う千歳に、白石は逆に問われる意味がわからないと笑った。
「やって、千歳やもん。
千歳がそないなことするはずないやん」
言葉を失った。
それも、多分色々いい意味で。悪い意味でも。
信頼されている。男の中では最上級レベルで。
それは非常に嬉しい。有り難い。
しかし、逆に心苦しい。
もし、俺が彼女を裏切る目で扱ったら、あっさり嫌われるのかと。
「…千歳?」
「…なんでんなか。とりあえず、………なんか食べんと? おなかすいた」
「…ああ。ごめんな。ほなお粥暖めよか」
うん、と頷く以外になにが出来ただろう。
多分、四天宝寺最高の秘密を共有することになった日。
これが幸運なのか不運なのか、千歳にはわからなかった。
→NEXT