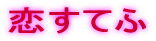
seasonⅠ-僕の優しいお姫様
第二話-【幼い騎士の約束】
「避けられとる…」
下校中、ぽつぽつとそう零す先輩の言葉に、財前はハァとしか返せない。
「好きなのに嫌いってどういうことやねん」
「…ちゅーか、謙也くんが言った“言ったらいかんこと”を思い出した方がええんちゃいます?」
「…思いあたらへんねん」
「幼馴染みでしょ? 家となりなんだから行って聞けば?」
「……考えたけど、あの顔でまた嫌いとか言われたら」
言いかけて、不意に視線を横に向けた。
その謙也の視界の先、反対側の歩道。
並んで帰っているのはその白石と、千歳。
「そういや、最近あの二人よう一緒におるな…」
財前の声が妙に遠い。
ぴたり、と白石が足を止めたので千歳もそれにならった。
「どげんしたと?」
「…あれ」
白石が見遣った先、一軒の女性向け衣服ショップのショーウィンドウに並ぶのは、シンプルだが可愛いセーターとマフラー。それに、胸の空いたワンピース。
「…可愛か思うと?」
「…まあ、ちょおええなぁ…とは」
あれ以降、変化があるとすれば二つ。
自分があからさまに白石を男扱い出来なくなったこと。
そして、白石が自分の前では女の子らしい好みや趣味を隠さなくなったことだ。
普通に女の子として生まれた娘より、白石の好みや趣味はやはり男寄りの嗜好だったが、それでも充分ボーイッシュな女の子という感じで可愛らしく、好ましい。
「白石、見て行くと?」
「いや、ええよ? 似合わへんやん」
それでも、自分が普通じゃないからと、そう言う言葉は逆に痛く。
「…なに話してるか聞こえませんね」
「当たり前やろ」
「ものっそう気になっとる癖に」
財前と謙也の視線の前、話していた二人は傍の個人経営の薬局に入って、すぐ千歳だけ出て来た。彼はその隣のショップに入っていく。
「…別に帰ることになったんかな?」
「あそこ…白石の叔父さんがやっとる薬局って聞いたな」
「ああ…」
やがて、白石が出てきて、周囲を見渡す。千歳を探している様子だった。
「…帰ったんかな」
特別、待っていてくれと約束はしていなかったし。
肩をすくめた白石が足で軽く地面をこすった時、隣のそのショップから千歳が出てきた。
「あー、よかった。もう帰ってしもたかと思ったけん」
千歳は満面の笑みだが、白石は千歳と女性向けショップの取り合わせにびっくりしている。
「千歳…お前どっから出て来るん…」
「いや、そげんこつはよかし」
「よくないやろ。特にそこの店員さん…」
「そげんこつより、白石」
呼ばれて、その首にふわりとなにか暖かい、柔らかいものがかけられた。
首に巻かれたそれはマフラーだ。それも。
「…これ…あそこにあった」
「うん」
自分がいいと言っていたシックな感じの赤いマフラー。
「…なんで?」
「この色味やったら男がしてておかしくなかし。
それに白石がよか言うとったん、ワンピースじゃなくこっちやなかと?」
「……そ、やけど…なんで」
「わかっとよ? 流石に白石の好みくらい。
一番傍におる女の子の好きな感じくらいわからんと男として甲斐なかよ」
女の子、と言われてなにいってると馬鹿と、言いたいのに、顔が熱い。
十五年生きてて、家族以外に女の子扱いされたことなんかない。
男の人にそう扱われて、普通の女の子はどう反応するんだろうか。
「……」
「白石?」
「……あ、……高く、なかったん?」
多分、これは違う。
けど、女の子がこういう時、どう話したらいいかなんて、わからない。
「別にそげん高くなかよ。良心的な値段やったし、それにもうすぐクリスマスやけん。
冬やし寒かろ」
「……あ、うん」
「…ばってん思った通りたい」
「…?」
「似合っとうよ」
微笑まれてそう言われて、顔は赤い自覚があるのに。
どう答えたら、正解かわからない。
「…ごめん」
「…なんで謝っとうや?」
「……普通、“女の子”はこういう時どう答えたらええんか…わからんねん。
仲間として答えたらあかんことくらいわかるけど…。それは、恋人とかやないから、それでええんやろけど…。
…なんて答えたら正解なんかな」
「…白石」
優しい溜息を吐いた千歳が、ぽんと頭を撫でてくれる。その手にはめられている紺色の手袋。
「正解なんてなかし、そげんもんは欲しくなか。
白石が思ったこつ、言うてくれたらよか」
「……」
自分の思ったこと。
「……もう、一回、言うて?」
「ん?」
「…これ、俺に」
「…似合っとうよ?」
「……」
その言葉だけで、胸にじんわりと何かが染みる。
白石は微笑うとそのマフラーに口元を埋めるようにして言った。
「……ありがと。嬉しい」
正直、ありきたりな正解の返事なんか期待してない。
欲しくもない。
けれどそう言って正解だ。
彼女らしい笑みがどこかぎこちなくて、照れている笑みは確かに誰より女の子らしく可愛い。
「…ちとせ?」
ショーウィンドウに額を押しつけて悶えてしまった千歳をいぶかしむ白石の声になんでもなかと答える。
(…犯罪的に可愛かし…。ばってん抱きしめたりしたらいかん…)
どうやらショーウィンドウとにらめっこしたのは思わずぎゅっとかしないための防衛策だったらしい千歳が、振り返って不意にハッと手を伸ばした。
「…え」
「危なか」
強い腕に強引に抱き寄せられて、白石のいた場所を通り過ぎるのは歩道を強引に走っていく自転車だ。
「大丈夫と?」
「…うん。おおきに」
「やっぱり白石、歩道側歩きなっせ。俺が車道側歩く」
「え、ええ! そんな女の子みたいな」
「女の子やろ」
額がくっつく程の近距離で言われて、咄嗟に頷いてしまう。
やはり、男の顔をすると千歳は迫力があって、どうしても負けてしまう。
(……だけん、俺も結構女と付き合うとーに…)
千歳が思うのは、相当に色々な女の表情や仕草も見ていたことだ。
可愛いだけの女も、綺麗な女も見てきた。
けれど、一度知ってしまった白石の表情や仕草の全てが、そのどの女の顔より魅力的に心臓を揺さぶる。
「…心臓持たなか…」
「へ?」
「いや、なんでもなかし」
「……」
「…白石?」
「…ちゅーか、女の子扱いせんて、言うたよな…お前、知った日に」
「…ああ」
「…しとるやん」
「…あれは、…今までの白石をなかったことにせんって否定したからたい。
女の子扱いして否定するこつになる思った」
だけん、と顔を上から見下ろされる。
「俺の出来る範囲で白石らしく振る舞ってくれる分には、なんも損なわれなかし。
それに」
「…それに?」
「…白石、女の子扱いされんの、嫌じゃなかろ?
あからさまは嫌やけん、少しは。
…そげんとこ、ほんに可愛か」
にこりと笑って言われて、白石は顔が異常に赤くなるのを感じた。
「…なんで」
「え」
「…なんでそうやってわかるんやお前…っ」
「わかるったい。白石、…俺が知っとう誰より女の子らしか」
またぽん、と頭を撫でられる。
けれど矢張り嫌ではなくて、されるがままに軽く俯く。
顔はきっと赤いから丁度いい。
「白石。途中喫茶店寄ってから帰らん?」
「ええけど」
「人の来んとこたい。そこ。
…実はパフェとか好きやろ」
「…やから、なんでわかるんお前…?」
「さあ」
そればっかりは千歳にもわからない。
でも、この娘は可愛いのだから、ちゃんと女の子の顔をさせてあげたいと思う。
(…ああ、そうか)
今まで男らしかったのに、最近やけに女の子らしく見えると思っていた。
白石が意識してそう見せているわけじゃない。
(俺が白石を女の子扱いしとうから…俺の前では女の子にちゃんと見えとったとか)
くすぐるようにその柔らかい髪を撫でる。
もう彼女はなにも言わない。
あれからやけに過保護になった千歳が家の傍まで送ってくれる。
遠ざかっていく下駄の音を見送って、白石は自分の家の門に向き直る。
「白石」
いっそ、彼らしくない静かな声のトーンで呼ばれたから、一度理解出来なかった。
「白石」
「……謙也?」
謙也がそこにいた。いておかしくない。隣は彼の家だ。
けれど、少なからず気まずいのは、この間の所為。
「…なに?」
聞いた自分の声も掠れてしまう。
謙也がじっと自分を見る。その瞳は、“あのコト”に気付くまで、それまでは嬉しかった。
「千歳」
「…ああ。送ってくれただけやん?」
「…ちゃうんやないんか?」
「……?」
謙也の言葉の意味がわからず、首を傾げた白石の首に巻かれたマフラーを謙也は睨むように見て、伸ばした手できつく握った。
「…っ…?」
強引な手に、なによりそうされると苦しくて、白石はわけがわからず見つめるしかなく。
「付き合うてんやないんか?」
「は? 俺と千歳が? んなわけないやろ」
「こないもん買ってもろて…恋人みたいやったやないか。
やから俺をフッたんやろ」
「…謙也? 苦しい…」
「千歳が好きやから俺をフッたんやろ! せやのに隠して意味わからんこと言うてフッたんや…。最初に千歳と付き合うてるからて言えばええのに!」
何故だろう。
自分を見る、謙也の瞳が痛い。
―――――――――――――痛い。
ああ、そうだ。
千歳はこんなこと、自分にしない。
絶対、しない。
もう、しない。
俺が、女の子だから。
千歳は、女の子にこんなことしない。
…優しいから。
謙也も、女の子にこんなことしない。
そんなの、幼馴染みの自分が一番知ってる。
「……なんで?」
零された白石の言葉に、謙也が一瞬動きを止めたのは、意味を理解したからじゃない。
白石の声が震えていたからだ。
「…なんで? …なんで俺にこういうことするん?
…他の娘には優しいんに…なんで。
知ってたけど…あの日理由なんかわかったから…知ってたけど。
……千歳の傍が心地ようなったってしゃあないやんか…」
「…なん」
「やって千歳は俺を優しい瞳で見てくれる!」
声を失った謙也の、気持ちなんかわからない。
『白石、女の子扱いされんの、嫌じゃなかろ?』
…そやな。千歳。
あってたわ。それ。
女の子として、扱って欲しかった。
テニス部部長になって、全国にみんなと行けて、みんなに信頼されて。
幸せや。
普通の女の子やったら絶対得られんもん、俺は持ってる。
やから、幸せなんや。
せやけど、俺は最後まで男で生きられる身体やない。
結局、女や。
そして、心も女の部分はちゃんとある。
みんなと男としてテニスするんが楽しいんに、
普通の女の子みたいに、優しくされることが、嬉しい。
他の触ったら壊れそうな女の子らしい女の子みたいに。
扱われることが嬉しいんやって。
千歳といて気付いた。
俺は誰かに、きっとそうされたがってた。
何年も前から、それに気付かないまま、
それでも平気やったのは、謙也がいたから。
謙也が、好きやったから。
謙也が、俺を理解ってくれてるって安心してたから。
『―――――――――――――がもらったるから』
昔の言葉に期待して、馬鹿や。
俺。
『男同士でもかまへん』
謙也はとっくに忘れてたんに。
白石の頬を伝う涙に、一番驚いているのは謙也だ。
意味すら、わからず。
ただ、自分の所為だということだけ、わかって。
「…言うてくれたんに」
白石の唇から零れる、声がやけに高く聞こえる。
『――――――――――俺がもらったるから、蔵は安心してええよ』
「『俺がお嫁にもらったるから安心しててええ』て…言うてくれたくせに…!」
謙也だけは理解っててくれるからって安心して。
謙也が俺が女だってことすら忘れてたことをあの日知らされて勝手に傷ついて馬鹿なのは俺や。
たかが七歳の時の口約束。
…覚えてるわけがない。
「…白石」
「…謙也のアホ! 大っ嫌い!」
外は広くて、冬だから余計広くて、空気は声をよく通して。
なのに、狭い密室で聞いたように、その声は耳に響いた。
自分を突き飛ばして、家に逃げるように姿を消した白石を茫然と見送った。
『謙也くん。蔵ノ介のこと好き?』
白石の親がそう聞いたのは、小学校一年の時だった。
入学式の前の日。お揃いのランドセルを、白石はどこか遠慮がちに見ていた。
「うん! めっちゃ好きや!」
「そうかぁ。あんなぁ…蔵ノ介…、謙也くんと同じ『男の子』として学校入るやんな?」
「…うん」
首を傾げて聞いた自分は、あの時はまだよくわかっていなかった。
白石の身体がどれほど異質かも、同い年の女の子の上半身が男と大差ないあの頃の自分に、あまり深刻に意味は届かなかった。
蔵ノ介のどこが他と違うのかと、思っていた。
「せやけど、ほんまは女の子や。せやけど、そうさせてあげられへん。
蔵が女の子って知っとるんは謙也くんだけやねん」
「……」
んー、と呻った自分は確かにこう言った。
「ほな、俺が蔵を守る! 守ったるから安心してや!」
「ほんまか? 謙也くん、蔵の騎士さまみたいやなぁ」
「…俺、お姫様やないし」
そうやっと言った蔵ノ介の手を握ると、きょとんとした顔がこちらを向いた。
「なに言うてん。蔵はいっちゃん可愛いお姫様や!
安心してええよ! 大きくなったら俺がお嫁にもらったる!」
「……ほんま?」
「うん!」
「……やくそく?」
「うん! 約束!」
はにかんで指を絡めた女の子を、女の子と知っているのは自分だけ。
だから守ると決めた。
色々わからないことの方が多いけど、守るんだと。
好きだから、守るんだと。
「…………―――――――――――――忘れとった……」(汗)
思い出した。
全て思い出した。
いや、どこで白石が女の子だと忘れたかが思い出せないが。
そして、辻褄があった。
それで白石は俺をフッたのだ。
『男同士』と、白石の性別を忘れてますということが丸出しの告白を聞いて。
「……そら、フラれるし…嫌われるし…顔見たないわなぁ……そら」
情けない声が寒空に漏れる。寒さが染みるが、それどころではない。
生憎、白石が男だろうが好きだと思っていたのだ。
女の子だと思い出したのなら、余計足踏みなんかしていられない。
自分の馬鹿で今までの信頼踏み倒した挙げ句、本来なら既に付き合ってただろう関係もパアだが。
今日の二人の様子から見て、千歳は白石が女の子だと知っているし、そうと意識して扱っている。
なら、千歳が白石に惚れるのも時間の問題(既に惚れてる可能性も大)。
白石が千歳を意識するのも時間の問題である。
「わかった!」
寒空の痛い十一月。
謙也の声が民家に響く。
「思い出したからな白石! お前をもらうって約束したんやから、失態を晴らしたら付き合うてくれ!」
すぐあの声が馬鹿言うなとか窓を開けて降ってくる予感もしたが、今日はそれはなかった。
とりあえず、言うことは言ったと謙也は自分の家の門をくぐる。
「…おや、今の謙也くんの声?」
「やねえ?」
一方、白石家の階下。
夕飯のお裾分けに来ていた謙也の母が、白石の母と顔を見合わせて笑う。
「謙也くんったら。今も蔵のこと好きでいてくれるんやなぁ。
私嬉しいわぁ」
「私こそ嬉しい~。
大人んなったら謙也があんな綺麗な蔵ちゃんをお嫁にもらってきてくれるんやもん!
あの人とお式の場所どこがええかもう考えたった方がええかなぁ?」
「あら、なぁなぁ、もう蔵のこともらう気分やで?
コメントはお父さん?」
「蔵は二十歳までは嫁にやらん。…が、孫ははよ見たいな」
「速攻裏切ってんやんお父さん」
声が二階まで響いてくる。
謙也のお母さん、あなたの息子は今さっきまで俺の性別男や思うてた阿呆やで。
と無性に言いたい。
「蔵~。なに拗ねてん。謙也くんが嬉しいこと言うてたやん。
羨ましい」
「…姉ちゃんにはわからへんわ」
扉越しに姉に言うとあからさまに扉を蹴った音。
我が姉はおしとやか系だが、内面は実際、自分より男らしいとこういう時思う。
「蔵。…それは二十五歳にしてまだ彼氏おらん私への喧嘩売り?」
「そういうわけやあらへんから姉ちゃん…」
「ならええけど…。ただ、なに。あの謙也くんの思い出したて」
「……俺、謙也にこの前付き合うてて告白されてん」
「あら、よかったやん」
「『男同士でもかまへん』て台詞が?」
扉の向こうが沈黙した。
「…蔵。まさか、謙也くん、蔵の性別…忘れとったん?」
「思い切り忘れとったし」
「……そら、………ごめん。複雑やんな…それは」
「……ええよ」
それで思い出したか。と扉の向こうの姉の声がやけに響いて、なんとなく姉は腰に手を当てて遠い目でもしているんじゃないかと思い浮かべられた。
(…思い出したんはええけど…やけどはいそうですかて流せることやないやんか)
一体いつから忘れてたんかも、気になるし。
でも、それを抜きにしたら謙也の好きって気持ちは嬉しい。
「……せやけど」
部屋でテンピュールのクッションを抱えて膝を丸めた。
「…千歳は俺をどう思てんねやろ……」
彼への不思議な気持ちが、ただ女の子扱いされたから嬉しいだけで済むようにと、白石はなんとなく思った。
→NEXT