Somebody,oh tell me
Defend me from enirely
Somebody,oh tell me
Baby,shout to me......
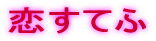
seasonⅢ-First Kiss
第四話-【溶けた端から再び凍り付く】
「謙也くん」
死刑を待つ罪人の気分はこんなだろうか。
翌日の朝、帰宅した白石の姉、櫻に睨まれた謙也はそう思った。
親はまだ帰れず、妹を心配した姉だけが帰ってきて忍足宅に迎えに来た時には、白石は熱に浮かされていて。
妹を医者に連れていってから帰ってきた櫻は、その間の白石の状態からおおよそを察したらしい。見舞いに白石家の扉を叩いた謙也にそう言った。
「蔵になにしたん?」
「…い、いや…」
「なんかあったわなぁ? 知っとるやろうけど、あの子頭ええから東大レベルの問題集前にしたって熱出さへんねん」
「……はい、それは俺も重々」
「なら、キミとなんかあったって思うんが普通やないかな?
最近キミのことで悩んどったし」
「…」
「謙也くんが蔵の性別、男て思ってたんも知ってんよ?」
「…っ!」
なかなか口を割らない謙也に、姉は溜息を吐くと、
「まさか、抱いて無理させ―――――――――――――」
「それは絶対ないっ!!」
速攻真っ赤になって否定した謙也に、櫻は軽く笑う。そんなことくらいはわかる。
言ってみただけで。そんなことになってたら妹は熱出すくらいじゃ済んでないに違いない。
第一、一ヶ月前まで性別を忘れていて、あっさり手を出す男だとは、謙也のことは思っていない。
「そっそそそそんな大それたこと! するわけあらへん!」
「うん。そこは疑ってないわ。そない可哀相な程うろたえんでええし」
「……したった、だけで」
「うん?」
「キス…初めてした…だけです」
「……ああ」
そうか、と納得した姉がぽん、と手を打った。
「今時の子にしては清廉潔白なお付き合いやなぁ。
お姉ちゃんそんくらいが微笑ましくてええわぁ。お父さんは孫はよ見たいとか言うけど。
よく考えたらそうやねー。蔵の肌なんかキスマークえらい付け甲斐あるやろし。
それをキミみたいな年の男の子がつけんと我慢出来る筈ないわな」
「櫻さんっ!」
「まあ、とにかく私は感動した。流石謙也くん。お母さんのお眼鏡にかなっただけはある」
「…あ、じゃあ」
見舞っていいのかと期待した謙也に、にっこり笑って、
「見舞いはアカン。
謙也くん見たら蔵、余計熱あがるから」
ほな謙也くんも風邪ひかんようにな、と手を振って玄関を閉められる。
項垂れて自宅に戻る謙也を、忍足家の窓から侑士が笑って見ていた。
「アっ」
忍足家。自室に戻った矢先に扉がノックされ、弟かと開けた謙也の視界にはにやにや笑う従兄弟。
「ホやな―――――――――――――謙也。
好きな娘のファーストキスとられたからって合意なくお前もキスすることないやろ?」
「……侑士」
つかそこで言うな!と部屋に引き入れ、扉に鍵をかけてから振り返ると従兄弟はさっさとベッドに腰掛けていた。
同じベッドに腰掛けている人間でも、昨日と違ってやたら腹が立つ人間だ。
「てか! なんで俺の好きな女の子が白石て…!
白石が女の子て知ってんねん!」
「お前アホやアホ。ドアホ」
「じゃかあしゃあ!」
「俺は寝言は言うけどいびきはかかんて知っとるやろが」
「それが……!
……昨日?」
「うん」
確かに昨日、階下で従兄弟は寝ていて、その部屋で母親が白石を女の子だというような発言をしていたが。
従兄弟はいびきをかいていたから寝ていると自分も思っていたが。
そういえば、確かに何度も同じ部屋で寝たが、この従兄弟のいびきがうるさくて眠れなかったなんてことは一度も。
「は」
「ん?」
「謀ったな侑士!」
「謀られるお前がアホなんや」
「や、やってなんか芋蔓式にここ一ヶ月で白石のことバレてってへんか」
「その辺は心配無用な」
侑士はそう言うと、ベッドにあぐらをかいた。
「俺は元から知っとったで?
白石が女の子やて。
四天宝寺に入った聞いた時、『マジで男として入ったんか』て思ったわ」
「え?」
「考えてみいや。俺、年中お前ん家泊まっとったし。
小学校低学年まではこっち住んどったし白石ともようお前と一緒に会ってたし。
お前から白石の話なんか腐る程聞いたし。
当時のお前なんか特に『白石は他と比べて変』て意識皆無やったから俺に年中『嫁にもらう』だの言うとったやんか」
「…マジか」
「覚えてへんねんな…謙也」
は、と笑った従兄弟を睨む気力が、今日ばかりは皆無だ。
ということは、筒抜けだったのか。
自分の名前を隠した好きな子トークも、相談も。
「……俺が白石を男て思てお前にどないしたらええて相談した時お前電話の向こうで笑てたな―――――――――――――!?」
「いやー爆笑を堪えるん大変やったでー?
そんでも顔にやけてしゃあないから丁度泊まり来てた岳人にえらい気味悪がられたわ責任とれや」
「知るか!」
真っ赤になって怒鳴りつけると、従兄弟から離れて机の椅子にどかりと座る。
「にしてもとうとうキスしたったかー。
『謙ちゃんも立派になったなー』て弥勒さんが褒めてくれるんやない?」
「あの人の話すな!」
「俺もはよ彼女作ろ。せやないと弥勒さんに『侑ちゃんが色恋で謙ちゃんに負けるなんてな』て言われる」
「やから弥勒兄シリーズで俺を馬鹿にするんやめえ!」
「で、謙也」
なんや、と怒って答えた謙也に、怒るんやったらなんで全部律儀に返事するんやろと思う。
「彼女に嫌がられたか?」
今までと違う真面目な声だ。
少し考えて、謙也はぽつりと答える。
「抵抗は、…されんかった」
「あ―――――――――――――! また来いやなんて!」
仕事先からかかってきた電話に、苛立ちながら仕方なく準備をする姉をベッドに横になったまま白石が見上げる。
「姉ちゃん。俺、大丈夫やし。行って来て」
「……せやからってこんな状態の妹、家に一人にするやなんて……。
……蔵、……」
櫻は息を一つ大きく吐くと、ベッド脇にかがみ込んだ。
「自分が普通やないから、私らに迷惑かけてるとかて、あんまり物わかりよくならんでええねんで?
こんなええ子授かって、お母さんもお父さんも嬉しい言うてたやない」
「……知っとるし、疑ってるわけちゃうし」
「…なら、ええけど。
ほんの数時間で帰ってくるから。
辛くなったらすぐ電話するんやで? なにがあっても帰ってくるから」
「うん……」
すまなそうにした姉が、それでも部屋から出て行ってまもなく、車の発進する音が遠く聞こえた。
「あれ、ワイらだけ!?」
金太郎が自分の家に泊まったため、一緒に来たストリートテニス場。
誘った小石川しかいないことに、金太郎は驚いた様子だった。
「小石川、俺らだけと?」
「いや、白石も誘ったんやけど」
そういえば来んな、と呟いた小石川に千歳は背筋が寒くなった気がした。
「あ、千歳!」
すぐ踵を返した千歳に、金太郎が声をかけた。
「約束!」
止めず、それだけ笑って言う後輩に、指を立てる。
「うん」
『泣かせたらあかんよ』
すぐ振り返らず消えていった千歳を引き留めることもなく、小石川は打つか?と金太郎に笑った。
家族がいる。謙也だって、隣の家にいる。
そう思っても、嫌な気分が千歳を急かした。
白石家の扉の前、チャイムを鳴らすが返事はない。
意を決して扉を引っ張ると、簡単に開いた。
そのまま家の中に入る長身を、丁度忍足家の階下に降りる途中の侑士が踊り場の窓から見たが、俺には関係ないわな、と階段を下っていった。
「白石……?」
おそるおそる入った家の中は人気がなく、そういえば靴もなかった。
余計焦って、くぐった白石の部屋の扉。
そこだけ点いた部屋の明かりの下、ベッドで眠る姿がある。
「白石…?」
呼びかけるが返事がない。
そっとしゃがんで顔に触れると、驚く程熱かった。
「……熱。…風邪引いたとか…」
家族誰もおらなかと、と呟いた声に意識が引っ張られたらしく、閉じていた瞼が開いた。
「……ちとせ?」
「…あ、すまん。勝手にあがったばい」
「……なんでおるん?」
「や…小石川が白石が来んて言うけん、なんぞあったかと」
「………あ、……返事…してへんかった」
「熱、何度あっと?」
「…今はわからん」
体温計を探すと枕元にあった。
「ちょっとよか?」
耳ですぐ計れるヤツだったので少し安心した。
自分の部屋にある脇に差し込むのでは、時間がかかるし女の子にするには困る。
いくら上半身は自分と大差なくても。
「……39.7…」
なんか恐ろしい数字が出とる、と絶句した千歳に白石が熱に浮かされながら。
「…ちとせ」
「…ん?」
「喉…渇いた」
「あ、ああ。すぐ下のなんか持ってくったい!」
下から丁度あった(おそらく家族が買ってきていたのだろう)スポーツドリンクを数本持ってくる。
冷えて丁度いいそれを、千歳の手を借りて起きあがった白石が口に含んだ。
「すぐ一気に飲んだらいかんよ。少しずつ」
「…ん」
「ばってん、どげんしたと? …あの時、もうこげん熱出す程具合悪かったと?」
白石がペットボトルから口を離したのを見計らって聞くと、違うと掠れた声。
「…なら」
「……なんでもない」
「なんでもなくなか。健康オタクの白石が、そこまで酷くなる程悪化させるわけなかよ」
「……ない」
あくまでなにもないと言う白石を強く呼んで、から不意に声を低くした。
「まさか、…なんかあったと?」
謙也と、と言う声は届いたのか白石が熱で赤い顔で、それでも瞳は揺らいで。
「…白石」
促すように呼んだ千歳に、白石は首を左右に振った。
「言うと…」
「言うと?」
「…千歳が怒るから………」
部屋に響いた声。それきり、落ちてしまった沈黙に千歳も黙る。
「…服、着替えた方がよか」
やっとそう言って、部屋を一度出た。
千歳が呆れて出たのか、しかたなく出たのかはわからない。
ただ、熱でぼんやりとしか働かない頭でも、そんな些細な沈黙の意味すら探した。
上着を着替えて、ふと床に転がったままだったアルバムを拾う。
そこにいるのは、昔の自分たち。
謙也と、あの従兄弟と、自分と。
戻りたい、なんて願ってはいけない。
「着替えたと?」
部屋から出たついでにどうやらゼリーを持ってきてくれたらしい千歳が、中を見てごとっとゼリーとスプーンを落とした。
「白石…! なんて格好でおっとや……!?」
「……?」
「? じゃなか!」
とりあえず千歳が真っ赤になって怒っているのはわかるが、なにが彼をそうしているかがわからない。むしろ、頭が重くて寝たい。
千歳はといえば、白石が上半身に着たシャツ一枚でいて、下着を履いていようが白い足がきわどく見えている姿に真っ赤になるなというのが無理。
(こん女は……俺ん理性、試しとるとかナメとるとか……!?)
千歳が葛藤する間にも起きているのが辛いのかぽすりと座ったベッドにそのまま横になる白石に、千歳が慌てて近寄った。
「そげん格好で寝たらいかん! とりあえず着なっせ!」
「…頭、…おもい」
「…え?」
「…………」
ぼや、とした視界の白石の様子に流石におかしいと千歳が体温計をもう一度耳に当てる。
「……41.8」
既に可愛い風邪レベルの熱ではない。
「家族…っ…」
「アカン…」
「え?」
「呼んだら…アカン。姉ちゃん、さっき仕事戻ったばっかり」
「お姉さんおったとか!?
それなんに行かせたとか?」
「やって、仕事…」
「仕事て…!
妹の体調と仕事の都合とどっちが…」
「姉ちゃん…悪くない…俺が戻ってて言うた…」
「っだけん、なんでん自分の辛いより他人の辛いを優先すっとや!
今すぐ呼ぶけん、番号…!」
言いかけて、枕にうつぶせている顔が震えていることに気付く。
「白石?」
「……」
そっと頭の向きを動かすと、その赤い顔は濡れていて、瞳から流れて頬を汚すのは涙だ。
「……やって…俺の所為…でみんな大変やもん……。
俺が変な身体やから……やから一個でも多く迷惑かけたらアカンねん…。
少しでもええ子でおらな…っ」
そのまま泣き出した少女に、千歳は自分まで顔を赤くしつつ、その髪を宥めるように撫でる。
「……俺も大概アホばい」
(…熱が40度越えてたら誰だってぐずるに決まっとうよ…)
その人間になに話しとったとか、と己の迂闊さを呪う頭上から声が降った。
「あ、千歳…くん?」
びくう!と反応した千歳が振り返った先には、あの白石の姉。
「櫻さ…ん」
「蔵診ててくれたんやね~ありがとう。
……で、蔵はなにに反応してぐずりだしたん?」
「は?」
「この子、熱が39度越えてないうちは普通なんやけど、熱が39度越えると怒鳴り声や大声聞いただけでぐずるんよ。テレビの声に反応してぐずった時もあったし。
……どないしたん?」
俺が泣かせました。
言葉なく頭を下げる千歳を訝りながら、櫻はてきぱきと白石を面倒見た。
気付けばすっかり暗くなった空。ようやく眠った白石を見ていると、不意に言われた。
「千歳くんて…、そういえば蔵が言っとった子?」
「…?」
「蔵が今好きな男の子の片方」
「……、……多分」
危うく呼吸が喉に逆輸入されそうになって痛んだ喉を押さえながら、千歳は辛うじて答えた。
「蔵がそうなったん聞いた?」
「……ああ」
少なくとも、俺が聞いたら怒るようなことだとは。
と心で呟く。
「そっか。せやけど蔵も複雑やんな。
昔なら謙也くんにキスされたなんて普通に喜んだやろに」
「…は?」
「え?」
どうやら櫻は先ほどの「ああ」で知っていると考えたらしいが、千歳はそんなの初耳である。
謙也が、キス?
財前じゃなく?
「……キス、されたんやて。謙也くんに昨日」
速攻誓い破っとうし…………!
誓ったその日じゃなかね!と脳裏で怒鳴りつつ、残された室内。
コンビニで飲み物だけすぐ買ってくるという櫻も、在る意味度胸がある。
自分を行かせればいいだろうに。風邪を引いた妹の部屋に、その妹を好きな男をおいて行くあたり。
「……白石は……嫌やったとか?」
熱に浮かされた彼女から返事など返らないだろう。
けれど、その唇が不意にうわごとを発した。
「……ごめ」
「…え?」
「ごめ……謙也……………ち…」
とせ。
それで、もうどうでもよく、なりはしないが、肩の力が抜けた。
それより、彼女が自分を責めている方が重要。
なにしろ、自分も謙也も、惚れきっているから。
「……馬鹿な子…」
悪夢を夢の中まで持って行かなくていいのに。
本当に、気の済むまで自分を責める人間なんだから。
「…怒ってなかよ。…白石」
そう、囁いて、その薄く開いた唇にそっと一瞬押し当てた。
知らなくていい。
自分の堪えきれない嫉妬からの、自己満足だから。
独占欲だから、ノーカウントでいい。
でも、いつか。
→NEXT