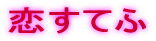
seasonⅣ-高校カウントダウン
第二話-【戦線離脱阻止宣言】
ぼんやりと部屋で考えても仕方なく、階下に降りた白石は甘い匂いにキッチンに向かった。
「…咲蘭? なにしとるん?」
「お姉ちゃん!」
小学二年の妹の手にはボールに溶かしたチョコレート。
「バレンタインチョコ作っとんやて。明日やから」
「…ああ」
すっかり忘れていた。
「蔵も作ったら? 謙也くんと千歳くんに?」
「え!?」
「ええんやない?」
妹に聞こえないよう小声で囁いた姉が笑う。
「好きな人が二人おったって今は。それでも今ちゃんと好きなんです、てアピールする日やない。ええと思うけど」
「………」
バレンタインなんて、意味のわからない日だった。
ただ、疲れる日。女の子の考えることなんてわからない。
でも、自分も女の子だ。
「……」
唐突に白石に呼ばれて行った公園。
白石一人しかいない冬空に、財前は「遠山恐るべし」と思った。
「なんの用ですか?」
「や…卒業するまで聞いてくれる言ったから」
「はぁ。聞きますけど。
なんでしょ?」
これ、と小さい箱を渡される。
「試作品?」
「試作…? 青学の乾さんの野菜汁みたいな言い方スね……」
寒さにかじかんだ手で箱を開けると、多少不格好に固まった固形が四つ並んでいる。
「……チョコ?」
「うん」
「…もしかして、明日バレンタインやから白石さんも千歳先輩と謙也くんにあげたくて、せやけど初めて作るから…みたいな毒味係?」
「大体そう」
「……まあ、ええですけど」
確実にもらえないだろうから、自分は。これも一日早いバレンタインチョコと思えば嬉しい。
一個をつまんで口に放り込む。
「……まずい?」
不安そうに聞く顔は、どっからどうみても女の子で。
「…や、美味いです。ほんまに初めて作ったんですか?
普通の女子が作るんより美味いし…。流石ちゅーかなんちゅーか」
基本、何事も器用にこなす白石らしい。
「ほんま?」
「ほんまです。俺、まずいもんは好きな相手にもまずい言いますよ」
「…よかった」
「形はこんなもんでええんちゃいます? ちゃんと丸いし。
あんまり凝ると味がミスりますよ」
「…そないもん?」
「義姉さんが兄貴に作るん。形凝りすぎてまともだった味が破綻したことあります」
「……そうなんや」
二つ目を口に運びながら、こんなもんはもらった時の気持ちでしょ、と言う。
「好きな女からもらえた、て事実に勝るもんなんかないですよ。
男には。味なんて二の次や」
「……ありがと」
零された笑顔が、誰のためでもやられた。
ああ、もう可愛いんだから本当に。
この人は。
「ええ加減、諦めや」
昼休み。一組にやってきた謙也に、千歳はうんざりするでなく椅子を譲った。
遠慮なく座った謙也はここ最近よく自分のところに来る。
「…諦めてなかよ」
「やから」
「…謙也が来るんは、諦めとう」
言うと、謙也は困ったように余所を向いた。
謙也はしきりに、帰るのは許さないと説得に来る。
それは諦めていて、出来るならすぐ、うんと頷きたい。
諦められないのは、大坂にい続けること。
諦められるはずない。
『千歳』
白石のことを。彼女のことを。
初めて惚れた女を、こんな容易く諦める気持ちで愛していない。
容易く手放せるなら、あの時キスなんかしなかった。
ノーカウントでいいと思いながら、それでもキスしたい気持ちを堪えられない様にはならなかった。
これほど、なりふり構わない程、愛したりしなかった。
「……親父さんに、もう一回言うたらどうなん?」
「…親父に?」
「一度は送り出してくれたんやし。…頭ごなしに言ったんも理由あるんちゃうか」
「………」
「はっきりせえや」
「…謙也は、…なんでそげん必死なんとや?」
「…当たり前やろ」
そんなこともわからないのか、と怒る瞳。
「お前はライバルなんや。
お前がおらんくなってそれで選ばれたって嬉しない。
…お前はライバル以前に大事な仲間や。
…正々堂々勝負させえ!」
謙也の大声に周囲の生徒がびっくりして見遣った瞬間、失礼しますとやけに通る低い声が響く。
「…光?」
「謙也くん。おらん間に机えらいことになってましたけど」
「ええわそんなん」
「まあそれはともかく」
財前は肩をすくめると、ええんですか?と笑う。
「俺、昨日白石さんに手作りチョコもらったんですよ。美味かったです」
「「は!?」」
二人揃って振り返った視界で、後輩はにこりと目を綻ばせる。
「もちろん、本命やなく。
多分、謙也くんか千歳先輩どっちかへの本命の、試作品て言うてました」
「……俺と、千歳のどっちか」
「当たり前ですやん。二人に本命チョコて。
…もろうてから諦めたってええんやないんですか千歳先輩。
謙也くんがもろたら諦める。自分がもろたら、…こっち残る」
「…………」
自分が。
自分に、くれたら。
「………」
頷くように微笑んだ千歳に、財前はどこか満足そうに微笑した。
諦められないから、好きになった。
触れたくて、腕の中に閉じこめたくて堪らない程、愛しくて。
一つの街をまたぐことすら、堪えられない好きはずっとあった。
なら、選ぶ方なんて決まってた。本当は、決まっていた。
少し、なら自分を選んでくれないかと急かしたくて口が滑っただけなんだろう。
ずるく、利用しようとした。
「あ、千歳。謙也…」
放課後の一組の教室。
千歳のところにいた謙也を見て、予想通りと近寄る白石の手には大きな紙袋。
対外には男なので、これも予想通り。
「おー、…相変わらずすごいな、白石」
「…うん。めっさ気分微妙」
とりあえず置け、と促されて床に紙袋を置くと、白石は二人は?と笑った。
「もらってなか」
「え?」
「断ったけんね」
「…それ」
千歳に不安げに視線をよこした白石に、違うと手を振る。
「本命がおるからて、断った」
「……」
「俺も同じく」
謙也の声に、困ったように、嬉しそうに笑う顔を誰より、可愛いと思う。
「白石」
「ん?」
そのさりげない声すら、欲しい。
自分だけに向けて欲しいと絶え間なく願う気持ちは今もあって、
諦められる筈、ないんだ。
「…俺、大坂残ったい」
「…え」
「親父はなんとか説得すっと。やっぱり、こっちでみんなでおれんのは嫌たい」
「……そう、なん」
「それに、惚れた女置いていけるわけはなかね」
少し拍子抜けしたような、なにか言い足そうな声に微笑んで付け足す。
すぐ赤くなった顔が、アホと呟いて俯いた。
「はいストップ!」
「…なんね謙也」
「俺がいる限りは二人の世界禁止」
「心、狭かね」
「当たり前やろ!」
白石の頬に伸ばしかけた手を引っ込めると、白石が顔を赤くしたままくす、と笑う。
「ほな、俺も怒られるかも」
「え?」
白石の言葉に謙也がどういう意味だというニュアンスをかける。
白石は答えず、鞄から二つの箱を取り出した。
ことん、と千歳の腰掛けていた椅子の前の机に置く。
「……千歳…、と謙也に」
「……お前から?」
「うん。…まだ、選べんくて悪いけど」
そこで財前に謀られたと気付く。あいつはきっと最初から二人にあげることを聞いていたのだろう。
「…手作り?」
「なんでわかるん?」
「……いや、やったらええなー…て願望?」
「……、味は、大丈夫や思うけど。…ちょお、形不格好」
「そげんもんどうでもよか」
箱を手に取った千歳が、開けると一つだけつまんで口に含む。
「…白石がくれた、…てことだけで嬉しかし」
「千歳。そこは味もコメントせなあかんやろ」
なんのために一つ喰ったん、と謙也に言われる。
いや、美味いから余計嬉しくて、今の台詞だったのだ、と思うと苦笑が漏れた。
「たいが美味かよ」
「……」
白石が言葉に出さす、安堵の息をもらした。
謙也も一個食べて、美味い証拠のように顔が緩んだ。
「…あ、のな」
「…ん? なんね白石」
「…こんなんやから、…長いこと宙ぶらりんで困らせるやろけど。
…でも、…今、ほんまに大好きやから。謙也も千歳も…」
顔が赤い自覚もある。指を握り込むと、精一杯二人を見た。
「…やから……高校でも…よろしく………………な?」
そう届いた瞬間、謙也が千歳に目配せするまでもなく同じことを考えたように千歳もこっちを見て、立ち上がると意味のわからない白石の身体を二人して抱きしめた。
「…え、え、え……っ」
「そんなん当たり前や」
「そうたい。当たり前たい」
「……あ」
「白石、好きとよ(やで)!」
両方の耳元で囁かれて、真っ赤になった彼女がその場に座り込んだ。
やっぱり、諦められない。
本当に、本当に愛しているから。
「…白石?」
「…アホっ。…腰抜けた」
「え!?」
「俺が負ぶってくたいっ」
「それが狙いか!?」
日の短い冬の教室のほんの一時間を、多分絶対、忘れない。
2/14
特別な、その日を。
後日、父親に電話したらあっさり許しが出た。
父親曰く、カマかけただけ。電話の不許可だけで諦めるようならそっちでまた三年も暮らしていけないからな、だそうだ。
→NEXT