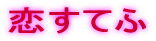
seasonⅤ-NEW SCHOOL DAY
第二話-【もっとがんばりましょう】
「あ、おはよ千歳」
まだ新入生は部活も始まってない朝。登校した白石が自分の机に鞄を置きながら“隣”の千歳に笑った。
「おはよ」
出席番号順の席。
となれば、二列目の四番目の九番と、三列目の四番目の十四番は隣である。
出席番号一番の謙也は当然一番目で遠い。千歳は密かに感謝した。
「最近なんか機嫌ええ? いや、まだ三日くらいやけど」
「あー、そら」
「今日仮入部の日やんな! 一緒に行こうや!」
ばん、と千歳を割って机に手を付いたのは先ほどまで教室にいなかったはずのクラスメイト。
「…謙也」
「ど、どないしたん息切らせて」
低い声で呼んだ千歳とは逆に、白石は単純に驚いた様子だ。
「いやいやなんも。
で、仮入部。テニス部やんな?」
「当たり前」
「そらな」
「……、…白石、気をつけや?」
「…なんで俺?」
「……新入部員歓迎という名のあの人の悪戯を、忘れてへんよな?」
「……あ」
千歳もだいたい、“あの人”が誰かわかる。
ここの『天災』として本当に有名な、あの謙也の従兄弟だ。
おかげで教師に謙也はチェックされている様子。
「あの弥勒の従兄弟か」という具合に。
仮入部を済ませた翌日、昨日は意外になにもなかったなと話ながら手をかけたのは教室のロッカーだ。
次の時間は八組と合同の体育。八組には小石川がいる。
「っぎゃああああああああああああああ!」
響いた悲鳴に、謙也と白石は開けようとしていたロッカーを条件反射で閉じた。
「…? どげんしたと」
千歳も驚きながら手を止める。
「……今の」
「健二郎の悲鳴、やな…」
「………」
「っ…あ! 免れてた! お前らそのままロッカー開けんな!」
悲鳴をあげた後にしては立ち直りの早い小石川が猛スピードで七組に駆け込んできて、まだ開いていない扉付きのロッカーにそう言った。
「…なんや? なにが入っとった?」
「…十中八九弥勒さんの仕業やけどな。…テニス部に仮入部したヤツのロッカーにだけ、冬眠明けのカエルがようさん…」
「うっわ! あの人はまたとんでもないことを…」
「白石、絶対開けたらいかんよ?」
「うん…」
「とりあえず、大丈夫なヤツが開けて体操着出そうか…」
「俺は大丈夫やけど」
「「大却下!」」
「……うん」
千歳と謙也に揃って叫ばれて、白石はごめん、と下がる。
「…お前ら、どうしたん?」
白石は実際平気やろ?と不思議そうな小石川がいる。
平気だろうが、女の子にそんな思いはさせたくない。
知らないからとはいえ、弥勒に殺意を覚えそうだ。
「ちゅーか、心底意外や…」
その後の体育。二人一組で柔軟を行う際、千歳はやむなく小石川とペアになった。
謙也は言うまでもない。
身長差が違いすぎるのだ。また、自分は伸びたらしいし。
背中に乗せた小石川がぐらぐら変わる視界の中でぽつりと言った。
「なにが?」
「お前らが白石を大事に扱ってんのが。
多分好きなんやろーな、てのはわかっとったけど」
「………」
一瞬ぎくりとした。女の子、というのはバレていないようだが。
「ま、今は学年一番下で、先輩からの扱いが怖いこともあるから注意したれ?
あいつ、男にもモテよるし」
「…知っとおよ」
「やろな」
「おい、千歳」
「ん?」
気付けばそこに一人きりの謙也。
「どげんしたと」
小石川を降ろしてから言うと、ちょっと顔貸せと真剣に言われた。
白石が目薬を取りに戻って、帰って来ないという。
俺もついていくと行ったが、すぐ教師に呼ばれて行けなかった、と。
「先生の許可は」
「白石くんが戻って来ないので見に行きます、て取った」
「ああ」
一緒に成り行きでついてきた小石川が、ふと一階に下りる階段の横の窓から下を見て、あれ?と零す。
体育館はこの学校は二階にあるのだ。
「…あれ、白石やないか?」
「え!?」
ばっと見遣った階下の庭。
そこに立つのは、見にくいが困った顔で戻ろうとする白石と、なにか喚く男の先輩。
「告白…から断ってのもつれ?」
「冷静に言ってんな」
「そやな。急いであそこまで…」
言いかけて小石川がはた、と目を二人に向ける。
乱暴に白石の手を掴んだ先輩に、これ以上時間はかけられないと判断したのは一緒で、窓をがらっと開けると背後の小石川の『ここ二階っ』という声も聞かず、ひょい、と下に飛び降りた。
「やから―――――――――――――…っうわぁ!」
「…………、とせ…や…?」
いきなり空から降ってきた千歳と謙也に、先輩がびっくりして手を離したならそれを間近で見た白石もびっくりである。二人の名前を中途半端にしか呼べていない。
「…その手、離せやセンパイ」
「以下同文」
チンピラすら殺せそうな目つきで睨む謙也と千歳に、びびった先輩がすいませんでした!と叫んで遥か彼方に走っていった。
「……、お…お前ら危ないやろ! どっから来るんや!」
「…お前が危ない」
「は…」
「俺達に危なかこつさせたくなかなら、…白石は俺達の見えんとこ行ったらいかん。
わかった?」
二人にひどく真剣に言われると、やっぱり負けてしまう。
やっぱり、卑怯だ。
「…男ってだけで卑怯やお前ら」
「?」
「…負けるし……。わかったから」
「…よし」
ぽんと千歳に撫でられた頭に首をすくめる。
それを二階の窓から、青春だな、と小石川が見ていた。
「じゃ、一年は脇で素振りな! 二年は-」
仮入部期間も末の四月中旬。春に似合わない大雨で校舎内の練習の部活が多い。テニス部もそうだ。
てきぱき仕切る弥勒を、部活中は真面目なんや無駄に、と謙也がコメントする。
「そら、部活中まで台風やったら流石に辞めさせられてるわ」
「それもそうたい」
「私語はええけど余所見すんなよ」
「はい」
ちゃっかり注意していく弥勒を、他の一年が「まともなとこあるんや」という視線で見ている。
二年、三年は廊下の向こうでステップなどの練習を個別でやっている。レギュラーは視聴覚室で試合の反省。
一年といったって既に大きい生徒たちは階段下の廊下で素振りだが、正式に部員になった後はコート使う頻度が思い切りあがるから、と先輩が言った。
学年差別は中学といい少ない。
「あ、千歳。お前気をつけろや? 振り回しすぎて天井の蛍光灯割ったりす――――」
んな、と言いかけたその白石のラケットが頭上の蛍光灯を見事に割ったので、千歳と謙也、ついでに小石川があからさまに引きつり青ざめた。
「白石!」
「ちょ、動いたらいかん! 服ん中入ったかもしれんばい!」
「じっとしとけ。出してやるから! 足動かすな破片踏む!」
小石川のは単純に元副部長で元部長の白石が心配なだけだが、周囲から見れば三人とも一緒に慌てているようにしか見えない。
「先輩! 白石が蛍光灯割ったみたいです」
「ちりとりと箒持って来い。あと救急箱。怪我は見た感じないな」
てきぱきと指示する有楽の横から弥勒が、これ、と箒とちりとりを持ってくる。
「早いなナイス」
「傍に教室あったしな」
直立不動にさせられて(少し動けば怒られるから)服を叩かれて破片がもうないと安心した千歳たちにもういい、と大丈夫と動く許可をもらって、白石がはーっと息を吐いた。
「すまん…」
「いや、ええけど…」
「怪我ないみたいでよかったわ…。あ、怪我ないです!」
「すいませんでした!」
「いやええって」
大事なくてよかった、という先輩の声に、安堵の後顔を見合わせた千歳と謙也の胸中は多分一緒。
「……」
声は何も出ないが。
(…白石の裸(上半身だけとはいえ)が他の奴らに見られた……)
上半身は男だから見たってバレないが。
すごく嫌だ。かといって騒げない。
これからまた三年間、こんな生殺しな生活か。とちょっと気が遠くなった。
「千歳?」
休憩時間。階段でぼんやりと雨の降る空を見ていた千歳を背後からテノールが呼んだ。
「ん?」
「ん?やない。おらんから」
「ああ。…謙也は?」
「さあ? 小春たちに遊ばれてんやない?」
そか、と呟く。嬉しい誤算だが。
とん、と隣に座った白石も自分も、まだ高校のテニス部ジャージはなくて四天宝寺のジャージだ。
「……雨、」
「ああ。…思い出したん?」
「…思い出して自己嫌悪」
言うと傍で白石がくすくす笑った。
こんな雨の日の、四月のことだった。
去年の四月。
気付けば二人きりの部室で、床に倒れている白石を床に押しつけていた。
欲情したとかじゃない。
最初は、一人きりだった部室で不安にロッカーを蹴った自分を注意した、いつの間にかいた白石を、掴むつもりがそのまま押し倒していた。
電話をもらった直後だった。
九州からの友人で、橘がテニスを始めたという電話。
胸に押し寄せたのは安堵だったから、大丈夫だと思ったのに開いた窓から入った風に巻き上がった埃が左目に入った。
それだけで見えなくなる視界。
安堵と同時に、浮かんだのは「お前だけ」という嫉妬。
お前だけ結局なにも失わないで。
そんな黒い感情。
見えなくなった視界は、安堵で消そうとした気持ちを大きくした。
それでつい当たったところを見られて。
弾みとはいえ押し倒したことを、撤回するまともな精神じゃなかった。
歪んだ虚勢が手伝って、千歳が触れた指先にぴく、と震えた白石の手を押さえつけて、そのまま右手の中指の爪を引っ張るようにはがした。
掠れた声が一瞬あがって、すぐ荒い呼吸だけで押さえ込まれる。
やけに高揚した視界に映る白石は痛みを堪えながらも、静かに見上げてくるから。
それで、気持ちはあっさり醒めてしまった。
馬鹿やってるんだ、と零したら白石にそやな、と笑われた。
無性におかしくて笑って、零れた涙を拭う白石の指を緩く掴んだ記憶。
雨の音が、やけに遠かった。
「女の子に…あげんこつはなかろよ」
「…っ…」
「おかしかや?」
「…反省しとるんならええんやけど別に」
「…今は桔平はよか友だちに戻っとう。
ばってん、あの時なにか違っとったら憎んだままやった。
…ごめん。…だけん、…ありがと」
あの時、いてくれてありがとう。
「…お礼はいらへんよ?」
「…」
白石の小さな声に、促されるように笑った。
「もっと頑張らんといけんね」
「…?」
「なんでんなか」
一瞬、謙也が聞いてたら、と危惧したがそれはなかった。
立ち上がった視界には相変わらず二人きりの世界。
「行こ」
「…うん」
四月の雨が降る。
小さな小さな、明かりのように。
→NEXT