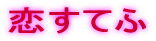
seasonⅠ-僕の優しいお姫様
第三話-【Nice to meet you,I will beat you】
謙也の絶叫告白の翌日、白石は家を出て声を失った。
その門の前に立つのは、その幼馴染み。
「…………」
なにを言えというのか。なにも言いたくない。第一。
無言で通ろうと門をくぐるが、門を背中に前に立たれて、余計苛立った。
「…退いて」
「ほな、一緒に行こうや」
「嫌。通して」
「一緒に行こ。蔵」
「…、…」
昔の名で呼ばれた途端、馬鹿みたいに心臓が跳ねて、それで同時に拒むのも馬鹿らしくなった。
「…わかったから。通して」
「うん」
満面の笑顔で退いて、隣を歩き出す謙也の顔に小さく溜息を吐く。
この幼馴染みは思えば昔からそうだ。
こっちが真剣に悩むことを、あっさり片付けて。
それで悩んでないわけでもない。本人は必死に考えているし、悩んでもいる。
ただ、それを周囲に見せられないのだ。謙也はそういうヤツだ。
毎日明るい顔をしていた癖、体重がたった一週間で五キロも落ちた時は彼が初レギュラーになった時。
あれは仲のいい先輩をけ落とす形だったし、その先輩がその後すぐ退部したから本人は相当な心労だったのだろう。それを全く見せない、見えない程明るく笑うから自分すら騙されて。
そうしたら実際、五キロもやつれるほど本気で悩んで、それでも諦められない気持ちで前を見ていた。そういう、馬鹿なヤツ。
必死に一緒に行くことを拒んで、またやつれられたら堪らない。
「白石、ごめんな。忘れとって」
「……思い出したんやろ? もうええ」
「よくないやろ」
きっぱり言われて、思わず彼の横顔を見た。
「女に…それもいっちゃん大事な女の子にあんな酷いことしたんや。俺。
よくない」
昨日の、強引に白石を扱ったことを言っていると気付く。
「そら、白石は千歳とおるんが心地ようて当たり前やわ。
あいつ、女に優しいやろし」
「…謙也かて、優しいやん」
「せやけど、お前に優しいしてやれんかった」
「…………」
「忘れとっても、思い出すきっかけなんかようさんあったんに…。
挙げ句、部長やからって女の子一人で暗い中帰して…。
ごめん」
「…も、ええ」
ものすごくむずむずしていたたまれなく、そう言った。
「おかんが気ぃ早い話すんやで?
お前のドレス、謙也は何色がええとか。俺らまだ中学やっちゅーの。
つか俺フラれてんに」
「…昨日、俺ん家でも言うてたわ」
「嫌やないんやけどな」
真顔でそう言うから、困る。
「男と思っとっても好きやった。千歳にとられた思って腹立った。
傷付けたってわかってんに、昨日の泣き顔も可愛え思ってた。
…馬鹿で最低でごめんな」
紡がれる声が、歩く足の靴音に混じって届いた。
俯くしかない。
そうしないと、すぐ声にしてしまいそうで。
忘れられていて悲しかった。
だから、謙也にもちゃんとわかって欲しいのに。
「…そういうんわかってて聞いてええ?」
「…なにを?」
「…千歳と、付き合うてん?」
謙也も多分ちゃんとわかってるって本当は思ってて。
彼だから、きっと許したって自分を責めてまたやつれるんじゃないかとか心配で、それが考えすぎと言えないほど、自分は彼をよく見て来ていて。
昨日今日で忘れるには、あまりに大きすぎるんだ。
自分の、謙也への気持ちは。
だって、今も、見れば馬鹿みたいに震えているのは、謙也の手だ。
「…付き合うてへん。ただ、女の子扱いしてくれるんが、…ようて一緒におったから」
千歳が過保護になったのもあるが。
「…そか」
よかった、と吐き出される声と共に握りしめられていた彼の手が緩んだ。
こんな数分でそこまで緊張する程、好きだなんて。
馬鹿じゃないか。
だったらなんで忘れるんだ。
馬鹿じゃないか。
こんな、気持ち悪い身体の女に。
馬鹿じゃないか。
それがこんなにも、嬉しいなんて。
「…なんで忘れたか、思い出したん?」
「…ごめん。なんで忘れたかも…いつからかもわからん。
そこだけ綺麗に」
「……わかった。もうええ」
「白石! 俺が困るっちゅー話なんや!」
「そうやのうて…。
これから、謙也が…女やって忘れへんなら…もう、ええ」
て意味、と背中を向けて言うと一瞬の間の後、背後から伸びた手が白石の手をぎゅっと握った。
見ると、ひどく嬉しそうに笑う顔。
…現金なヤツ。
そう思ってくすりと笑った白石の手を緩く握った謙也の手が、暖かい。
(……ほんま、なんで忘れてられたんやろ)
謙也自身、不思議でならない。
運動をしていて、あれだけ強くても。
こうして改めて見た白石の指も、手首も、服に覆われた腕も足も、肩幅も。
自分と比べてあまりにも頼りなく細いのに。
こんなにか細い身体の少女を、男と信じ込んでいた自分が信じられない。
(ほーんま、アホや俺)
こんな細い身体の腕を強引に掴んだり、首を掴むような真似をしていた。
軽く握っただけで折れそうな柔らかい肉も骨も、男とまるで違う。
あまりにか弱すぎるのに。
(そんな身体にあんな馬鹿力使っとった……)
いっそ愚か者と誰かに思い切り殴って欲しいが、一番効き目がありそうな石田はまずそんなことを他人にしないし、小石川も理由がないなら人を殴らない。
財前は殴ってくれる可能性はあるが、延々理由を問いただされそうだ。
千歳は論外。恋敵(かもしれない)に殴られたくはない。
「…謙也?」
「え?」
「…いや、変な顔しとった」
「…あ、ああ……。いや」
?と首を傾げた白石に、もう一度なんでもないと言った。
しかし、千歳も見る目があるやつだ。と彼女の首に巻かれたマフラーを見る。
白石が大抵着ているコートや、他の私服にも無難に合う感じの色味とデザインだし。
なにより、彼女の小さい顔や薄い色の髪によく似合う派手じゃない色。
女の好みさっぱりわからんタイプだと思っていたが、それは改めないといけない。
それに、
(…嫌われ、…かけた…んやからな…俺は)
話してくれて、手を繋いでも大丈夫なら徹底的に嫌われてはいない。
だが、今までの信頼も失った。
彼女が自分に向けていた気持ちも、もう今は期待出来ない。
これから、もう一度自分を見てもらえるよう努力しなければならない。
急に強くなった手の力に、白石がどうしたのかと謙也の顔を見る。
「…謙也?」
「…あ…いや」
「…なに、悩んでん?」
「…悩んではないし」
「嘘や。お前そうやって平気な顔して痩せたり成績下げたりする」
「成績は覚えあるけど…痩せ…?」
無自覚か、と呟いた白石の顔に既視感があった。
昔だ。
昔、まだ確実に自分が彼女を女と覚えていた頃。
その時に見ていた顔だ。
(…ああ)
今まで彼女が男に見えていたなんて嘘。
見えていたなら、それは自分が忘れていたからなだけだ。
女の子、と思い出しただけ、理解しただけで、こんなにも。
誰より可愛い顔でこっちを見るのに。
ホンマ、アホ。
「……んーん、…嫌われた分…頑張らないと…ってだけ」
嘘を吐きたくなかった。その顔に。
そう答えた謙也をきょとんと見た後、白石は一瞬口を開いて閉じ、俯く。
ああやっぱり、と思った謙也の頭に、聞き慣れた声のトーン。
「…アホ。んなわけあるか」
「…え?」
「…男て言われてへんかったら好きや言うたやろ。
昨日の今日で嫌いになれるわけあるか…。そら、その上ずっと男や言われたら嫌いになったやろうけど…。
今…ちゃんとわかってくれてんのに。
……」
「…白石」
「……俺が……謙也を嫌いになれるわけ…ないやん」
本気で本気で、ずっと謙也が好きなんやから。
そう呟かれた声は、一瞬吹いた風の所為で不明瞭になったけれど、自分の自惚れな幻聴じゃない。
前を歩く彼女の顔が、耳まで赤いから。
「……“やから”……、て、言うた…?
“やったから”…やない?」
「……」
白石はもうなにも言わなかった。
その代わり、微かに、けれど確かに頷いた。多分。
「……っ」
自分は現金だ。今、馬鹿みたいに幸せで、顔がにやけてしかたない。
「やったら、ちゃんと頑張る。余計頑張る。
今度こそ、ちゃんとお前に言えるように」
「……」
なんて?と聞くように振り返った顔に、笑った。
「俺のお嫁さんになってください、て」
真顔で言ったら、真っ赤になった顔が咄嗟に自分の足を踏みつけてさっさと先を歩いたが、痛くない。
幸せボケしたというなら言ってくれ。光でも誰でも。
でも、幸せなのだから仕方ない。
「白石! 昼飯食べ行こ!」
「あ、うん。…ごめん、先行ってて?」
昼休み、謙也の誘いに頷きかけて、白石ははたと立ち上がった。
「え? なんかあんの?」
「委員会の予定聞いて来な。すぐ済むから先行ってて」
「一緒に行こか?」
「そしたら特等席とられるやろ」
「…そやな」
なんとか納得させられる形で頷いて、謙也はいつもの屋上に向かった。
屋上の扉を開けて、やっぱり特等席とられてたから別のとこ行こうと白石に言いたくなった。
特等席は空いていたが、おそらくいつものように授業をサボっていたサボリ魔の姿がある。
「あ、謙也―――――――――――――てこつは、今の昼休みのチャイムか」
「なんのチャイムや思てたんや」
「さあ?」
「そこはボケろ。関西舐めてんのか」
「舐めてなかよー。謙也」
「なんや」
無性にいらつくな、と余所を向いた謙也の耳に、冷静なバリトンの声。
「白石と仲直りしたと?」
「……知ってて聞くんか?」
「白石本人から聞いてよかならそげんすっと」
「やめ。した。これでええやろ」
「うん」
ほんま、腹立つ。
全部知ってます、て顔。
俺の気持ちも、知ってます、て顔。
「…今、初めてお前がむかついたわ」
「今までは違ったとか」
「そうや。お前普通にええヤツやし」
傍にどかりと座って少し高い場所にある顔を睨む。
それにへらりと笑う、緊張感のないヤツ。
そのくせ、
「お前、白石が好きか」
「………………」
聞かれて、少しびっくりした顔は幼くも見えたが、すぐにやりと笑う。
「自覚してなかよ?」
「ないんか」
「さっきまではな」
意味深に言われて思わず見遣った謙也に“お前に聞かれるまでは無自覚に過保護やったけんね”と冷静な分析。
「ばってん、今気付いた。
…女の子として愛しとうから大事にしたかったと。
うん、好いとうよ。白石んこつ。男として、女の子として」
こうやって、誰よりむかつく男の顔になる。
「白石はやらへん。俺のもんや」
「全部なかったこつになったならそうたいね。
ばってん、そうじゃなかろ?」
ぐ、と言葉に詰まった。
白石は好きだとは言ったが、今までのことを許すとは言ってない。
もういい、とは言ったが気にしてない、とは言っていない。
事実、それまでと違う微妙な距離を感じるのだ。
なんの隔たりもなく触れてきていた手に、躊躇いがある。
「……」
「なら、俺んもんに出来る時間もまだあっとね」
「…そうかもしれへん。せやけど、やらへん」
「強がっても俺と謙也、きっと今同じスタート地点たいよ?
謙也がミスしとらんかったら天と地も離れとった場所にハンデつけたは謙也やろ」
「……なにがいいたい」
「宣戦布告。
こっからはお互い抜け駆け上等…てこつ。
だけん、俺も謙也が頑張って白石と付き合うようなったら文句は言わんけん、逆の時は謙也が文句言わんでくれな」
「…上等や」
ほんま、むかつく程食えない顔。
「お前を負かす人間の名前、よく覚えとけ」
「そっちこそ、よろしくな」
よろしくなんかしないだろ。
いけしゃあしゃあとウルサイ大男。
それでも、ああ、女の子には自分より大きい男が素敵なんかもしらへん。
そう考えて最初から微かな遅れを感じた気分の謙也を、後から来た白石が訝った。
→NEXT