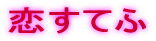
seasonⅥ-あなたのものになろう
第二話-【難攻不落の城の女王-2 エマージェンシー】
嵐のように試験が過ぎれば、待ち受けるのは六月の最大行事、体育祭。
主に忙しいのは運動活動委員会-通称運活と各クラスの委員長、生徒会。
文化祭は文化活動委員会-文活が死にそうになるので、体育祭の運活も以下同文だ。
「じゃ、これ、次のHRで誰を出すか決めてくれ」
職員室で静飼から渡されたのは体育祭の種目の紙だ。
種目名と、それにクラス毎に何人出るかが書かれている。
七組の委員長である白石からは、他にも同じ紙を渡されている生徒が職員室に見える。
「わかりました。先生は、会議が終わり次第来るんでしたね」
「ああ、それまでに決めておいてくれると助かる」
「すぐに決まりますよ、こんなの」
「……どうだろ」
てっきり、淡泊だが明るい静飼らしく“そうだな”と返って来ると思っていた白石は、静飼の、遠い目で呟かれたなにかを達観したような一言に、違和感と嫌な予感を覚えて咄嗟に手に取った紙を見る。
「……あの」
「…あ、なんだ?」
「…この、借り物競走らしき種目の、…名前はどういう意味ですか?」
「…ああ。それな、一番決めるの難儀すると思う」
白石が目に留めた種目。借り物競走には違いないのだろうが、そこには。
“イヤなモノを借りて来よう☆競走”
とあった。
「イヤなモノを借りて来よう…」
「その名の通り、普通の借り物競走じゃなく、とんでもなく嫌な、だが借りては来られるものを借りてくる競走だ。はっきり言って、とんでもなくイヤだろうが、その代わり一位、二位、三位のポイントは高いぞ」
「…たとえば」
「言ったら意味ないだろう」
「そうですが」
「…というか、実は俺達もしらん」
「はい?」
「実は、その競走で借りるイヤなモノは、全部生徒会の会長と副会長が決めるんだ。
だから教師は知らない」
「………」
白石の頭に、あの有楽と、弥勒が浮かぶ。
(よりによって、あの二人の案…)
「…ま、命には関わらないんだ。気楽に決めろ」
慰めるように肩を叩いた静飼に、白石は“まあ俺は別の種目だろうな”と気持ちを切り替える。
千歳か謙也あたり行かせるか、これ。とも。
「……いや、謙也は徒競走だから、小春の方がええか」
「なにがだ。独り言なら漏れてるぞ」
「…すいません。あの、一ついいでしょうか?」
「答えられることなら」
「他に嫌な種目はないですよね?」
「……………………」
「なんでそこで黙るんや静飼先生?」
思わず普段の口調に戻った白石に、静飼は改めて肩を叩くと。
「落ち着いて訊け。いいな?」
「……、はい?」
「まず、男子1500メートル走。女子800メートル走だが」
「…いわゆる持久走は元から嫌なものでは?」
「いや、今回走るコースが変わってな。
男子は裏庭を直線通過(舗装されてない道。しかもヘビがよく出る)、女子は西校舎の側の大池の周りを回る(アマガエルが一杯這い出てくる)のがコースだ」
「………女子が逃げます!(いやマジで!)」
「更に、障害物競走は水場関係が多い」
「…全部苦情が来るでそれ」
「…まあ、嫌な種目はそれくらいだ。徒競走は普通だから。心配するな」
「……とりあえず(俺が出る種目は大丈夫だってことか?)」
とりあえずそれは安心材料なんだろう、そう思った白石は、無言で会釈すると、職員室を辞した。
「ちゅうもーく!」
職員室から戻った白石がすたすたと教室前の黒板に立って、手で黒板を叩いた。
副委員長の小春がチョークを片手に白石から受け取った種目を書き始めた。
「てわけで、体育祭の種目決めや。
種目は、女子100メートル走、男子100メートル走。
女子200メートル走、男子200メートル走。
女子リレー(六人一組)、男子リレー(六人一組)。
持久走、女子800メートル、男子1500メートル。
障害物リレー、男女六人。二人三脚リレー、男女四組。綱引き。
あと、一番のネック、イヤなモノを借りて来よう競走、男女四人」
最後でクラス中が騒いだ。
「イヤなモノ…を借りて来る競走ってことか?」
「その通り。内容は生徒会の会長・副会長が決めるらしいから忍足弥勒っちゅー人の思考をよく考えた上でこれに行け」
明治の声に白石はそう一言。お前は絶対違うからって!と森永に言われた。
「はい」
「あら、千歳くん立候補?」
「いや、イヤなモノじゃなか。
持久走がよか」
「…あー、千歳がいっちゃんあるしな。どう見たかて。
異論あるか?」
「「「「ない」」」」
「よし、千歳、持久走、と。
謙也は100メートル、200メートル行っとくか?」
「任せろ!」
「あとは千歳と忍足と白石と金色で男子リレー行っとけやぁ。
残りは次点で早い水原と森永で」
それはいい、と全員一致だ。
それが一瞬ざわめいた。
「?」
白石が不思議に思って背後を振り返ると、イヤなモノ競走のところに『金色小春・白石蔵ノ介』の名前。
「…なんで?」
「いや、ポイント高いんでしょ? 蔵リンが肌を脱ぐべきよ!
足も早くないときっとダメや!」
「…小春」
白石と逆に盛り上がるクラスに、まあいいかとも思うが。
「それに蔵リンは弥勒先輩の書いたくじを避けられそうや」
「……それは自信あるかも」
己でも。
そう呟いたところで、教室に来た静飼があれ?もう男子決まったのか?とイヤなモノ競走を見て驚いた。
「っへー…。白石が、あの『イヤなモノ競走』」
「感心すんな健二郎」
掃除の時間、同じ廊下の分担になった小石川が心底感心したように頷く。
「いや、ええとこついたんちゃうん?
ウチ、やっぱりお笑い学校やから出場選手のパフォーマンスも得点やし。
ていうか、俺もやねん。『イヤなモノ』走者」
「健二郎もか!」
呪われてへんかテニス部!と言う白石の手から箒が奪われる。
見ると四月の体育で白石にボールをぶつけた例の生徒。
「なんや」
自然険しくなる表情を見て少し退きながら、生徒はちゃうちゃう!と手を振る。
「そうやのうて。…忍足と千歳が怖いんにするか!」
「…なら、なに?」
「さっき、二人が告白されてて」
「二人一緒にか!?」
小石川が驚くと、うん、なんかお互い一人で告白できん子やったみたい、と。
「で、忍足は『好きな人がおるから』て断って」
「やろうな」
「健二郎、重い」
白石の頭に腕を乗せて納得した風の小石川に文句を言っていると、その生徒が笑って。
「千歳のヤツ、『白石一筋やけん』て」
「なんの話ね」
その言葉と同時に背後から来た下駄の音と声と、肩に置かれた大きな手は間違えようもなく。
知っている。
「っ…うわぁっ!」
飛び上がる程驚くリアクションをした白石に、千歳のみならず小石川まで驚いた。
「……白石?」
やばい。答える余裕も言葉もない。
だって嘘じゃない。千歳は本気でそう答える。
顔が赤いのは気のせいじゃない。心臓がうるさくて、声なんか。
『白石一筋やけん』
あの声がそう綴った声が、頭の中で再生される。
出るわけない。
「…―――――――――――――…………とせのアホ!」
うっかり「ち」が言えなかったがそれはもういい。
そう真っ赤な顔で吐き捨てて風のごとくその場から逃げた白石を追えず、茫然と見送った千歳の肩を小石川が叩く。
「白石の語彙が金ちゃん並になっとったんはこの際おいといて…。
お前、なにした?」
「…全然、記憶になか」
信じられない。
大分離れた下の階の廊下で、しゃがみ込んで白石は火照った頬を押さえて泣きそうになった。
気付いたら、すぐ落ちる予感はした。
だから、気付かないようにしたのだろうか。
本当はずっと前から、二人が同じくらい好きじゃなくて。
(千歳が)
気付いた途端、顔も見れなくなったわけじゃない。
あの日から今日まで、一ヶ月普通に話せた。
でもアカン。
ちょっとでも、彼が自分を好きなんだと知るだけで。
そぶりを見るだけで。
堪えられない。
苦しいんじゃない。泣きたいのとも違う。
告げてしまいそうで。
抱きしめて。
って告げてしまいそうで―――――――――――――。
→NEXT