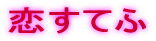
seasonⅥ-あなたのものになろう
第五話
【LOVE PHANTOM 前編・キミを射ち落とす声】
「あれ、白石」
体育祭も過ぎた学校の朝。
自分の席に早くから来ている白石はいつものことだが、クラスメイトの水原と明治が注目したのはそこではない。
「ん? あれ、森永は? 三人一緒やないなんて珍しい」
「俺達は別に。たまに一人寝坊することもある」
「寝坊なんや」
「あいつだけ帰宅部やから」
「で、テニス部なんにはよからおるから?」
白石が聞くと、いやちゃう、と二人揃って。
「テニス部の朝練があったなら忍足と千歳も一緒におるやろ。
三人一パックなのはお前らの方!」
「…卵か俺らは…」
「そやなくて、白石、目薬なんかしてた?」
二人が指さすのは白石の机に置かれた目薬。どうみても市販ではなく、目医者でもらった類の代物とケースでわかる。
「マイティア…なに? 人工涙液?」
「ドライアイの人がする目薬や。涙の量が足らへんのやと」
目薬の文字を読み上げる明治に白石が大したことじゃないと言う。
「なんか、瞬きしてへんと目を開けてられんって思ってたんや。
そしたらドライアイやと」
「健康オタクの白石にあるまじき状態やな」
割り込んできた声に、明治が「あ、小石川」と長身を見上げる。
「そういや、健二郎。お前また伸びた?」
「伸びたんかもな。千歳に追いつかへんのはあいつが更に伸びとるだけや」
「言えとる」
「で、なんでドライアイ?」
「多分、最近パソコンに向かいすぎた所為」
「なんで。今、部長やないし作成するもんないやろ」
「弥勒先輩らがコキ使うんや。お前の方が上手いとか言うて」
ふ、と黄昏た風に笑った白石に小石川が俺が後輩コキ使うなて言うてくる、と頭を撫でた。
「で、久しぶりにパソコンに向かってたからドライアイ?
そのうち治るわ。
…ていうか、健二郎」
「ん?」
「身長高いヤツが低いヤツに男女問わず頭を撫でたがるんって普通?」
「…どうやろ。撫でやすいんは事実。やから勝手に手は出るし。
白石かて金ちゃんや光にはするやろ」
「…ああ、あんなもんか」
「ただ、女子にはやらんわな。そういうのうるさいご時世やし。
それに女子なんか邪フィルターかかってるわバリア張っとるわで撫でられへん」
「…バリアはわかるが」
「邪フィルターの言いたいことはわかる」
意味のわからない白石の代わりに明治が頷いた。
「“この人、あたしに気があるんかな”とかいう可愛いものから“いや、なにこいつ気持ち悪い”っちゅー酷いもんまで千差万別やけど、取り敢えず女子の被害妄想や」
「男子はみんな女見ればヤりたがってるっていうフィルターが思わせることやな」
「そういう意味な。…つか今、女子おらんでよかったな」
「やから言った」
ふうん、と頷きながらなら、あいつらは俺を信用してるんだろうかと思った。
俺は、そうは思わないって。
…あれだけ大事にされて思う女も余程馬鹿か相手が嫌いかのどっちかやろうな。
「っ…、一緒にすんな?」
勢いよく教室に飛び込んできた身体が、聞こえていたらしく、自分も一緒にするなと言って白石の席に来た。
「謙也」
「おお、忍足重役出勤」
「抜かせ。部室で弥勒兄に用事押しつけられたんじゃ」
「…あれ? テニス部は今日部活なかったんやないん?」
「え、あったで?」
小石川がなにを、と答える。
「アレ? ほななんで白石が先にここにおったん?
普通、千歳と忍足を待つやろ?」
白石が先に教室に一人でいた=朝練はない図式だったらしい水原と明治は不思議顔だ。
「白石がさっさと来ただけや」
「……フられたん?」
「てへん。…なんやねん白石」
即否定して、謙也は前の席にどかりと座った。
「謙也。そこ、他のヤツの席」
「朝は関係あらへん。…なに?」
「……」
言う声は、見つからない。
ついじっと見つめてしまって、謙也が急に気まずそうに顔を赤くする。
ああ、謙也だ。
そう思ったら安心して顔が緩んだ。
「謙也見たら安心した」
「へ?」
止めのように微笑むと、更に真っ赤になった謙也が明治たちについに実ったか!と笑われる。
断るのは、まだ先や。
今は、考えるのは―――――――――――――。
よそう、と思いかけた。
不意に向けた視線。
教室の入り口に立ったまま、憮然とした顔で睨む長身に気付いて、思考は急ブレーキで停止する。
「…あ、千歳」
小石川が呼んだ瞬間、千歳は歩いてきて乱暴に机に鞄を置くと、そのまま無言で外に出て行った。
「…機嫌斜め?」
「カノジョが謙也に告白したからか…?」
勝手なことを言う水原と明治の声も、頭に意味もない音として木霊するだけだ。
ダメだ。
がたんと立ち上がった白石が急いでそれを追ったのを茫然と見送って、小石川たちが顔を見合わせる。
「…追わへんの?」
「…今、」
追うと泣くやろ。という言葉を謙也は飲み込んだ。
「千歳!」
しばらく走って前方にその長身を見つけた。
アカン。
しばらく後、とかやない。
そんなことしとったら、なくす。
絶対、なにかなくす。
普通に接することが出来ないのに、先延ばしに出来ない。
なにか、納得のいく理由をでっちあげてでも―――――――――――――。
「…千歳っ?」
呼んだ声は聞こえた筈だ。
なのに千歳は振り向かない。止まらない。
「千歳!?」
全てを無視するように歩く足と違い、こっちは走っているのに追いつかない。
距離が、逆に開く。
なんで?
「千歳っ!」
角を二つ曲がった先に、その長身は見えない。
「……千歳。嘘や……」
無視された。
そして、置いて行かれた。
「……千歳………」
堪らなく寂しくなって、瞳に涙の膜が張る。
その瞬間、ぐいと右手を掴まれて、気付くと傍の教室に引っ張り込まれていた。
背中が壁に当たっている。
見える、大きな彼の身体越しの教室は無人だ。
「…ちとせ」
「ほんに、警戒心なか」
頭上から降った声は、安堵を余所に酷く冷たかった。
「……せ?」
「謙也にいい顔して、それで俺の機嫌取ろうとこげん人おらんとこまでついてきて。
…アホじゃなか?」
頭から、冷水を浴びせられたような気がした。
思考が、停止したまま動かない。
「…今、『千歳やから』なんて言うたら、…犯すばい」
「……………」
怒ってる。
気付いて、る?
自分は、謙也から逃げて部室を先に出たんじゃない。
あの日からずっと。
逃げているのは、謙也からじゃない。
千歳からだ。
「謙也とは普通なんに…なんで俺に余所余所しか…。
見てて拷問じゃなかね。
…はっきり言うたらよかのに」
右手が痛い程掴まれる。
怒っても、女の子には力込められない、って言葉は千歳自身、わからなかったんだろう。
多分、と。思う、と言っていた。
事実、彼は今、すごい力で身体を押さえつけて、手を掴んでいる。
言葉を誤ったら、暴力が奮われても不思議じゃない。
身体が臆する。恐怖に似ている。
身体が勝手に身構える。巨大な彼の身体に。
普段、笑って傍にいるから、感じてなかったんだ。
「謙也が好きって気付いたってはっきり言うたらよかのに!」
言葉が、ない。
なんて言えばいい。
逆だ。
逆だって、言えばいいのに。
なんで言えない。
理由なんてわかりきっていて。
謙也に答えを言ってないからだ。
彼を、フっていないからだ。
「…………違う」
「嘘はよか!」
「…違う。…違うねん。ほんまに………」
もう一度いいと怒鳴ろうとして、千歳は声を失う。
声が震えている。顔を見ると、泣いていた。翡翠から溢れるのは涙だ。
心臓が痛いのは、多分自分が初めて彼女の泣き顔を見たから。
正月に見た涙は、本当に俺の言葉に泣いた涙じゃないから。
『…ええな、お前自制心強くて。俺、もう何回見たやろ』
いつだったか謙也が言った。
強くない。全然、強くない。
謙也を選んだら負けを認める?
どこが。怒鳴って押さえ込んで、全然、諦めて引き下がったり出来ない癖に。
「……そやない…。違う……。
…………らんで」
「…白石」
「…嫌ったらんで」
千歳の瞳が細められて、一度伏せられる。
制御なんか、出来ない。
堪えられない。
俺だって、そんな出来た男じゃない。
掴んだ手をそのまま引き寄せて、後頭部に手を入れて固定して上向かせる。
泣くまま声すら上げない白石を抱き寄せるようにして、口付けた。
こんなの、ノーカウントだって誤魔化す余地なんかない。
正月とは違う。
でも、堪えられない。
一度触れた甘い唇を一度離して、すぐまた塞ぐ。
「ち、とせ…っ」
やっと我に返ったように白石が抵抗する手も押さえ込んで、軋む程抱きしめて何度も角度を変えて口付ける。
「…と…せ…………」
千歳の腕に突っ張るように置かれていた白石の腕が、拒絶をやめたように服を握る。
「…………せ…………………馬鹿………」
掠れた声がキスの合間に呟くのを、どこか遠くに聞いた。
「…白石、白石……」
「………」
唇を離しながら、それでも抱きしめる腕を解かない千歳の腕の中で見上げる瞳が涙に潤んでいる。
「…好いとう」
「……せ」
「…好いとう」
繰り返すしかなく、他に、言葉なんか知らない。
そんなに長く、生きていやしない。
身体は大きくたって、全然大人じゃない。
子供なんだ。
「…愛しとう……。…………蔵ノ介」
そう口にして、なにか言うのを聞きたくないともう一度塞いだ唇は、酷く甘かった。
→NEXT