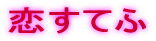
seasonⅥ-あなたのものになろう
第六話
【LOVE PHANTOM 後編・あなたのものになろう】
―――――――――――愛しとう。
そう告げられて、キスをされて、千歳はやがて優しく笑って離してくれた。
ごめん、と言って。
それでも、忘れてくれとは、言われなかった。
「白石! とうとう千歳に落ちたか!」
教室に帰ると今日ばかりはうるさい水原たちに囲まれる。
「…森永はまだおらんのか」
始業するで。とぼやくとあいつは文活でかり出されてるという返事。
傍を見ると、普通の顔で隣に座る千歳の横顔。
視線が合うと、そのくせ困ったように微笑んだ。
「もうそんな時期か」
視線を誤魔化してそう繋げる。
「大変なスケジュールやんな。
体育祭が終わって、夏休み明けに文化祭やから夏休みも文化祭準備に使うために六月の終わりっから忙しい文化祭活動委員会…やなくて、千歳!」
「もう授業始まるし」
「そういや忍足は文活やんな」
「え?」
平静を装うつもりが思わず返してしまった白石に、知らなかった?と明治。
「ほら、今おらんやろ」
そういえば、いなかった。
ということに今頃に気付く自分はどれだけ千歳のことで頭一杯だったのか。
「千歳も変な約束してもうたし」
「え!?」
「…カノジョ、反応顕著すぎや」
「…ええから、なに」
「さっき演劇部の先輩が来て。
千歳の長身見込んで演劇に出て欲しい、て。千歳はオッケーしとったし」
(演劇…千歳が!?)
「…………出来んの? こいつ標準語からして無理やん」
驚いた後すぐそう思わず突っ込んでしまったことを、責めないで欲しい。
なにか期待していたのか、千歳が思わず机に突っ伏した。
「やって、…標準語無理なんは事実やん。
関西弁も論外やろ」
掃除の時間、小石川に零すと確かに、と同意された。
「でもなぁ、あいつにそこ違うって注意出来るかあ?」
「…普通の女の子はでけへんわ」
「…やんな」
そういえば謙也は?と聞かれる。掃除分担箇所は違うのだが。
「あいつは文活でおらんよ。文活は期間は掃除も免除」
「あー…」
「千歳も連れてかれたし」
「…演劇部?」
「うん」
「ほっとかれて寂しいか」
「……」
意外に沈黙が返ってきたので図星か、と小石川が内心ぼやく。
「…健二郎」
「ん?」
「好きな人がわかって…、…でももう一人をフってへんから好き言えん場合どないしたらええ」
「……………………………………………………………………敢えて質問内容にはツッコむまいと思ったが、お前参っとるやろ。俺に相談する自体」
「ほっといてくれ」
「お前がほっといてないやろが」
俺を捕まえたんは誰やねん。
「……そんなん、フったらええ話やん。好きやないってわかったんなら」
「……」
「生殺しやで? 千歳も謙也も」
窓硝子を拭きながら、小石川は一度視線をよこして言う。
「謙也は尚更な。…はっきり言うたれ。
やないと、あいつがいつまでも幸せになれんわ」
「……うん」
ありがと、と小さく呟いて白石が廊下を駆け出すのを、さりげなく押しつけられた箒を片手に見送る。
「…あいつ、なにげに理系やな」
理系ってなんで普通に解ける心のことまでパズルみたいな考え方するんか。
「…おっと、…光に電話しとこう。
フられた謙也によく効く薬や。
…あ、もしもし、光…」
「ほな、忍足、それそっち頼むわ!」
おう、と書類を引き受けて謙也は受け渡しの場所へ走る。
こういう遠い距離を行き来して確かめなければならない作業には定評がある。
足が早い、というだけだが。
「謙也!」
「あ、白石! …掃除は?」
ジャージ姿ということは掃除中だ。
「あ、…抜けてきた」
「白石が。珍しっ」
「…今、平気?」
「これそこに渡したら暇」
「そか」
でもなんやろう。と思いながら待っていた係の人間にチェックの紙を渡して戻る。
「ええで」
「ちょお、あっち行ける?」
「…?」
白石に連れて来られたのは、旧校舎の傍の壁。
(…あれ?)
誰もおらんとこに、二人きり。
で、連れてきたのは白石。
急いでいた様子で。
「……」
期待、してええんやろか。
(いやただの肩すかしって可能性も!)
首を左右に振ってから、なんや、と澄まして聞くと白石はてっきりバレバレやと笑うと思ったのに、うんと頷くだけだ。
気のせい、やない…?
「……ずっと、保留にしとったこと、…返事しに来た」
心臓が一瞬酷く高く跳ねた。
目を下に向けた白石が、すぐ謙也を真っ直ぐ見つめる。
「……こと、って」
白石はよどみなく言うのに、俺の声が掠れて出ない。
「…謙也と、千歳。…どっちが好きか」
心臓が誤魔化しが効かない程うるさくなって、彼女の声すら聞き逃すんじゃないかと思う。
「……わかったん?」
「…うん」
「……」
どっちが?
聞きたくて、聞きたくない。
天国と、地獄だ。
「……千歳に、言うた?」
「…あいつには、…まだ」
「…」
「お前に、言うてから…」
それは、喜ぶことかわからない。
順番で、決まることじゃない。
「…俺は、…どう思てん?」
「…」
白石が手を握り合わせて小さく笑った。
「…一生大事」
「……て」
まだ、わからない。
「…謙也が思いだした日の言葉に、嘘はない。
謙也は一生、好きや。
…一生、特別で、大事な男の人。
……愛しいて、大事や」
「……しらいし」
「…だから……」
白石は一度握った手を離すと、深く謙也に向かって頭を下げた。
「ごめん」
「……好きで、でも…恋愛やない。多分。
今はまだ、恋愛の好きはちゃんとある。
でも、…きっと、どんどん好きになるあいつへの気持ちに負けてく一方や。
……いつか、ただの友だちになってまう。
ならへん可能性は高くて、相変わらずきっと好きや。
恋愛で多分。
…せやけど…二番目の好きを選んで…誰かが幸福になれるとも、俺が幸せになれるとも思わん」
「……、そ……か」
「…ごめん。ありがと。ずっと、守ってくれて。
…大好き、謙也。
……はっきり、嫌いて言えんで、…ごめん」
伸ばした腕で、白石を抱きしめた。
その己の両手は震えている。
彼女にも伝わっている。
かっこわるい。
「……好きや。白石、…大好きや……!」
「…うん。…知っとる」
「…好き。めっちゃ好きや。…大好きや。大好きや白石…!」
「……うん」
瞳を破って溢れる涙を、もう見られてもどうしようもない。
堪えられない。
「…愛してる……」
そう、告げた瞬間、終わったんだと胸に落ちた。
繋ぎ止めたくて、往生際悪くすがって言った言葉じゃない。
今が、最期だから。
俺が、キミに自分の愛を告げられる、今日が最期の日。
白石はわかったように、おとなしく腕の中で瞳を閉じる。
その瞼から涙が伝ったのを、多分、俺は忘れない。
一生、忘れない。
『謙也、……どうしたん?』
見上げる顔があった。
中学一年の冬。
家の中で押し倒してしまった。故意じゃなかった。
でも焦って、すぐ身体を繋げたい程感じた欲望を。
もう殺せないと思った。
ずっと、その夜、願った。
忘れろ、って。
あいつを傷付けないように。
あれだった。
俺が、白石が女の子って忘れた理由。
やっと思い出した。
「……ほ、ほんなこつに」
「はい、ストップ。『本当に』」
「…だけん、無理言うたとに」
周囲の女子部員が笑う。
時間あるからドンマイと、背中を叩かれて、じゃ私ら帰るから、と手を振られる。
ばいばいと見送ってから、一人きりになった体育館で台本を片手に天井を見上げた。
正直、欠片も演劇に興味はなかった。
シナリオを聞いて、ついうっかりうん、なんて言ってしまって。
物語は貴族の女性が詩人を愛するために家も性別も捨てる。そういう話。
アレンジはしてあるらしいが。
「…見てたけど、お前ホンマにアカンな」
くすくすと笑う声に振り返った顔に、そうぶつかった意地悪な顔。
「…白石?」
「他の誰に見えんねん。眼鏡買うか?」
「…いや」
なんでここに、しかもジャージで。
そういう質問は飲み込んだ。
今は、普通に会ってくれるだけでいい。
朝、暴走した思いはそのままに、今は遠ざけたくない気持ちが必死で。
「代役やったろか?」
「白石が!?」
「本番の役やのうて。一人で台詞言うん空しいやろ。
相手したろか、て」
「…よかの?」
「ええって。お前に注意出来るやろ」
「?」
「標準語」
そげん意味ね。と安堵と少しの寂寥。
ちょっと、練習すると舞台の端に向かった千歳から台本を受け取って、白石は指さされた部分の台詞を見る。
台詞なんか、ホンマは覚えなくてええ。
こんなん、言うつもりはない。
謀ったんやから。俺は。
お前に告白したぁて、お前になんでもない顔を謀った。
やから、言うまで騙されて。
魔法が解けたら、驚いてくれ。
言葉遣いを考えている千歳が、もうすぐ出てくる。
震えてきた足に、自分を笑う。
(今更、なに怖じ気づいとんねん。俺)
もう、後戻りは出来ない。
謙也を選べないと、謙也自身に先に告げたんだ。そうしないと、狡い心は千歳に受け入れられなかった悪い想像に負けて、言えず逃げて謙也にすがりつくだろうから。
手が震えて、仕方ない。かっこ悪、と呟く。
テニスの試合より、怖い。
逃げるな。逃げるな。…今日だけでええ。ちゃんと、戦え。
ほんまはずっと戦わな付き合っていけへんけど、未来を考えたら今は潰れるから。
今だけ、未来に目隠しをしていいですか。
あなたの答えも、あなたが口に出す瞬間まで、どうか目隠しをさせて。
靴音が背後で響く。
振り返るな。
振り返りたい衝動を押し殺す。まだ、時間じゃない。
たった一瞬の、告げる魔法の時間じゃない。
「…」
息を整えた千歳の息が聞こえて、背中に感じる視線に背筋が震える。
恐怖じゃない。
もうすぐ、あの腕に飛び込めるんだ、と。本当に、あの腕だけ選んで傍で、言える。
好き―――――――――――――と。
心臓から上る震えは、恐怖じゃない。
「『本当にヴァイオラなのか?』」
「『はい』」
「『夢のようだ。これから、一緒に生きてくれるんだな…?』」
心臓が一瞬、強く高く鳴ったのは、恐怖じゃない。
目を一度閉じて振り返った。
舞台の台詞は『はい。これからは男としてあなたと共に生きましょう』。
でも、俺の台詞はそれじゃない。
「はい」
見上げる顔は、台詞が覚えた通り来ると疑っていない顔。
そういう顔が、綺麗で好きだった。好きになった。
お前も、綺麗なんや。千歳。
「これから、男の俺は捨てましょう」
「……え」
驚いた千歳がなにか言う前に見つめて、声を必死に絞り出す。
掠れないでくれ。最後まで。
「これからは、女として、あなたと共に生きましょう」
逃げないでくれ。最後まで。
「…しら…い……し…? ど、げん意味…」
動揺して、戸惑う顔がどうか『まさか』という期待であるように、誰かに祈った。
「あなたが好きです。…謙也やなく、千歳が」
もう、震えても許されるだろうか。
「俺はお前を愛しとる。
お前を選ぶ。
謙也より、…誰より、お前が好き。
千歳千里の全部が好き。
…大好き、千歳」
真っ赤に顔を染めて見下ろす顔が、俺のように震えている気がして、同じ意味で。
だから、真っ直ぐに微笑んだ。
それは、嬉しい、喜びの、恋の震えだ。
「俺を、お前のもんにしてくれ…」
手から捨てられた台本が床に落ちる。走るように傍に立った巨躯を瞳が認める前にすぐきつく抱きすくめられた。背中に回された右手。左手が頭を抱き寄せて、鼻孔をくすぐるのは前にも嗅いだ彼の匂い。ずっと、この匂いの中で、手の中で素直に背中に手を回して、好きと言える日を、自分を、待っていた。
「…ちとせ」
「……ほんに…夢じゃなかね…? 俺、…」
「…当たり前や」
千歳の声の方が、掠れていた。
泣いてるかもしれなくて、でも離してくれないから見えない。
「…白石。…好いとう。…ほんに好いとう。
…愛しとうよ………………」
囁かれるように告げられる愛を、もう苦しく思わなくていい。
そっと上向かされて降りてくる唇。もう、怯えることはない。
そっと瞳を閉じた瞬間、重なったキス。
手が抱く場所が、触れた唇が熱くて、一瞬夢のようなことを考えた。
このまま溶けて千歳と一つになりたい。
そう、願った。
旧校舎まで響く生徒の声も壁に背を向けて座り込んだ自分には遠い。
靴音が頭上で聞こえたが、白石なんてことはないだろう。
おおかた、大抵耳聡く来る後輩。
「…泣いてんスか?」
やっぱり。そう笑った声は、誰にも明らかに泣いていた。
謙也の頭をぽん、と一回だけ撫でて財前は笑うこともせずしゃがんだ気配。
「後輩としては、先輩の失恋相談の一つくらい聞きたいですけど」
「逆やろ…アホ」
「そうです。アホですよ」
「…ちゃうやろ。なに肯定してんねん…。
……フられたわ」
「知ってます」
「……でも、あのまま終わるよりは良かったんや」
あのまま、白石を男と思って、千歳に獲られたと思って諦めるより、きっと、ずっと。
はい、と後輩が優しく笑った声。
「ずっと、カッコええですよ」
「……殺し文句やわ……」
そのまま、顔を押さえたまま壁にもたれかかって泣いた。
ただ、思うままに泣いた。
後輩はずっと、そこにいて静かに微笑んでいた。
→NEXT