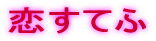
seasonⅦ-彼氏彼女の夏休み
第三話-【白い世界~夏の墓標-静かな夜の恋】
『謙也はしらん。謙也が親戚の家泊まってた間やし、親も謙也にだけは内緒にした』
白石を送った後、帰ってきた自分の部屋の鍵が空しく響いた。
『でも、ホンマになにもされてへん。服脱がされたりしてへんし、男や思われてた筈や』
「…ほんなこつ?」
白石の家の前でそう聞いた千歳に、頷いた。
「ほんに、なにも?」
「当たり前やろ」
「……」
なお心配そうに見下ろす顔を、白石が頬を赤くして見上げる。
「なにもされてへんかどうか、…俺をお前が抱けばわかるやろが…」
「………あ」
「女は初めてかどうかわかるんやし……」
「……、あ、そう、たいね」
千歳もやっと気付いたらしい。案外根本がすこんと抜けるところがある。
「…じゃ、他に、そのことで隠しとうことはなかね?」
「…他にないやろ」
「…信じてよかね?」
肩を掴んだ手に、手を重ねて頷かれた。
「なんも、ない」
玄関に消えた白石を見送って、つい彼女の部屋の明かりがつくまで立ち尽くしてしまう。
明かりを見上げて、帰るかと門を出たところで謙也とはち会った。
気まずくはないが、なんか気まずい気がする。
「よう、デートの送りか?」
「当たりばい。謙也が昨日白石と一緒におった謎は解けたとよ」
「服やろ? 可愛えやろ?」
やけに自信満々に笑われて、うんと押されて頷く。
「あれは俺が選んだんや! 褒めろ!」
「……」
「ノーリアクションかい!」
「…俺、今まで『謙也がうざい』っていう光の気持ちは理解出来んかったばってん、今ものすげー理解出来たばい………」
「…失礼やな」
光を引き合いに出したあたりがえらい失礼や、とツッコミをいれてから、謙也はふと白石家を見上げて。
「あいつ、デート、やんな」
「…? なに言うとーと?」
今更。
「二人きりやろ?」
「うん」
「…夏で、あの格好やったん?」
見てたと?と言いながら千歳は謙也のいわんとすることがわからない。
「…いや、デートで、夏で半袖で女の子の格好で、白石ってわかるんはお前だけやのに」
「……?」
「あいつ、包帯巻いたまんま?」
えらい服装から浮いてへんか?と謙也に言われて気付いた。
今まで、包帯のない白石を見たことが一度もなかったから、普通に見えても自分はおかしいと思わず流していた。
謙也は逆に、冷静に横から見たから気付いたという。
『俺も、付き合って一緒に行ったんやったら一杯で気付かへんわ』
謙也の声が木霊する。
ベッドに投げたままだった携帯を引っ張って取ると、メモリから探した番号に通話ボタンを押した。
「連日誘ってごめんな」
千歳に迎えに来られて、彼の家に連れて来られた白石が別にええ、と笑う。
今日は普通の男女どっちにも見える服装で、思い返せばそういう服装が白石は多かった。
部屋に上がった白石を自然に寝室に招く。
特に疑問も感じずついてきた白石に、そこ座ってとベッドを指して飲み物持って来ると言うと、頷いて素直に座った。
「明日からはずっと部活やし。やから嬉しいし」
「…うん」
「…ちとせ?」
キッチンに行こうとしない千歳を白石が不思議そうに見上げる。
「…もう、ナイショはなか、て思ってよかね?」
「……うん」
視線を外さず白石が言う。
「…安心してよかね?」
「……うん」
微かに頷いた彼女の肩を掴むと、え、と顔を上げた白石の唇を塞ぐ。
「……ん」
驚いたのは一瞬で、すぐ目を閉じた身体を抱くと、そのままベッドに押し倒した。
「……え……、」
「…」
「…ち、とせ」
流石に押し倒されて、戸惑った白石が呼んでも、それを見下ろすのは真剣な千歳の顔だ。
別に、もう恋人だからおかしくない。
それは、早いとか思うけど、千歳はそもそも手が早そうだし。
「……イヤ?」
そんな風に優しく聞かれて、イヤなんて言えない。
ぎゅ、と目を閉じるとそれを返事と受け取った千歳が覆い被さってきた。
ぎし、とベッドが軋む。
手首を掴まれたまま、何度もキスをされて力が抜けていく。
そのまま首筋を辿った唇が一つ外したボタンの隙間に触れる。
小さく身を震わせたのを見た千歳が、不意に左手に手を這わせた。
つい、と包帯の結び目にかかった指に、驚いた身体がびくりと大きく反応してしまって。
それを見た千歳が少し身を起こして、やっぱりと呟いた。
「…とせ?」
「…まだなんかあっとね? …誘拐されたこつで。…左手に」
そう問う千歳の瞳に、もう先ほどのあの熱はなくて。
気付いた瞬間、冷えた頭とは裏腹に、軋む程痛んだのは胸だ。
「……白石」
「……わざとか?」
「え」
「……続けて呼んだのも、…ここに座れ言うたんも……押し倒したんも…わざとか」
俯いたまま呟いた声の感情のなさに、千歳が白石が感じた意味を理解してハッとした。
「っけんな!」
がたんと大きな音がする。
勢いで床に腰を着いた千歳が、殴られたばかりで感触のない頬を押さえずに見上げる先に立った顔が、涙と怒りに揺れている。
「お前も、…毎日会いたいって思ってくれてるんやって…。
ここまで呼んでくれたんは俺だけやって…。
…千歳なら今抱かれてもええて馬鹿みたいに思ってたんは俺だけか!」
「違っ…」
「…なんやの…わけわからん……。
……こんなん、付き合う前の方が楽しかった!」
ぐいと乱暴に涙を拭った手がなにも持たずに寝室の扉を開けて駆け出す。
「…白石…っ!」
すぐ立ち上がって追いかけた足が、道路に出た頃にはその姿はどこにもなく。
「………、しら」
裸足のまま地面に落ちた足に感じるこの季節の熱さも意味がない。
「………」
ごめん。
知りたくて、その結果がこれだ。
愛しすぎて間違えて、お前がどれだけ俺を思って、その先を覚悟してくれたかも気付かずに。
…騙す真似をした。
それが、彼女にとってどんな酷い裏切りかにすら、気付かずに。
「蔵~。……ご飯やで?」
帰って来るなり部屋に閉じこもった妹を呼んで、鍵のかかった扉を叩くもやはり返事はない。
櫻はなにかあったんか、と思いながらも口にはしなかった。
「話せたら、話しは聞くから…」
それだけ言って階段を下りた。
一方、同時刻。午後七時の忍足家の玄関を黒髪の従兄弟がくぐった。
「ええておばさん。俺が行ってきます」
謙也に行かせるから、と言う謙也の母親にいいと笑って頼まれた買い物リストを片手に門を出た。
そこではた、と隣の家の門の前。じっと上の階の明かりの灯らない窓を見上げる長身に気付いた。
「千歳?」
「…あ」
「千歳やんか。どないしたん。入ればええやん」
駆け寄った侑士に気付いた千歳が、少しだけ困ったように微笑んだ。
「…? …、お前、なん」
気付いて侑士が言葉を失う。
「…靴くらい履いてきぃ。どんな喧嘩したかしらんけど」
千歳の足は素足だ。彼の家からそのまま来たのなら当然だが、汚れている。
…自分は千歳の家なんか知らないが。
「いや、履いてきたばってん」
「?」
「…電車降りた時、…うっかり排水溝の溝にはまって」
とれんかったけん、そのまま脱いできた。
「…アホか」
駅員さん呼べや、と言おうとしたが多分、そんな暇すら惜しい喧嘩をしたのだろう。
「…なにがあったん?」
一応聞いた。本当に、一応。
結局、白石も千歳も謙也の気持ちも自分にとっては対岸の火事である。
従兄弟の謙也には親身になれるが、千歳や白石には無理だ。
「…俺が馬鹿やって、泣かせただけばい」
「……」
「…どれだけ思われたかも気付かんで…裏切った」
(そんな顔して悔いてんなら、『裏切った』言わんやろ……)
「完遂してこそ『裏切り』は裏切りやてわかってんのか…」
「え…?」
「いや、…その頬、白石か。…湿布くらいしろや」
一応言ったがもう腫れている。無駄な忠告だ。
「……ちなみにグーか?」
「…グーばい」
「…まあ、育った環境が男子テニス部部長やからな…」
普通の女の子みたく平手やすまんか…。
「…よっしゃ。千歳、ここであと十五分だけ待てるか?」
「え? そら…」
「俺が一肌脱いだるわ」
侑士はそう言うとにこりと笑った。
時計が一度大きくかち、と音を立てた音に少し顔を上げた。
ベッドから身を起こすと、脇のゴミ箱にティッシュが相当溜まっていた。
「…どんだけ泣いたんや俺」
掠れた声で呟くと、立ち上がって明かりをつける。
そのままふと沈んだ空が見える窓を見遣って、ぎょっとした。
「…千歳っ?」
門の向こうに立って見上げている顔が、ついた明かりと見えた自分の顔に安堵したように笑ったのが見えて。
思わずその場にしゃがみ込んで隠れた。
「…いつから」
言ってから愚問だと気付く。
ずっと、いたんや。
「蔵、お客さん!」
「え?」
千歳? いや、だって彼はまだそこに。
コンコンとノックがされて、咄嗟に鍵を開けると開いた扉から現れたのは謙也の従兄弟。
「…忍足くん」
「よ」
ども、と手を挙げると侑士は断りなく床に座って、飲む?と持っていた袋からペットボトルを一本取り出した。
「……なんでキミが。謙也やなく」
「謙也やったら千歳がもう一発殴られとるわ。あいつは気付いてへん。
…ま、なにがあったかなんてしらんけど」
あいつは全然話さへんし、と千歳を指していい、侑士は受け取ってもらえないペットボトルを床に置いた。
「俺には話さんでええ。謙也にも。
俺達は他人で、…責任は持てん。それこそ一切。
やってお前と千歳だけの問題や。結局、全部」
「……そら」
「……一個だけそんでも聞くわ」
「……、」
「お前、あいつに裏切られた思た?」
その言葉にぎくりとして、すぐなんで、と返す。
思わなかった、は嘘。
でも、本当に裏切られたって思えるかって聞かれたら、あり得ない、だ。
そんなやつじゃない。
「あいつは言うとった。裏切って傷付けた、て」
「…千歳が」
「俺が想うに、お互い夢中になっとるだけちゃうん?
お互いに、やのうて。
やっと三角関係やのうなって晴れて付き合うて…、どこまでが線引きかってラインがなくなったから。
特に千歳は念願叶ったわけやから、そらお前に夢中んなるわ。
シたいやろし独占したいし、なんでも知りたい」
「…………」
「喧嘩って、ヒントがないとでけんよ?」
知りたい、と思ったからだ。
千歳が。
話したいと思って、でもあのことだけ話せなくて騙したからだ。
…喧嘩をするヒントは、俺が蒔いたんじゃないか。
「おおきに」
「…、答えは見つかった?」
本当にそれだけが用事だったのか、侑士が立ち上がる。
「うん」
「そか。俺、暗号とか得意やねん」
得意げに笑うと、侑士は袋をやる、と置いて部屋を後にした。
→NEXT