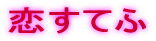
seasonⅡ-聖・バースディの夜に
第二話-【LUCKY NUMBER“24”】
手を繋ぐのは、嫌いや。
支度をして家を出た白石を、門のところで謙也が待っていた。
十二月二十四日。
「中で待っとればええんに」
「ええて。ほら」
ひょい、と差し出された手に、意味を掴み損ねた。
「…なに?」
「手、繋いでこ」
「…謙也」
溜息を吐いた白石の手を、文句を言う間なく謙也が掴んだ。
「ええから。はよ行こ! あ、俺らがケーキ買ってくんやって」
引っ張られて、なにをそんなにはしゃぐのかと肩をすくめる。
手を、繋ぐのは、嫌いなんだ。
イルミネーションが飾る街。
人通りも多く、ほとんどがカップルだ。
「謙也」
「ん?」
「手、もう離して」
「なんでや」
「はぐれたりせんし」
「…そういう意味やないんやけど」
知ってる。それくらい。
「せやけど、万一ってこともあるし。危ないやん」
「なにがや」
「やって」
「俺はどー見たかて、男なんやから。なに心配することあんねん」
「……」
言い方が気に入らなかったのか、謙也が黙った。
言い過ぎたと思った。精一杯、女の子扱いしてくれるのは、嬉しい。
けれど、
傍を通るカップルの声が聞こえる。
男同士やな?と。男同士で手?ホモか?と。
「……やねん」
「え?」
ぽつり、呟いた白石に謙也が耳を寄せた。
手を、繋ぐのは嫌いや。
小学校にあがる前まではよかった。嬉しかった。
けれど、成長するにつれて、手を繋ぐ俺達によこされる視線は「微笑ましい」ではなくなった。
ただ、「気持ち悪い」というソレ。
『白石、普通男の子同士で手を繋いだりしないだろう?』
いつだったか、学校の担任がそう言った。
気持ち悪いとは言わなかったが、おかしいとは、異常だとは言ったようなものだ。
手を繋ぐのは、嫌いだ。
手を繋ぐだけで、気持ち悪いと言われる。
おかしいと。異常だと。
それは、繋いだ相手にも向けられて。
結局俺が堪えられなくて無理矢理離すから。
だから、手を繋ぐのは、嫌いだ。
繋いだって、結局離さなきゃいけないんだから。
「…嫌いなんや。手を、繋ぐん」
「…………」
黙り込んだ謙也が、手を離したのは助かった。
けれど、同時に寂しくなる。
とことん、自分は馬鹿だ。
「白石!」
呼ばれて、はた、と俯いていた顔を上げる。
視界に飛び込んできたのは謙也の笑顔。
そのまままた、手を掴まれてそれを謙也の手ごと、謙也のコートのポケットに突っ込まれた。
「謙也っ!?」
「手を繋ぐんやないならええやろ?」
「…そういう、問題やない」
周囲の反応なんか、見なくたってわかる。
なのに、彼はこっちの当惑も全部理解したように言うんだ。
「俺は恥ずかしくないし、嫌やない」
手を、繋ぐのは嫌い。
「……アホ」
「お前に関しちゃ、アホでええ」
ずっと、離さないでって、願ってしまうから。
千歳の家について、謙也の手にあったケーキを切り分ける。
「これ、四人で食べるには大きくありません?」
「問題なかろ? 男三人おれば」
「ああ。そらなぁ」
こういう時、さらっと自分を「男」から除外する千歳の言動には馴れた。
「ちゅーか、これ全部千歳が作ったん?」
「いや? さっき白石もキッチンおったろ? 半分ずつ」
「どれが?」
白石の?と聞く謙也に、お前失礼に素直ばい、と千歳の声。
「言うたら白石さんの分だけ売れそうっスから言わんでええですよ千歳先輩」
「お前は嫌やないんか? 光」
「そうやのうて。言われたら俺も千歳先輩の食べたないし。
せやけど、一応人様の誕生日に沢山食べ物残すんアカンでしょ」
「正確にはクリスマスて、キリストの誕生日やないけどな」
財前が知ってますけど礼儀上。と一言。
「え!? キリストの誕生日ちゃうん?」
「ちゃう。キリストの誕生日は九月か十月。十二月やないんは確か。
十二月二十五日は冬至の祭りや」
「っへー……てか、白石、なんでそない詳しいん?」
「うちは姉ちゃんが高校がミッションスクールやったから」
「ああ、櫻さん」
「光も知っとうたな?」
「俺は兄貴が櫻さんと同じ感じなんで」
「ああ。どっちも上兄弟ソースな」
切り分けたケーキを当分しながら、そういえば上兄弟おるん半分ですね、と財前。
「俺と部長はおるけど、謙也くんと千歳先輩は下兄弟がおって上はおらん」
「ああ。そやな」
「そういや春霞くんは今日は家で?」
「春霞は友だちん家」
「ああ」
「ハルカ?」
「謙也の弟。中一で四天宝寺に通っとるよ。あんま学校では話さへんからしらんやろけど」
「そういえば、なんで学校では他人の振り?」
「もうちょいオブラートに包め光。…いや、そうやのうてな。
春霞は話したいらしいんやけど、俺が年中他の…具体的にお前らやら小春やユウジらとつるんどるから、…話すに話しかけられへんのやと。
あと、話しかけて『なんかあの眼鏡の兄ちゃんに近づくん嫌や』らしい」
「…小春先輩を嫌がっての結果スか」
「みたいや」
フォロー出来ませんね、悪いけど。という財前の一言。
「そういえば、みんなってなんか用意して来たん?」
プレゼントな。と謙也が当たり前と笑った。
「ほな、まず俺から。ほい」
「俺?」
謙也が千歳に渡したのは小さな包み。
なんだろうと首を傾げた千歳が開けると、そこには。
「……ジブリの」
「…となりのトトロのぬいぐるみ……」
中三男子のプレゼントが?というニュアンスの財前を余所に、謙也がいかにもきらきらした目線でそれを見つめる千歳に誇らしげに言った。
「お前がこの前ゲーセンで欲しい言うてとれへんかった景品や。
感謝せえ。結構回数頑張ったんやで」
「ああ。UFOキャッチャーの景品か」
一瞬、そういうショップに足を運んだ謙也が浮かんでしまった財前が安堵のように呟いた。
「で、光へのプレゼントはもう済みな」
未だぬいぐるみを凝視する千歳を余所に一言。
「はい。俺の謙也くんへのも済みで」
「え? なんなん?」
「ほら、この前言うてたライヴ。あれ抽選やったから。
会員になって当てたんが俺で、金は光持ち」
「会員になるにも金かかるんで一人で全部は中坊にはきついんでプレゼントいうことで半分ずつ、て決めたんですわ」
「ああ。そうなんか」
納得した。と白石。
「で、白石にはこれ」
ひょい、と渡されたのは一枚のCD。
「探してたやろ」
「…うん。どうやって見つけたん?」
「ものっそう嫌やったけどな。弥勒兄のツテや。あの人バイト先がショップやから」
「あはは」
白石への謙也からのプレゼントは所謂、限定アルバムだ。
人気もあり、かつ予約分だけで売り切れる代物だったので諦めていたらしい。
流石幼馴染み。好みは知り尽くしてる、ということか。と財前。
「俺はケーキ以外の食材買ったんでパスいうことでええんですよね」
「そうそう。光はそれで」
「あ、俺たいね?」
千歳がやっと顔を上げてこたつの傍から二つ包みを取り出した。
「これは光と謙也に」
「はい。ありがとうございます。…なんですか?」
「もう高校生やけん、使うことあるかもしれんって。
キーケース。色違いの」
「へー。おおきに」
「俺はまだ中学生です」
「せやけん、来年やと別のもんあげそうやったし」
「これはやっぱりダブルスやから?」
「そう」
で、白石へはこれ。と取り出したのはそれなりに大きな包みだ。
「……服かなんか?」
柔らかいし。と手に取った白石に頷いて開けてみてと促す。
「高かったけん諦めとったんやけど、同じもんを九州の従兄弟が店で扱っとうて、特別にもらえたと」
包みの中から出てきたのは、真っ白のシックなデザインのセーター。
「…これ…っ…あの時俺が見てた…!」
「そう。今言うたやろ? あそこのは高かったけん、て。
ばってん、従兄弟が向こうで扱っとう店におったけん」
「………」
「サイズ大丈夫…と?」
少し不安げに問う千歳に、首を左右に振って、白石はううん、と繰り返す。
「…うれしい………」
零された言葉と、一緒のその微笑み。
謙也まで真っ赤になってしまって、向かいにいた財前と顔を見合わせて呟く。
「なに、光まで赤なってん」
「…いや、あれを可愛え思わん男はアホっスわ」
「…そやな」
「あ、…ありがと」
お礼忘れてた。と言い直した白石に、千歳がどういたしまして、と微笑んだ。
「…謙也くん」
「へ?」
「『へ』やのうて、…失敗したっスね」
見つめた後輩の顔が意地悪く笑う。
「女の子向けの、喜ぶプレゼントリサーチ不足。
謙也くんの負けやな」
「っっっっっっっ…!」
「…どないしたん?」
「…ばってん、うまかね」
白石からのプレゼントも渡って、落ち着いた室内。
料理を口に運びながら、千歳が不意に言った。
「…ほんま?」
「うん」
「…姉ちゃんに聞いただけやったから。よかった」
なんかええムードやけどええんか?とふと見て財前は軽く呆れる。
謙也はといえば、半分寝ている様子だ。
(…まあ、基本夜更かしせん人やからなぁ……)
後、俺がおってどうこうなったりせんて安心も手伝ったか、と時計を見ると既に二十五日だった。
「白石て」
「え?」
「よかお嫁さんになれっとね」
「………」
千歳の言葉に声を失った後、白石が無理やろ、と視線を逸らした。
「貰い手がおらんわ」
「そう? 俺なら喜んでもらうとに」
「………」
今度こそ声をなくした彼女を見つめて、笑って九州まで連れてくし、と千歳は一言。
眠る謙也を一度千歳の家において、ジュースを買いに三人で行ったコンビニ。
深夜だけあって、人気も少ないが、商品も少ない。
やはり、クリスマスだからか。
「千歳先輩て、部長を好きですよね」
千歳が飲み物を選んでいる隙に財前に言われて、お菓子を見繕っていた白石の手から箱が一個落ちた。
それを拾って、好きやろ、どう見ても、と重ねる。
「そう…なん?」
「余程のタラシやない限り、女の子に気ぃ持たせる言葉は使いません。
それもクリスマスに。
面倒ですやん」
「…そら、そうやけど」
「千歳先輩はどー見たかて、タラシやないし」
モテるんはモテるけど。
「…やけど、俺は元々部活仲間やし」
「部活仲間として好きならそのまま扱い変えませんよ。
態度変えて洒落にならんの部活仲間の方が余計や」
「………」
「嬉しい、…て。プレゼントが? 千歳先輩の、気持ちが?」
わからない。
「白石、光! もう行くたい」
「はい」
足を向ける財前を見遣って、でも足が動かない。
気付いた千歳が、近寄って手を取った。
そのまま白石の手を握って、外を歩き出す。
「…千歳。人が見る」
「別によかろ」
「…男同士にしか見えへん」
「そげんもんどうでもよか」
「…気持ち」
「悪くなか。…お前は女の子やろ」
そう言われてなお、反論出来なかった。
元々、最初から弱かった反論。
謙也の時は、あんなに強く言えたのに。
「俺が繋いでたかの。…嫌?」
ずるい。
そんな言い方されて、断れない。
こくりと頷いた白石の手を更に強く握って、千歳は歩き出す。
『嬉しい、て。プレゼントが?』
財前の声が木霊する。
嬉しいのは、プレゼント。
だけど、選んで探して、渡してくれた、千歳の気持ちが。
嬉しいのも、本当。
「…ちとせ」
「ん?」
「…おれ…の…」
「…?」
「と………き?」
「…え? 声、小さくて…」
「…」
なんでもない、と誤魔化した。
それでも、想像の中の彼は「好いとうよ」と笑うから。
自惚れでも、心臓が痛い。
たったそれだけで嬉しいのは、既に恋じゃないのか。
…謙也だって、好きなのに。
手を、繋ぐのは嫌いだ。
離したくなくなるから。
ずっと一緒にいて、と。
願ってしまう人が、私の手を握っているから。
千歳が囁くように言った。
大晦日、一緒にいて、と。
誕生日だから、と。
謙也とじゃなく、俺と。
けれど、その大晦日に彼は風邪を引いた。
傍の駅まで行った俺を、迎えたのは伝言を聞いた財前だった。
手を繋ぐのは、嫌いなんだ。
どちらかの手は、いつか離さなきゃいけないから。
→NEXT