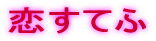
seasonⅡ-聖・バースディの夜に
第三話-【“愛してる”の記念日(バースディ)】
「今日は、無理やそうです」
財前の言葉に、胸に落ちたのは安堵かもしれなかった。
「…そか。…わかった。ありがと」
そう答えたのは、強がりじゃない。
安心、した。
今、まだどっちかを選ぶとか、出来ない。
都合がいい女だと思う。けれど、まだわからなかった。
なのに、もし千歳にはっきり「お前が好きだ」と言われたら、なにかが壊れる予感さえしたから。
行かずに済んで、安心したんだ。
「ほな、俺…」
「ああ、うん、ありがと」
手を振って電車に身をくぐらせた白石を見送って、財前は嘆息と共に一言。
「…味方すんのは、…ここまでやで。謙也くん」
その怜悧な線の瞳には、既に一人の少女しか映っていない。
かちかちという時計の音で目が覚めた。
薄暗い自分の部屋の天井が見えた。
(…てことは…)
白石は、来なかったのか。
「……」
やはり、謙也を優先したかったのか。単純に大晦日に男の家にくることの許可が家族から出なかっただけか。あるいは。
「…光が謙也に味方した…ってこつもあるか」
ただ、謎を持つならあの財前がいつまでも謙也の味方というポジションに甘んじるかだ。
謙也には頭の上がらない後輩というイメージが最初からあったから、他の人間が相手なら彼は謙也を優先するだろう。
だが、彼自身の気持ちが相手なら、謙也を味方しつづけるかが疑問だ。
白石のことを知った彼が、いつまでも白石を『理想の部長』と美化したままでいるか。
想像上の答えはノーだ。
男でも女でも、年上でも年下でも。
誰でも惹きつけ、虜にする魅力が白石にはある。
男としても充分にあるなら、女と知った場合どれほど普通の男の目に綺麗に見えるかを、自分が実体験したのだ。否定なんか出来ない。
それでも、今はもう会えない。
もう、時計は夜の十一時過ぎ。
今年は、もう彼女に会えない。
声、くらいは望んでいいだろうか。
そう思って、枕元の携帯を探した。
手探りで探す指にはなにも当たらず、しかたなく起きあがろうとした時指先に触れたのは、携帯の冷たい機体ではなく。
柔らかい、指の感触。
「…っ?」
飛び起きた千歳の視界に、触れるのは既視感さえ感じる、あの光景。
ベッドで眠る自分を待つように、ベッドに寄りかかって眠る、幼い彼女の寝顔だ。
「…しらい…し?」
おそるおそる呼びかける。信じたら消えそうで、それでも心臓が痛いほど高鳴る。
触れたら消えそうで、触れられなくて。
「……ん」
小さく唇から零れた声。
あの時と、同じ。
自分が彼女を、『女』と知った日と同じ。
ただ一つ、あの時と違うのは。
「……ちとせ?」
自分が、彼女を好きだという気持ち。
瞼を開けて、起きあがった白石が千歳と眼を合わせて、柔らかく微笑んだ。
「…」
小さい驚きの声の後、自分を呼ぶ、不思議そうな声。
堪えきれず身体を抱きしめた千歳の腕の中で、白石が身じろぐのを許さず、閉じこめる。
それ以上抵抗せず、彼女は具合悪いん?と聞いてきた。
それに、小さく笑う。普通、違うだろ。
自分を確実に好きとわかる、倍も大きい男が相手なんだ。
普通、抵抗するだろう。嫌だと邪な気持ちを想像して。
けれど、千歳の脳裏に蘇ったのは、あの日の彼女の信頼。
『千歳やもん』
「……謙也んとこ、おらんでよかの?」
やっとそう聞くと、少しその身体が強ばった。
「……そう、思うた」
「なら…」
「……けど………ここ、おりたかった」
「……」
唇がなにかを欲するように渇いた。なにを言うんだ。
期待、する。
「…まだ、謙也と…お前と…どっちが…なんてわからん。
…やから、ここに来たら…多分。
…なにか壊れるってわかっとった。このまま、三人でなんかおれんことだけははっきり。
……」
「………なら、どげんして」
「……せやからって……て思うんは卑怯なんか?」
腕の中の身体が、初めて自分を見上げて言う。
その顔が、赤いかどうか、暗くてわからない。
「……二人に好かれとるとか…自惚れるもええとこやし。他の女に殺される。どこの漫画のヒロインやって話や。
…せやけど…、俺は」
「…し」
その細い、髪が首を流れるのを追うように伸ばした指。
「…今のまんま行ったら謙也、選ぶ。
それはそれでええて思う。
でも、それは卑怯や思う。
…一回もお前の口から、俺のことどう思てんか聞いてへんで謙也を選ぶんなんか、卑怯や」
その指が、触れる前に震えて、そっと背中を抱いた。
「憶測やからお前をもっと知ることもできんまま、知ってるから楽な謙也のとこおるんは楽で…卑怯や。
俺は知りたいだけや。
お前とおった時、謙也と仲直りする前からずっとお前と一緒におって嬉しかったんは、ただ女の子扱いされて気持ちよかったんか、……お前やから嬉しかったんか」
「…。白石」
「…お前も卑怯やろ。
なんも言わんでわかってくれ、で…伝わらんから諦めるなんか…。
ふざけんなや。
気ぃ持たせるだけ持たせて、…遊びとか本気やないとか言うな。
遊びならあんなに優しい顔で笑うな…っ」
叫んだ身体を強引に引き寄せて、唇を寄せる。
キスされるとわかって一瞬暗闇でも明らかに怯えた瞳を見つめたまま、その身体をベッドに押し倒した。
その上から、小さく白石の上に落ちた笑いは苦笑でもからかいでもなく。
ただ、いつもそこにあった、優しい声。
「…て、襲われても、文句言えんシチュエーションと言葉」
「……とせ…?」
立ち上がると千歳は部屋の電気をつける。ぽかんとした顔でベッドに横たわらされていた白石が起きあがるのを待って、その額を軽くこづいた。
「俺も謙也もオオカミばい?
そげん台詞は、襲われる覚悟出来てないうちから言ったらいかんよ」
「……ごめん」
そのくせ素直に謝る姿に、千歳はくすくすと笑った。
怒ってへんの?という声に怒ってないと答えて。
「…まあ、理性がやばかったんは事実?」
「……」
「警戒せんでよか。自分の誕生日に好きな女を強姦したいわけなかよ」
言った瞬間、びっくりしたその顔を、見つめて微笑む。
確かに、卑怯なのはお互い様だ。
今、初めてキミに『好き』という言葉を使った。
「好いとうよ。白石。…お前を愛してる」
真っ直ぐ、誰かに思いを告げたのは、何度目だろう。
いや、きっと初めてだ。
ベッドに座ったままの顔は、すぐ真っ赤になって言葉を探しながら俯く。
「…よか。今すぐ、答えを求めて言うてなかよ」
笑って言ってやると、見上げた顔は赤いけれど、少し安心していた。
こたつの電気をいれて、向かいに座らせた白石を見遣って、それにしてもと思った。
たった一ヶ月でとんでもなく自分たちの関係は変わったものだ。
ただの元部長と部員の同級生と、かたや友人と言っていい同級生。
それが今は、初めて本気で惚れた女と、その恋敵。
…恋敵かもしれない予定なら、もう一人いるし。
「…あ、着てくれとーね?」
コートを脱いだ白石の身体を覆うのは、クリスマスに自分がプレゼントしたセーターだ。
「あ、うん」
「よかった。着たとこ、マフラーみたいにすぐ見れんけん。
やっぱ、似合っとう」
「……、ありがと」
本当に、すぐ赤くなる。本当に可愛い。
恥ずかしさに目をそらした彼女との会話を探したくてつけたテレビは、既に十二時のカウントダウン。
「あ」
白石が気付いてあげた声と、ブラウン管の中の音楽番組の司会者の「4」の声が重なる。
3…とカウントされる間に、なんとなく見た白石の顔も、こちらを向いて。
慌てた声が、自分に届く。
「千歳、十五歳、おめでと」
「…ん」
そう答えた声は、白石に届いただろうか。
「0!」
そうテレビが告げた瞬間、重なった視線のままお互い微笑んだ。
「「あけましておめでとう」」
先は未確定。
散る可能性も、充分ある。
けれど、とりあえず傍にいて、言葉を惜しまず伝えよう。
とりあえず、去年の誕生日は「好き」の記念日でもあるからとらしくないことを思う。
好きな奴が出来れば、らしくもなくなるさ、と橘が昔言っていたな。
雪はまだ降らない。
今はただ、その微笑みだけ見ていたかった。
→NEXT