Somebody,oh tell me
Defend me from enirely
Somebody,oh tell me
Baby,shout to me......
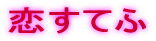
seasonⅢ-First Kiss
第三話-【騎士でなくなる瞬間・キミが抱く天秤】
金太郎は千歳の家に泊まることになった。
家に謙也が帰ると、従兄弟は居間で寝ていた。
「…はぁ」
自室に戻って、ベッドに腰掛ける。
金太郎に全部持って行かれた気分だ。
「…宿題の答えまで、金ちゃんに持ってかれたわ………」
そうだ。
白石を、誰のものだとか、騒いでるのは自分たちだ。
けれど、誰を好きになるかも、選ぶ権利も、白石のもので俺達が決めることじゃない。
それに、昔からよく「女なんてなに考えてるかわからん」と思っていた。
そういうことなんだ。
わからない、じゃない。
元々、考え方自体男と違う。わかるわけないんだ。同じ男の親友だって、なに考えてるかわからないのに、心の構造から多分違う女の気持ちを推し量れるわけがない。
「…金ちゃんて怖いわ」
ずっと大人だ。瞳なんかあんなにまだ大きい癖に。
『ワイ、白石、大好きや』
「……いやいや、金ちゃんはまだちっちゃい! 恋なんてまだ早いっちゅーの!」
必死に首を振っていたら、扉をノックされた。
「侑士?」
「俺! 開けて謙也兄」
弟の春霞だ。
「ええよー開いてるし」
かちゃ、と扉が開いて身長はまだ低い弟が入ってきた。
「どないしたん?」
お年玉の額が兄と比べて少ないとかいう毎年恒例の愚痴だろうか。
それは仕方ない。自分はもうすぐ高校生だが、弟の春霞はまだ中学一年で。
「……春霞」
「え?」
急に真顔になって立ち上がった兄に、春霞がびっくりして軽く身を退く。
「なに…?」
「お前、好きな女の子おる?」
「…え? なんで?」
「ええから」
「……おるけど…。兄ちゃん、変や」
「おるんか!? まだ一年やのに!」
「おるん普通やで? みんなおるもん」
「…………」
自分は確か、中一の頃なんて恋より食い気とテニスだった気がするが。
「…最近の子ってマセてんなぁ」
「兄ちゃんより二歳若いだけやんか…」
それもそうだが。
「? そういや、なに?」
「今、下に蔵ノ介姉ちゃん来とるん知らせて来い、てオカンが」
その瞬間、テレポートのように部屋から姿を消した兄を、弟は予測済みの顔で見送った。
「白石!?」
「……けんや?」
居間で、コートを脱いでいた白石がぎょっとして、走り込むように居間に入ってきた謙也を呼んだ。
居間には白石と、ソファで爆睡する従兄弟。そして母親。
「ど、どないしたん?」
「あ、と…謙也のお母さんが」
従兄弟を指さしてしー、と合図した白石につられて声のトーンを落としてから聞いたら、白石はそう言った。
「蔵ちゃん家、今日蔵ちゃん以外おらんのやって。
女の子一人で家にやなんて危ないやろ?
やから、今日は蔵ちゃん泊めるからな」
「え!?」
「謙也」
「…あ、…いや。……そら異論はないけど。
……危ないし」
「大袈裟やて…」
「金ちゃんが一人なんが危ないんに、白石の一人が危なくないわけないやろ」
「……まあ、ともかく」
「……あー、うん」
とにかく、妙な間が目立つ。
親も兄弟も白石が女の子と知っているが、今日も泊まる従兄弟は知らないのだ。
「ちゅーか、…白石、どこで寝るん?」
「あんたの部屋でええやろ。侑ちゃんと一緒の客間なんかアカンし」
「そら当たり前やけど……! ……俺の部屋…?」
急に声の減速した謙也に、白石は視線を逸らして困ったように口ごもった。
「ええやろ? どうせ蔵ちゃんあんたのお嫁さんにもらうし」
「いやいや! …いや欲しいけど…いや、そうやなくて白石の気持ちがな」
「……俺はええから。そない困らんでええし」
やっと落ち着いたように白石が苦笑する。
見ると、侑士は未だにいびきを立てていた。
思えば、白石は家が隣だし、よくこの部屋にも来ていた。
ただ、その当時は、自分は白石を男と思っていた。
今は、違う。
「白石、紅茶でええ?」
「うん。ありがと」
ベッドに腰掛けた白石にペットボトルの紅茶を渡す。
向かいの机の椅子に腰掛けた謙也を見て、すぐ視線を下に落としてから白石はペットボトルを開けて口を付けた。
琥珀色の飲み物をこくこくと飲む唇をなんとなく凝視してしまい、勝手に気まずくなって謙也も視線を逸らした。
「けど、ほんまにええん?」
「え?」
「…俺の部屋で…寝るん」
「………」
聞くと、白石は困ったように笑う。
千歳と同じように、言われるのだろうか。
『謙也やから大丈夫』と。信じて。
それは嬉しいけれど、複雑で。
でも、泣かせないと誓った。
今日。
「…謙也やから」
「…」
やっぱり。
「…て、…言うんは言い訳かもな」
「え?」
己を納得させるように目を伏せようとした謙也の耳に届いた声。
顔を上げた謙也に、白石はぎこちなく首を傾げた。
「『千歳やから』『謙也やから』て言うんは、俺の方のいいわけかも。
…手を出したらあかん、てお前らの理屈はそうやないかもしれんし。
そのうえで、信じたいのは俺の勝手」
「そないなことない!」
咄嗟に否定して立ち上がった。
「光の言うこと気にしてんやろ?
そんなことないて! 俺達が勝手にお前を一緒に好きになったんや。
…お前は悪ない」
「……謙也」
「……俺も、千歳も…、誓うたから」
「…?」
「お前を、泣かせたりせえへんて。
…やから、信じてくれるなら、ものっそう嬉しいて。
俺もあいつも」
「…」
微笑んで言うと、白石は逆に驚いたように、戸惑うように瞬きをする。
「たかがキス一つとか、言うたらおかしいわ。
女の子は大事なんやろ? 俺も千歳もそんくらいわかるし。
…お前がいややろうから怒らへん。
けど、……守ってやれんでごめんな」
傍の床に座って、見上げて言った。
白石はなんと言ったらいいかわからない顔で、見下ろして掠れた声が続く。
「…なんで?」
「約束」
指切りのように、小指を白石に見せた。
「したやろ? 俺は、お前の騎士やから」
「………」
声を失った白石は、なにかに堪えるように手を握って、堪えきれないと顔を歪めた。
その翡翠の瞳から涙が零れた。
きっと、あの日から泣くことすら出来なかったんだ。辛かったのに。
俺達のことばかり気にして。自分を置き去りにして。
「…お前を今抱きしめても、…金ちゃん怒らへんか?」
「……」
白石は涙を堪えることに一杯で肯定も否定もしなかった。
そのまま細い身体を抱きしめる。
嗚咽に震える背中を抱いて、天井を一度見上げる。
「…大丈夫や。…次は、もう。守るから。
お前が、誰を選んでも」
「……、……」
腕の中の掠れた声が言う。ずるい、と。
自分がずるい、と。
「…どっちも…好きやなんておかしい」
その声は、あまりにか細くて空耳かと疑った。
「白石?」
「…謙也も、千歳も同じくらい好きやなんて…変や」
「…おなじ…? 俺と、千歳?」
「軽蔑するやろ…。せやけど…ほんまおんなじなんやって今気付いた。
…まだどっちも選べへん。呆れてくれ…ほんま、…都合よすぎや」
「…するわけないやろ」
抱く腕を強くした。
世の中の誰が間違ってると言ったって、自分は嬉しかった。
彼女を、誠実だと思う。
黙っていればいいのに。黙って楽になればいいのに。
そうはなれずに、素直に伝える勇気を持っている。
だから、誰より綺麗で、愛しいんだ。
「…昔、…中二とかの時。
白石がようこの部屋来てたなって思ってたわ。
俺は忘れてて、意識してへんかった」
「…俺は、」
してた。と小さな声。
「いつ、…抱きしめてくれるんやろう…とか。大人になるまで待たないで…もうええからって。…思ってた」
「……」
声もなく驚いた謙也の腕の中で、顔を上げた瞳はまだ泣いている。
「して欲しいて…期待してたから…。やからお前が忘れてて…悲しかっ……」
ごめん、と言った声は、多分届かなかった。
彼女に届くより早く、濡れた頬に手を添えて、手首を掴んで、その柔らかい唇を塞いだ。
あの日、財前がしたように。
驚いて一瞬、強ばった手が、身体が。
それでも戸惑ったように揺れた瞳が、離さない意志を謙也から感じたように、瞼をそっと閉じた。
それに、身体中が激しい欲望に満たされるのをリアルに感じる。
欲しい。
自分のものにしたい。なって欲しい。
もう、この手にも、髪にも、顔にも、誰も触れないで。
腕の中に閉じこめて。離したくない。
その声も、唇も俺のものだと。
俺だけに笑って、と祈るように強く願った。
俺を好きになって。
大事にする。
一生、大事にする。
騎士ではもういられないけど。
一生、傍で愛して守るから。
その声で、俺だけが好きだと今すぐ言って。
俺だけに笑ってよ。
それを、今は願えない。
けれど、心の中では強く願う。
『誓う』
その日の誓いすら、俺は守れずに。
それでも、欲しかった。
どうしても、欲しかった。
→NEXT