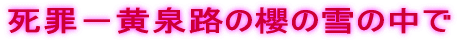
第一話−【それは、まるで罪のような】
「お前に殺されたい」
雪のように吹雪く桜の下、彼が微笑んで俺に愛を告げた。
千里、お前の好きなように生きなさい。
父は、九州を出るとき千歳にそう言った。
テニスのために育った九州も、家族も捨てるようにテニスを選んだ息子を責めず、彼は背中を押した。行ける場所があるのなら、生きなさいと。
父は、昔から千歳の決断を、決して責めない人だった。
「もう咲いとーとか…」
大阪に着いたその日、荷物の荷ほどきもせずぶらぶらと街を歩いていると、一際綺麗な桜並木を見つけた。
もう三月末だ。おかしくないが、その美しさがいっそ異常な程、綺麗な桜だった。
惹かれるように並木を歩いていると、やがて人一人いない小さな公園があった。
そこにも、桜の木があった。
風でキィと揺れるブランコの上に、ひらひらと散る花びら。
「………」
その桜は、むしろ神木と言える程綺麗だった。侵しがたい、桜そのままの色。
魅入られたように見上げ、眺めていた。その背中に声がかけられるまで、人の気配に千歳は気付かなかった。
「なぁ、そこのでっかいお前」
柔らかいテノールが耳に触れる。あの桜のように自分を引っ張って、振り向かせた声の先に立っていたのは、恐ろしい程美しい男。
翡翠の瞳と、銀灰色の髪。真っ白な肌の、整いすぎた美貌。
着ているジーンズとシャツが、酷く似合うようで、彼の美貌には安すぎる気さえした。
「俺と雪合戦してくれへん?」
微笑んだ唇に言われて、誘われるように頷こうとした。桜をずっと見ていて、夢心地だった所為だと思う。桜は、雪のようだったから。
「……?」
すぐ違和感に気付く。すぐそれはあからさまな異常として千歳の口を吐いた。
「今、…三月たいよ? どこに雪があっとね?」
自分はツッコミなんて絶対出来ないと思っていたが、このときばっかりは出来るかもしれないと思った。眼前の男は、目をびっくりしたように瞬きした後、茫然と。
「あれ…キミ。…ここの人やない? 大阪やない…よなその言葉…」
「俺ぁ九州っから今日来たばっかたい」
「……」
男は絶句すると、勢いよく斜め後ろの塀を振り返って叫んだ。
「おい! この人大阪の人ちゃうやんか! 一応丁寧につっこんでくれたけどアカンやろ九州の人にツッコミ無理矢理させて! 誰やこの人に行ってこい言うたん!」
誰かいるのか、もの凄く焦って怒鳴る彼の前の塀から数人の男の顔が現れた。
塀をよじ登った数人の少年たちが『悪い』と口にしたかどうか千歳が聞き取る前にまたその銀灰色の髪の男が叫ぶ。
「とにかく俺はやったからな罰ゲーム! これで無しやで!」
わかったごめんなそこの人ーという少年たちの声を背中に振り返った男が、目の前でぱんと手を合わせて頭を下げた。
「すまん! 学校の友達との罰ゲームやねん! 桜の下におる誰か捕まえて雪合戦にナンパしてこいっちゅーしょうもない…。
…付き合わせてごめんな」
気恥ずかしそうに謝ると、幼く見える美貌に、すっかり気がそがれた。元々怒ってもいなかったが。
「ああ、…よか。学校の罰ゲームってもんは大概はた迷惑たい。
俺もダチにえらい罰ゲームやらされたことあっと」
「そか。よかった…。…え、どんな?」
「いや、…教室の前の廊下を通る移動教室の下級生の女の子をお茶に誘え…って。
俺に声かけられた子…涙浮かべとったけんね」
「…そら…大変やったな。すまん聞いてしもて」
「いや、よか。あんたの気持ちはようわかっと」
「…そか、助かる。あ、…」
急に気まずそうにした彼に、おかしがったことを気付いたのだろう。彼が遠慮がちに。
「えと、あなたは…って言った方がええですよね?」
「…あー…お前さん、幾つ?」
「俺は中学三年や。四月から。そこの―――――――――――――」
彼の指が塀の向こうを指す。そちらにも、桜並木が見える。
「向こうの四天宝寺って学校の生徒」
「ああ。俺、四月からそこに通うたい。だけん敬語ばいらん」
「………」
多少予想はしたが彼も固まった。やはり自分は既に成人に見られてしまう。
「お前、中学生!?」
「そうたい。そう見えなくてすまんね」
少し棘を含んで言ったが、彼は気にせずおかしそうに笑った。
「そっか。なら同級生やんな! ごめんごめん。
…三年やんな? まさか二…」
「三年たい」
「やんな。よかった」
失礼な。
「なら、新学期に会おうや。運良くクラス一緒になるかもしれんし」
「ああ、そうたいね。あ、でも俺…」
明日からテニス部に顔出しに行く、と言う前に塀の向こうから誰かが彼を呼んだ。
「ああ、今行く! ほなごめんな。また新学期!」
「ああ…。あ、俺千歳千里言うたい! あんたは?」
走り出した彼の背中に叫ぶ。
聞こえなかったのか彼は振り返らなかったが、その代わり公園の出口でぴたりと立ち止まった。
「ああ、そか。なら、明日また会おうや。
俺、四天宝寺テニス部部長の白石蔵ノ介! キミやろ?
獅子楽の千歳くん!」
声と共に手が振られる。そのまま走り去った彼――――――白石の背中を見送って、千歳は手の平に落ちてきた桜が指をすり抜けた感触にふと思った。
まるで今の桜の花弁のように、すり抜けて行ったような男だった。
なんて、柄ではないけれど。
(白石、蔵ノ介…)
雪のような桜の下、彼に出会ったのは、紛れもない春だった。
翌日、部室の前に立って、扉を叩こうとした手が止まった。
(あの…『白石』がおる…とね?)
出会いが強烈過ぎて、彼が普通に部長をやっている姿が全く想像出来なかった。
ジャージ姿の彼がいると思うと、やたら緊張した。
息を吸って叩こうと手を振った瞬間。
ゴン
先に内側から開いた扉は、当然千歳の額を強打した。
「〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!!」
額を押さえてしゃがみ込み、あまりの激痛に呻く千歳のぼやけた視界に誰かのテニスシューズが見えた。
「あれ、千歳くん? うわ今頭打ったん!? ゴンってお前か!?」
(この声!)
思わず上げた顔。痛みに歪んだ視界でも心配そうに見下ろす白石の顔がわかった。
「うわごめんな! 痛かったやろ? …赤なっとる?」
心配そうに屈んだ白石が、額を押さえる千歳の手を退けて、自分の手で額を撫でる。
「ホンマに赤なっとる…痛いか?」
触れる熱い、けれど白い手。至近距離の睫の長さすらわかる顔。
「……っ」
なんだか堪えられなくなって立ち上がった千歳を、白石はぽかんと見上げた。
「あ、いや、…大丈夫たい。そげん痛くなか」
「そか…? ならええけど…一応冷やしとけな?」
「…うん」
頷きながらつい顔を背けた。別の意味で今、顔が赤い気がする。
「ああ、昨日ホンマごめんな。遠路遙々来て早々あんなツッコミ付き合わせて」
「もうよか。別に怒ってなかよ」
「そか。おおきに。
うちのジャージまだないか。なんか自分で持ってきたか?」
「ああ」
「なら着替えて。部室もう使ってええよ。ロッカーはもう用意しといた。
名前あるからそれ見てや」
「…ああ」
「……?」
じっと自分を見る千歳に、流石に気付いた白石が怪訝な顔で見上げてくる。
「…いや、…ファーストコンタクトがあげんだったけん、部長さんがどげん顔でどげん部長やっとーか想像つかんかった。やけん、普通に普通に普通の部長さんたいね」
「お前も失礼やな。まあファーストコンタクトがおかしかったんは否定せんけど」
「お互い様たい。部長さんも初対面、俺を年上と間違えとうよ」
「お前は仕方ない。……って、部長さんはないんやない? 部長やけど、同い年やん」
「……あ、…あー…“白石”?」
「そやな。みんなそや」
微笑んで頷いた白石が、ほなコート行くわと足を返す。
「俺んことも“千歳”でよかよ!」
「わかった!」
まだ散らない桜並木がコートの向こうにある。
普通に日の下で見ると綺麗だけど、ちゃんとした男だと思う。
けれど、彼の背後で花弁がちらつく度、矢張りとても美しく見えた。
「白石は自主練しとるから誰とも一緒に帰らんで?」
そう言ったのは忍足謙也だった。
四月の入学式も過ぎ、桜も散る頃、部活帰りはたこ焼きだお好み焼きだで一緒に帰る部員たちの中、いつも一人それを断る白石のことを聞いた。
「ちゅーか、誰もあいつん家しらんしな」
オサムちゃんもしらんらしい、と顧問の名も出して言ったのは副部長の小石川。
「あと、誰もあの人の家族とか会ったことないですね。家に遊びに行かないから」
案外一人暮らしやったりして、と二年レギュラーの財前。
「昔の写真はおろか昔話すら聞いたことないわ。中学あがる前、小学校どこやったとか、そういう話も一切せんの。誰もあいつの過去しらんな」
昔テニスの大会出たことあるんかとかもしらん、と顧問の渡邊。
流石に異質に感じたのは、教師であり、白石の組の担任である渡邊すら白石の出身小学校を知らないことだった。他の先生は?と聞くと彼は無言で首を横に振った。
己でもやりすぎだと思う。まだ会って一ヶ月そこらだ。
けれど知る程謎が増える彼の輪郭に、気付けば囚われていた。
「……、別に」
夜道を歩く足が不意に止まって、背後を振り返った。
「尾行とかせんでも、ウチ来たいなら連れてったるで?」
「気ぃついとったとか」
数メートル離れた角から出てきた千歳に、甘くみるなと白石は笑った。
「けど、別におもろいもんないで?」
「気になっとう。みんなお前んこと、しらんしらんばっかたい」
「そんなに謎かいな俺」
「俺みたくわかっとらんけん、近くても気になるんやろ」
「それもそうや」
けらけらと笑った白石が、簡単に案内するのも不思議だったが、甘えたかった。
知りたかった。この気持ちを、俺はもう知っていた。
もっと歩くと思ったが、白石が立ち止まったのは四十分ほど学校から離れた民家の並ぶ道の途中だ。
「ここや」
指の方を見遣ると、周囲の小さいがそれなりに新しい民家とは明らかに違う、古い山奥の、屋敷と言った方がしっくりくる木の家があった。
木の門を開けると、白石が入れと促す。
中に入って少し歩くと、もっと驚かされた。
大阪市内には珍しい広い庭。屋敷は奥まで続いていて、縁側の廊下が手を付くとぎしりと軋んだ。
「俺、着替えてくるからそこおるなり好きにしてや」
白石はそう言って家に引っ込んだ。
それにしても。
「…相当…時代錯誤過ぎたい」
古すぎる。縁側で周囲を見渡すと見えるものは、ここが戦前の時代かと錯覚するような風景ばかりだ。
そういえば家族はいないのだろうか。挨拶すべきじゃないのか?
そう考えながら立ち上がる。下駄を鳴らして、家の裏手へと進むと、その視界を花弁が横切った。
(…まぼろし?)
いや、違う。現実だ。
裏の庭には、未だに鮮やかに咲く、大きな一本の桜があった。
あの公園の桜のように、恐ろしい程美しいそれは、神聖であり、同時に恐ろしい。
花弁が、物語の死体の埋まった桜のように鮮やか過ぎる。
「…見ほれたん? 驚いたん? どっちや?」
背後で声が笑い混じりに響いた。
「しら…」
振り返って、千歳は更に驚いた。白石の小さな下駄を履いた足は当然素足で、白い足が膝まで見えた。
その身体を覆うのは、一枚の死に装束に見紛う着物だけだ。
「…白石?」
「ん? ああ、この格好?
俺、家ではずっとこういうんや。そら多少みんなで外出するように私服持っとるけど、他はみんな着物。親父たちがくれたんみんな着物やから」
開いた胸元から覗く白い肌と、歩くたび開いて足が見える裾。
どちらかといえば洋風な顔立ちの彼のその姿は、いっそ禁忌を犯していると思う程美しかった。
「…家族、は」
「ここにはおらん。ここは俺一人で住んどる。
親父たちは生まれたとこにおるわ」
「…生まれはここじゃなかと?」
「………そやな」
白石はそう曖昧に笑って、それ以上は語らなかった。
「…この桜すごいやろ」
「…ああ」
「俺がここに来た時から、ずっと咲いとる。一年中。
…会った公園の桜もや」
「……」
「七不思議みたいやろ」
なんと答えたらいいかわからない千歳に、白石はにこりと笑った。
彼の手が木の幹に触れて、頬を寄せるように木に寄った白石の髪に花弁が落ちる。
思わずそれを手で取った千歳を、白石は夢から覚めるように瞳を開けて見上げた。
それがあまりに、現実離れしていて、幻のようで、綺麗で。
だからなんて理由にならないのに。
熱を持った自分の手が白石の肩を掴んで、見上げるその唇にそっと自分のそれを重ねた。
ほんの少し強ばった身体は、驚く程薄く、冷たい。
離れた瞬間、翡翠の瞳が自分を見上げるのを見て、千歳は我に返ったように手を離した。
「…ごめん」
「…なんで謝るん?」
「なんで…て」
白石は笑っていた。
「…白石は、なんで怒らんね」
「…時と場合によるし」
「…これは、“よらない”と?」
心臓が勝手に期待して聞いた言葉を、白石は微笑で答えた。
「……」
声が出ない。それでも視線は、白石から離せない。
透き通るような髪も肌も、侵しがたいと思うのに。
「……千歳」
微笑んだまま、白石が呼んだ。
桜の方を向いて、顔だけ千歳に向けて笑う。
「……お前…気付いとるん?」
「…?」
問われても意味が分からない。ただ白石を見た千歳を首を傾げるように彼はおかしがった。
「……お前ずっと、…そういう目で、俺、見る」
「……そういう、…目?」
「そう」
白石は風に煽られて舞った桜を受け止めるように手を伸ばして言う。
「ものっそう…物欲しそうな目…」
心自体が心臓のように鳴った気がしたのは、それが理解できたからだ。
「……ずっと、そういう目で、…俺だけを見とる…」
手の平に捕まえた花弁を持ったまま、白石は裾をさばいて千歳に近寄る。
「俺の身体…服剥いで、手を這わせて、肌に赤い痕つけて、暴いて、貫いて、…中にハイりたい…って顔」
その手が、そっと千歳の顎から首筋を辿った。
「…ちゃう?」
ごくりと、のどが鳴る。
「……いつから、気ぃついとったと」
「…最初から言うたら、怒るか?」
「…いや。……俺にも、わからなか」
首筋で止まった、細い手を掴むと、簡単に手首が収まった。
「…これが恋愛の好きか、…劣情なんか…、欲なんか…、…わからなか。
ただ…お前が…」
「欲しい…?」
「……ああ」
白石は微笑むだけで、千歳から逃げようとも怯えようともしない。
「…だけん、それはいかん」
「なんで?」
「…なしてって…白石は俺んこつ…」
自分が掴んだままの手首が引かれた。口でそう言っても離したくなく、そのまま彼の手の動きにあわせてその顔に近づいた千歳の指を、白石はチロリと唇から覗かせた舌で舐めた。
「…しら」
「……ええよ。ちとせ……」
掴まれた右手をそのままに、白石の左手が千歳の頬を撫でて髪を指が掴む。
見上げる顔が、酷く綺麗に笑う。
「………して…………」
麻薬や媚薬のように耳に届いた甘く掠れた声に、正常な思考は飲み込まれた。
そのまま地面に押し倒した身体が、浅黒い手に脱がされる着物から露わになる。
彼の右手に握られたままの花弁が、はらりと地面に落ちる。
初めて抱いたのは、彼の家の、狂い咲きの桜の庭だった。
→NEXT