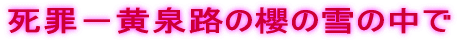
第二話−【桜はキミの涙だから】
桜が背中を押してくれた―――――――そう言った俺を、彼は「それ罰ゲームか?」と笑った。今は夏や、と言う言葉は理解していた。
「………ちとせ」
掠れて己を呼ぶ薄い身体を、押し倒して何度犯しただろう。
夏が来て、既に千歳は百では足りない数、彼を抱いていた。
大抵が、白石の彼以外いない屋敷の縁側や、彼の部屋、酷い時は庭だった。
白石は決して拒まなかった。どんなに練習がきつくても、何度求めても。
「……あ…っ」
零れた嬌声を絡め取るように唇を塞ぎ、舌を絡める。
伸ばされた首にすがる手に引っかかった白い着物が、木の床を這った。
情事の後大抵意識を失う彼を風呂に入れて、湯船の中で抱えて濡れた髪を撫でた。
意識のない裸体は千歳の腕の中に完全に収まって、また求めそうになるのを無言で堪える。
白石の家の風呂は広く、しかし矢張り古かった。
今日は風が強いのか、屋根ががたがたと軋んだ。
「…こげん家に一人で夜とか…怖くなかか…?」
ぽつり呟いた。独り言だった。
「……別に」
だから、腕の中の身体が答えたことに驚いた。
白石は柔らかく微笑むと、さっき気付いたと言った。
「…怖くないで? そういう歳やない」
「…ばってん、…」
「……そやな。……嵐は、怖い」
白石の白い手がちゃぷ、と湯船のお湯をすくった。
「………なぁ」
「ん?」
「…終わったな……」
それを、わからない筈なかった。
きつく抱きしめると、千歳の胸に触れた手にすがるように力がこもる。
「………ごめん」
「…千歳の所為やない」
「…俺は負けた」
「責めたいわけやない…」
全国大会が終わったのは、三日前だ。
自分たちの夏は、途中で終わってしまった。
「………でも、最期やった」
俯いた彼の顔は見えない。けれどその慟哭すら滲んだ声に、手を掴んでいた。
「顔、見せて白石」
「…嫌や」
「…見せて」
首を左右に振られる。すぐ両手で頬を挟んで上向かせた。
「…………頼む」
瞳から止めどなく流れるのは、間違いなく涙だ。
翡翠が、絶望しきったように歪む。
「…見んな…」
「……嫌たい」
額をそっと重ねて、涙が伝った唇を指で撫でて、塩の味のするそれを舐め、唇を重ねた。
手が湯の中の彼の秘所を探し当てて、指を突き入れるとびくんと震えた身体は、それでも求めるように千歳にすがった。
「……桜は…、人を生け贄にして咲くんやて…。どう思う?」
出会った日の公園。ある日の夜、白石は千歳にそう言った。
彼が座ってこぐ、ブランコがキィと軋む。
「それは、物語の話たいよ?」
「……そうやな、普通は」
「…?」
不思議そうに見下ろす千歳を、白石は笑ってなんでもないと言った。
「……やけど、…その“人”はどこにいくんやろう…」
なんでもないと言いながら、話を続け、彼は遠くを見た。
千歳の肩の向こう。遠く。
「…身体は腐って栄養になって…骨だけ残って…誰にも…永遠に気付かれず」
「…白石」
「……こころは?」
「……しら…?」
「…こころは…あの世…? 天国…? 地獄…? …それともこの世界で…幽霊になる…? ……誰の、手も届かんとこに…独りぼっち…ずっと…」
「……白石…?」
いぶかしがった千歳がブランコの手すりを掴む。
今更気付いたように見上げた翡翠の瞳に、気付けば涙の膜が張っている。
「……、泣きたか時は、言えばよかよ」
「……言えん。お前が、ずっと…傍おるなら…言うかもしれん…でも」
がしゃんとブランコが軋んで揺れた。
きつく抱きしめた瞬間、白石の身体がブランコから落ちて、手すりを掴んだまま地面に足がつく。
「…おるよ。ずっと。傍に」
「……無理や」
「無理やなか」
「…………千歳」
見上げる顔が、千歳が頬を撫でるとすぐ膜が剥がれて涙に濡れた。
唇を頬に、額に、瞼に落として、最後に唇を塞ぐ。
キスの合間に、白石は酷く悲しい声で言う。
「…千歳………独りになりたない……」
夏が過ぎて、彼のそんな声を聞くのは、どんどん増えていった。
なにが怖いのか、悲しいのか、話してくれない。
それでも、傍にいた。
「…独りになんて…俺がせん」
いたかった。
ある、晴れた日だった。
ぼんやりと寝転がった屋上からは、抜けるような青空しか見えない。
白石が泣く理由がわからない。
「……独りにせん…て…」
ここからは、桜なんて見えない。今は、夏。
「…誓って欲しいなら、何回だって誓うとに…」
(…そげんもんが、白石の欲しいもんかも…わからん)
答えすら持っていない。彼の欲しい、答えすら。
その時がちゃんと屋上の扉が開く音がした。
千歳は給水塔の傍にいたので、入ってきた生徒からは見えなかった。
「…」
白石だ。傍に、見知らぬ生徒。いや、知っている。テニス部の。
「で、用件ってなんや?」
手すりまで歩いた白石が振り返って聞くのを、その男は一瞬口ごもって見る。
千歳はそれで、男の意図がすぐ理解出来た。
告白、だ。
実際、白石は男にもよくモテた。
「俺、…部長が好きなんや」
「…俺、もう部長やないよ?」
「……」
全く違う方向、「はい」でも「いいえ」でもない言葉を返された男が言葉を探して俯いた。面白くないが、興味はさしてなかった。
自惚れていた。白石はもう、自分のモノなのだから、と。
「…………、なぁ」
微笑んで言った白石が、不意に男に近寄った。
その白い手が男の肩を撫でる。
「ぶちょ…?」
「…黙って」
囁くように言った白石が男の首に手を回して、自らキスをした。
「……ええよ?」
キスの後で掠れたテノールが笑う。
「…俺が欲しいなら…求めてくれるんなら…、…お前のもんにして、…ええよ?」
思考が、止まった後浮かんだのは、制御出来ない怒りに似た衝動と、暗い独占欲。
「部長…!」
その声に煽られて白石を抱きしめた男の唇が白石に触れる前に、その肩を掴んで引き剥がした。
千歳が突然現れたことに、驚いたのは白石も同じ様子だった。
驚く白石を見下ろす千歳の顔は、我ながら必死だろうと、思えて。
俺は違うのか。俺もそいつと同じなのか。求める男なら誰でもいいのか。
言葉が渦巻くのに、声にならない。
ただ怒りに顔を歪めた千歳の視界を、不意に白いなにかがよぎった。
ふわりと空から散る花びら。
(…さくら…)
すぐ、心は決まっていた。
白石の手を掴んで、強引に引っ張ると屋上から連れ出した。
廊下を歩いて、階段を下りて、すぐ見えた昇降口をくぐって学校から引きずり出す。
白石は全く抵抗せず、ついてきた。
「……邪魔?」
それでも、歩きながら彼はそう言った。
「桜が、背中押してくれた…」
「なんかの罰ゲームか? 今は夏や」
振り返らず、歩く千歳の背中に白石の笑い声が聞こえる。
「あれは、お前ん家の桜の花たい。お前を止めてくれって言った!」
「それこそなんのお告げや。お前、頭おかしいん?」
「白石が泣いとうって思った」
足を止めて、手を握ったまま言った声は、酷く悲しい気持ちで言ったのに、声は静かに世界に出てしまった。
「…泣いとらん」
「嘘たい。…桜は」
振り返って、不思議そうに自分を見上げる白石の手の甲に口付けて言う。
「…桜は、白石の涙やろ…?」
気付けば、視界を横切る沢山の桜の花弁。
そこは、いつの間にかあの公園だった。
あの狂い咲きの桜の花弁が、落ちてくる。
「……そんなセンチなこと言ったかて、本音ちゃうやろ?」
一度だけ驚いたようにも、泣きそうにも見えた白石は微笑んだ。
「…俺を所有した気になっとったから、…浮気された、て怒ったんやろ」
違う?という言葉を否定する気はなかった。
「…白石は、違ったと?」
「…俺は、俺を欲しがるヤツなら誰でもええ。お前も、あいつも」
「嘘たい」
「どこにそんな証拠があるん?
俺、お前に一回でも「好き」言うたか? 言ってへんやろ」
「…それでも、嘘たい。白石は俺を」
「お前なんかいらん」
間髪入れず言われて心臓が痛んだのは、彼の顔が本気だったからだ。
「…それ以上言うて、俺をかき乱すなら…お前なんかいらん」
もう、堪えられなかった。衝動のままに抱きしめて、顎を掴んで口付ける。
ここが町中だということすら忘れていた。
頭がしびれる程深く貪った時、感じた痛みに思わずその身体を引き離していた。
血が口から零れる。白石の唇からも一筋、赤い雫が落ちた。
「…わかったやろ?」
笑う顔を、信じたくない。差し入れた舌を、いっそ噛みきる程強く噛まれたなんて。
決して、拒まなかったのに。
「…お前は、ただの遊びや」
ぐいと唇の血を拭った白石が傍を通り過ぎて歩いていくのを、追える筈がなかった。
「またねー!」
ふと聞こえた少女の声に、意識が現実に戻った。
今、何時だろう。帰らないまま、あの公園にずっといたらしい。
空はもう、真っ暗だ。今は夏だから、相当遅い時間だ。
「……遊び」
呟いた言葉すら、空しくて痛いと千歳は思った。
思いが、通じていると信じていた。
好きと言われてないことなんて、どうでもよかった。
全て嘘なら、何故泣くんだ。
(泣かんでくれ…)
視界を横切る、狂い咲きの桜。
(それなら…泣かんでくれ)
桜は彼の、涙だから、散らないでくれ。
「………さくら?」
けれど気付いたように言葉にしていた。
何度も何度も、白石は自分にすがって泣いた。
心から絶望して、悲しんで、泣いていた。
独りになりたくない、と。最期だった、と。
あの涙も、嘘?
あの、あんなに散るように綺麗で悲しい涙が?
「……」
すぐ立ち上がって、走り出した。下駄の音は、耳につかなかった。
桜が散るから。
今も、視界を横切る、幻の桜。
桜は、―――――――――――――彼が泣くから散る、彼の涙。
何度も来た白石の家の門をくぐる。
足早に、玄関でもなく、縁側を通り過ぎ、あの裏手に向かった。
白石が泣くなら、桜の傍だ。
ざあっ、と風で散った現実の桜が千歳の傍まで舞う。
桜の木の下に、白い着物姿でしゃがみ込んでいた細い身体が驚いたように顔を上げる。
その顔は、嘆きと涙に濡れていた。
「……せ…?」
「…やっぱり、…泣いとった」
駆け寄ると、立ち上がらないまま、白石は何故と千歳を見た。
「言ったとだろ?」
「…?」
「桜は、…白石の涙やから」
桜が散るから、お前が泣いてるって思った。そう言うと、彼が嗚咽を殺すように唇を引き結んだ。それでも堪えられず、涙がぽろぽろと流れる。
傍にしゃがんで、その濡れた頬を両手で包んだ。
「確かに、好きとは言われてなか。遊びかもしれなか。俺も、あいつと同じかもしれなか」
「…なら」
「…やけん、…俺の前で、お前が泣いた…。それだけは本当たい」
「……」
「お前が、俺の前であんなに悲しんでた。俺が見た涙は…本当やから。
…だから…そいでよか。
…お前にとっての、ただの泣き場所でよか。
…傍に、いさせてくれ」
頬を包む手の上を、幾筋も雫が流れる。
殺しきれなかった嗚咽が、とうとう零れた。
「…っあ……っとせ…!」
全身ですがりついてきた細い身体を抱きしめる。ただ、きつく、強く。
「…千歳……俺、…独りになりたない…」
「俺が、せん」
「…死にたない…っ」
「…死なせなかよ…」
「……千歳」
泣き声に呼ばれて顔を覗き込むと、涙に濡れながら、微笑んだ白石が言う。
「お前に殺されたい」
「……白石? …矛盾、しとうよ?」
「…独りになりたない。独りで死にたない。
どうしても死ななあかんなら……お前に殺されるんがええ」
「……なんで、白石が死ぬと?」
「………俺は、十五になったら、死ななあかん子供やから」
九州より更に奥の山の狭間。
そこに――――――――――千里堂という、隠れ里がある。
白石はそう言った。
「…俺はそこで生まれた。そこは、テレビも電話もない、…小さな里やった」
縁側に座って、自分を抱きしめる千歳の手を、白石は離さなかった。
「親父も家族も…そこにおる。みんなそこで生まれた。外から、来る奴はおらん。
里から、出るヤツもおらん。
…閉じた里やったから」
「…それ」
「うん。子供は…やがて近親で生むようになっとった。
それでも、異常を持って生まれる子はおらんかった。
作物は冬でも実る。水は綺麗なわき水で、枯れることはない。
雪で埋もれることもない。桜が一年中咲く、綺麗な、…異常なほど、神に守られた里」
「…神に」
「やけど…、里には、外の世界ではとっくに廃れた因習が今でも生きてた。
それがあるから、その異常な恵みがあるってみんな信じとった。
因習を止めようとした時、里は多くが死にかけた。やからみんな信じた。
生きるために、…その因習を今でも守っとる」
「……」
「…生け贄を神様に、…人柱として捧げるっちゅーやつや」
「……人殺し、…」
「そうやな。生け贄は死ぬから、人殺しや。やけどあの里では儀式で片づく。
誰もおかしいなんて言わん。思わん。
儀式は十五年毎で、前の儀式の年に生まれた子の中で、印を持って生まれてきた子が次の生け贄んなる。前の儀式は十五年前」
「次の儀式は今年。―――――――――――俺が、その生け贄」
白石の目が、遠くの桜を見た。
「生け贄の誕生日が、儀式の日や。俺の、誕生日も近い。
死にたくなくて、里を出た。…やけど、俺みたく逃げたヤツもみんな、結局死んだって知った。…こっち来たばっかの頃はなんとかなる思っとった。
やけど、三年なって…時間のうなって。最期の大会に負けて。
…怖くなった。死にたくないて……思った。やけど、…逃げられんことを、助からんことを、俺はどっかでわかっとる」
頬に手を当てて自分の方を向かせると、白石はごめんなと小さく言った。
「それなんに…お前、巻き込んだ」
「…そげんこつどうでもよか…!
…ほんに、逃げられなか?
こげん遠くなら…!」
「…印がある」
見つかるんや。
白石が片手の包帯を解いた。
下から現れたのは、大きな桜の花弁の形の痣とその周囲を這う血管のような筋。
「今年入ってどんどん…広がっとるんや。最初は花弁の痣だけやった。
…見るたび思う。逃げられん…て」
「…そげんわけ…っ」
「……それでも俺は…」
抱きしめられたままの白石が、千歳の背中に手を回して、肩に頭を乗せる。
「お前の傍で生きたい…そう一瞬でも願ったんや」
やから、お前に殺されたい。お前の傍で、ずっと生きられるように。
生まれ変わったら、お前の傍にいられるように。
桜やない、証がお前から欲しかった。
それは、間違いなく、愛の言葉だった。
好きより深く。愛してるより残酷で。
愛しいより、ずっと深くて暗い、とてもひたむきな愛情。
もう、好きなんて言葉はいらなかった。
なにより罪深い愛を、俺は告げられたから。
空で不意に音が鳴った。
「……花火」
まだやるところがあったのかと驚く。
空に散る、大輪の華。
「白石」
「え…?」
手を引いて立ち上がる。
「行こう。二人で」
「…え、いや俺…格好…!」
目立つと焦る白石の手を離さないよう掴んで走り出す。
道路で鳴る、二つの下駄の音。
走って、手が離れていないことを何度も確かめて、海の見える堤防を通った時振り返った顔は、足痛いと言って、確かに楽しそうに笑っていた。
「…ちとせ?」
空で咲く花が、頬を照らす。
「…約束する」
「…え?」
掴んだままの手を引き寄せて、口付けた。
「ほんに…死ぬしか道がなかなら…約束する」
「…………」
「俺が」
「お前を殺すから」
誓う、と言う。告げると、白石は信じられないように瞬きして、すぐ泣きそうに微笑んだ。
「…やけん、諦めんで。…最後までは。生きたいって願って欲しか。
…俺の傍に、おって欲しい」
「……っ」
白い着物の裾が風を含んではためく。駆け寄った白石が、千歳の胸に飛び込んだ。
手を掴んで、頬に手を添えて、顔を見て、唇を重ねた。
「……千歳」
白石の頬を、また涙が流れた。
「……嬉しい…」
空を、幻の桜が、また散った。
→NEXT