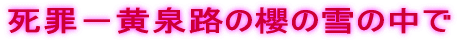
第三話−【運命の時は訪れた】
「…いつ…?」
野菜を切る手を止めて、千歳が不意に聞いた。ここは白石の家だ。
泊まる回数があの日以降増えた。
「え?」
「白石のほんの誕生日…、…九月二十日じゃ、なかね?」
「…九月二十日や。まだ」
「…もっと、早いんじゃなか? …今月じゃ、なかね………」
白石の唇が、声を出そうとして、出さずに閉じた。
「…今月たいね…?」
「……」
促すように手首をきつく掴むと、泣きそうに揺らいでいた顔が千歳を見上げて、寂しそうに微笑む。
「…うん」
「いつ」
「…二十九」
「……あと、一週間もなか」
「…うん」
「…ほんなこつ、手段、なか?」
「…」
白石が俯いて、首を左右に振る。さらりと髪が首を撫でて、露わになる。
「…みんな、…どこ逃げても…結局」
「…そか」
「…」
「…白石、」
落ちるのは、外の雨音だけ。
「…あれに、嘘なかね?」
「…。」
肩を抱き込んだ千歳の腕が白石を引き寄せた。空いた手が包丁を掴み、千歳の胸元に固定された白石の首筋に当てられる。
「…俺に、殺されたか、って…言葉」
翡翠の瞳が、静かに千歳を見上げた後、ゆっくり閉じられる。
降ろされたまま、抵抗を示さない両手。
「……うん…」
「……」
「殺して…ちとせ」
包丁が首から離れて、胸元に向けられる。胸を覆う着物の隙間を狙って降ろされた切っ先は、白石の背後の柱に突き立てられた。
「……ち…とせ?」
「……白石は、やっぱり甘か」
「…ち」
「……俺は……、…白石を独りにせん」
見開かれた白石の目が、困ったように揺れる。だからってどうしようもない、と。
「……白石、俺は、あの世を信じとる方たい」
「…あるから、俺は独りにならんて?」
「そうやなか。……死んでも、一緒…って信じとう」
「……」
先ほどより大きく見開かれた白石の瞳から逸らされない黒い目が微笑んでいる。
「…白石がもし、独りで死んだら…、そうならず済んでも…俺が殺すことになった時は…」
「俺は白石を追うよ」
「…白石の傍行って、そこで自分で俺も死ぬ。黄泉を追っていく。
だけん…白石を、独りにせん」
あの夜以上に無惨な悲しみに打たれたように、涙を溢れさせた瞳を閉じて、白石はその場に崩れ落ちた。
「……ない」
「…ん?」
「…わけ…ない」
千歳の手が白石の片手を掴んで、軽く引っ張った。
こっちを見ろ、と。
「……お前を…連れて逝けるわけないやろ…!」
上げられない顔から落ちた涙が、床に染みて跡を作る。
「……ばってん、先死ぬんはどう考えてもお前たい。
やけん、白石に、俺の自殺、止める力はなか」
「…やめてくれ」
「嫌たい。嫌なら、白石が死ななければよか」
「………それも無理やって言った」
「二十九日の夜が明ける前から、言うことじゃなか」
「…無理なんやってわかってくれ!!」
「嫌たい。俺は、白石の傍に逝く」
「………っ」
涙に濡れた顔がようやく千歳を見上げる。何故と、責めるように。痛いと、助けにすがるように。見上げる顔が、それでも愛しい。
「………っ……ぁ……。あ……っ」
最早言葉にならない程、嗚咽に詰まる身体を抱きしめた。
嫌だと全身で嘆く癖に、彼は俺にすがりついた。
離れたくないと。同時に一緒になんか来るな、と。
願う彼は、なんて我が儘で、傲慢なんだろう。
なんて、寂しくて悲しくて、拙くて、脆くて、弱くて、ひたむきに優しいのだろうと。
思った。
だから、諦めないでくれと。
誕生日の夜が明けるまで、諦めないで。
捨てないで。逃げないで。望んで。この手にすがって生きたいと言ってくれと願った。
「……叶えるから」
それが、生きたいという、彼にとってはどんなに願っても叶わないお願いでも。
「…絶対、叶える…から」
一緒に死んでくれという、残酷な願いでも。
「……だから、…願ってくれ」
鬼でも悪魔でも、神でもなんでも、俺の魂なんて持っていけ。
だから、俺に彼の願いを叶える力をくれ。
人に生まれ変われなくていい。
動物でも、蜘蛛でも、世界の果ての粒子でも、桜の花弁でも、いい。
笑って生きているお前の髪に落ちる、桜になれるなら、人になどなれなくていい。
生きるお前の傍に、一瞬でも寄り添えるなら。
人間で、なくなっていいよ。
だから、どうか願って。
諦めないで。
俺が死んだって、生きてくれ。
出来るなら、俺と一緒に、生きて欲しい。
望めるなら、今の人生を、俺と一緒に、生きて欲しいんだ―――――――。
『お前も来い』
そう花火大会のメールが謙也から来たのは、八月の二十日。
三日前のことだった。
メールを送った千歳と一緒に白石も来たので、謙也は驚いていた。
「白石! お前なんで?」
「千歳と一緒におったから。で、千歳が来い言うたし」
「…へぇ」
あまりにあっさり言われて、謙也は随分驚いていた。
石田に金太郎、小石川、小春にユウジ、つき合いの悪い財前もいて、空の花火大会は終わってしまったからと、花火を持ち寄って、誰かの家でやろうと言う話だそうだ。
「誰ん家でやるん?」
「それが俺ん家からぶって、師範は寮やし、金ちゃんもあかんし、あとは小石川と光頼み」
「決まってからやれや」
「そういったかて…」
背後で財前が携帯を畳んだ。
「すんません。ウチあかんですわ。ユズルが寝たばっかで」
「ああ、甥っ子か…ほな」
「小石川先輩も無理やって」
「うわ、全滅か!」
「千歳はアパートやしなぁ」
最後の夏の思い出に、やりたかったんやけどな、と謙也が言った。
「最後の?」
「そう。このメンバーでこの夏に。…俺達でこの夏生きたんやー!って大人になっても忘れられんように」
白石が謙也らしい台詞に笑った。千歳にはそれで、何となく予想がついた。
止めるつもりもない。
「なら、ウチ来いや」
白石がそう言ったので、その場の全員が驚いた。
「なんやその顔」
「い、いややって部長…」
「…ええ、ん?」
「ええって。こっから近いし。ついてきぃ」
白石の家に行くなど、全員が初めてなのだ。
全員がどんな家族だろう、どんな家だろうと道を歩きながらしゃべっていた。
実際、彼の家について、謙也も財前も、言葉がないくらい固まっていた。
麦茶持ってくる、と引っ込んだ白石をしばらく視線で追って、広い庭をうろうろ見渡す他のメンバーのように純粋にすごい、で片付けられなかったらしい。
それでも白石が盆に麦茶を人数分持って来て、金太郎が花火早くと言い出す頃には、二人もなんとか各々納得したらしい。
花火をそれぞれ持って、好きずきに庭に火の華を咲かせている。
白石が縁側から金太郎に、人に向けたらあかんよと言った。
白石は今は、出かけた時のままの普通の私服だった。
「着替えんとか」
「みんながびびるやん」
「…そか」
「なんやその笑顔」
「いや、俺は特別待遇やったけんね、って」
「…なんやそれ」
白石ー!と金太郎が呼ぶ。はいはい、とそちらに走っていく白石を見送った千歳に、謙也が近寄ってきた。
「お前は、驚かなかったな」
一瞬意味がわからなかったが、すぐこの家のことだとわかった。
「俺は前から来とったけん」
「そか…」
「…謙也?」
「白石は、お前には心許してんやな」
「…………ああ」
それは否定しないし、出来ない。
約束した。
「……なぁ」
「ん?」
「……お前は、白石、好きなんか?」
「…好いとうよ。誰より」
謙也の頬が、花火の明かりに照らされて赤い。
「……なら、なんで」
「…?」
「…約束したん?」
遠く、あー消えた、という声。
「白石に、殺す、て…」
「……聞いとったと?」
あの夜、約束した、花火の空の下。
周りを見る余裕はなくて、謙也がいても、気付かなかっただろう。
「意味わからん。経緯もわからん。けど、白石がホンマにそれに喜んでた。
そんだけはわかった。…なんでや?
聞こうとは思わん。白石が俺に話そうとしてくれんことやから。
お前以外が、聞いたらいかんことやから。
やけど…好きなら、なんで約束出来る?」
理由すらわからないのに、彼は悲しそうに顔を歪めた。
「なんで、あいつの命、諦められる」
謙也の身体の両側に降りている両手がきつく握られる。
震えている。
「…諦めんなよ。…お前まで、諦めんで」
「………」
パン
と、傍で小さな打ち上げ花火が鳴った。
「何言うとーと? 謙也」
「え…」
謙也が見上げる千歳の顔は、限りなく真剣だった。あの、いつも暢気にへらへら笑っている顔からは想像もつかない、真剣な色で。
怒ってさえ、いた。
「俺が、白石を諦めると思うと?」
「……」
「俺が、白石の気持ちだけで満足すっと思うと?
一瞬で満足すっと思うと? 満足なんかせん。
俺はあいつの一生が欲しか。そんために、気持ちも、未来も、あいつの命も。
諦めるわけなか。一個も諦められるわけなかよ。
…見くびるんじゃなかね。謙也」
「……じゃ、なん…」
「…謙也」
だって、桜が散るから。
「俺以外の誰が、白石のためにこげん惨めに生きられっと?」
「…ちとせ?」
「未来も捨てるほど、人殺しの覚悟して、後追う覚悟もせないかんほどの愛し方は、あいつんために、惨めになれんなら出来なか。
俺は、あいつんためなら、どげん惨めになって、地面に這い蹲ったってよかよ。
どげん惨めになっても、あいつの全て、一個も諦めんでいられるならそれに勝るもんはなか。
俺以外に、誰があいつのためにこげん惨めになれっとね。
…謙也には、無理やっただろ?」
「……千歳」
「俺は、欲深か。だけん、一個も諦めなか。
希望が絶望でも、…諦めなか。
…俺は、白石と生きたか」
千歳の視線が、金太郎の傍で花火を握る白石に映る。
彼は、笑っている。
「…ばってん、あん時約束せんかったら、あいつはずっと泣くから。
…笑って過ごして欲しかよ。俺の約束で、あいつが笑ってられる程安らげるなら、そいでよか。それを破ることもわかってて、胸が痛むんは俺だけでよか。
…あいつが笑ってくれるなら、…俺は謙也を殺す約束だってすったい」
心臓がどきりとしたのは、その時の千歳が限りなく本気の眼差しで謙也を見たからだ。
「ま、そげん約束は、あいつには必要なかけど」
すぐ千歳は笑った。冗談だ、と。
けれど、心臓は静まらなかった。千歳が本気だから。
「……ち」
「……謙也、…桜が、…散るとよ」
「…え? …さくら?」
「…謙也には見えなかやろ。…だけん、桜の花弁がずっと散っとると。
白石が泣くと、桜が散る。
桜はあいつの涙やから…あいつが泣くと、散る。
……俺には、あいつが泣くなら、どこおってもわかる。
桜が散るから」
空を見上げる、その瞳に映っているのだろうか。桜が。彼には。
見えていない、右目にも。
「…今も散っとう。笑っとうばってん、あいつは今も泣いとう。
…だけん、俺は油断なんか一個も出来なか。
安心なんか、一個も出来なか。
…やけん、白石が安心出来る気持ちは、…俺は欲しい。
…あいつが心から笑う日が欲しか。…桜が散らない日が、欲しか。
……そんためなら、…俺はなんでもすったい」
最後の、金太郎が持っていた花火が落ちる。
「…神様殺すんも、なんでも」
「え」
「…俺も、…あいつをもう一回泣かせて悲しませても、…あいつにも、決めさせたか。
…生きたい、って思わせたいから」
地面に落ちた火が、すぐ黒くなる。
謙也の視界で、千歳はにこりと笑った。
全て、夏の長い夢だ、というように。
「だけん謙也。俺がもう一回、あいつを泣かせても、…許してな」
それを最後の言葉にして、千歳は下駄を鳴らすと白石の方に歩いていった。
終わったと?と笑う顔は、矢張り先ほどの彼が、夏の夢のようだった。
だから、決めたことだった。
約束を破るように自分も死ぬと告げて、白石を悲しませることも。
決めたことだった。約束をした、花火の日に既に。
泣き疲れて布団で眠る白石の、赤く腫れた瞼を指で撫でた。
「…それしか、わからん」
白石に、生きたいと願って欲しかった。
諦めないで欲しかった。
自分は、こんな運命を知らない。
だから、どうしたら正しいかもわからない。
それでも、あの言葉を、白石が望んでないことだけはわかっていた。
彼を追い詰めて泣かせるだけだと、それだけは理解していた。
「…そんでも…俺は」
生きて、欲しかった。
ガタン
大きな音が不意に鳴って、びくりと反射で身が震えた。
ただ、台所のなにかが落ちただけだろうとすぐ興味を失った。
「……、ん」
「ああ、起きたと?」
それでも、今ので目が覚めてしまった白石に笑いかけると白石は困ったような顔で見上げた。
ドン
また、音がした。今度は、部屋の傍の廊下付近からだ。
「…なん…?」
ドン
流石に部屋の扉を叩くような音が響いて、千歳は顔をしかめた。
「…なんね?」
まさか、誰か迷い込んだ人でもいるのか、はたまた強盗か。
立ち上がって扉を開けて確認しようとした千歳を、立ち上がった白石が背後から抱きしめて止める。
「白石…?」
「…開けへんで…」
「…し」
気付く。自分を抱きしめる、身体が震えている。
「……わかる…痣が痛い…っ……迎えや―――――――――――――」
瞬間、部屋中に亀裂が走るように木の枝が部屋の中に伸びて、千歳の腕が枝に絡め取られて自由を奪われたと思う間もなく、白石の片腕も絡め取られた。
ひらりと、降るのは桜の花弁ではない。赤い、深紅の花弁。
「戻りなさい。神様が呼んでいる」
知らない声が、扉の向こうからした。
ぎい、と開かれた扉。立っているのは、着物姿の数人の男。
白石の顔が青ざめたのは、知っている顔だからだろう。
「……い、いや…や」
拒絶の言葉を吐いた白石を見て、男は小さく手を彼に向かってかざした。
瞬間、床を裂いて天井まで走った木の枝が、白石の左肩を貫いた。
「―――――――――――――っ!」
「白石!」
ぼたぼたと傷ついた左肩から赤い血が床にこぼれ落ちる。
そのまま力を失って倒れた白石を男の一人が抱え上げた。
白石に、既に意識はない。
ナイフや包丁などの切れ味のよい刃物ではない、木で貫かれる衝撃は恐らく気絶を促す程の激痛だったのだろう。
「…待て!」
「…この子供は、…里のことを知ったか」
「ここで殺せばいいのでは?」
なんだ、彼らは。
殺人の躊躇いもなく、人柱に対する礼儀も優しさもない。
「…いや、…連れ帰ろう。…この男は些か人柱に触れ過ぎた」
ウォォォオオン
なにかの鳴き声がする。
低い、獣のような、いや、この世のものではないような。
壊れた家の壁が崩れた先で、あの狂い咲きの桜が幹の間に大きな漆黒の穴を開けて佇んでいる。
「神様が呼んでいる」
男たちがそちらに歩いていく。ぐいと千歳の身体を引っ張るのは、男たちではない。
その木から伸びる、枝だ。
男たちに抱えられた意識のない白石の肩からまた新しい血液が大量に落ちた。
その血をあっさり踏みつけて、歩く男たちには白石への気遣いすらなく。
何故、あんな酷い扱いをされなければならない。
彼は、お前達のために死ぬ運命じゃないのか。
何故、そんな惨い扱いが出来る。
なにも、言葉にならない。
それでも、口を開ける木の前。
声が、一言千歳から零れた。
「…なか」
「…、」
振り返った男に、自由にならない腕で吐き捨てた。本心だった。
掠れたのは、あまりに信じられないからだ。
「お前たち…――――――――――人間じゃ、なか」
彼らが人間だなどと、信じられないからだ。
男は口の端をあげて笑う。
「口の減らない…。なら、人間ではないと教えてやろう」
お前の前でこの子が死んでも、同じことを言える精神が残っているか、見たいものだと。
笑う声は、もう人間ではない。あって堪るか。
こんな、こんな酷い、己のために消える命を餌のように扱える人を。
人間だと認められる筈がない。
あんなにも優しい、綺麗な白石と同じ人間でいる資格なんて、こいつらにはない。
そう思った瞬間、視界は暗闇に落ちた。
感覚もない。
ただ、胸に、落ちたのは絶望に似た悲しさだ。
約束を、守れないのだろうか――――――――――そんな、見えない未来の、悲しみだった。
→NEXT