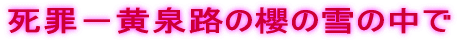
第四話−【傍にいたくて手を汚しても】
視界に、桜が見えた。
ああ、泣いている。
彼が、泣いている。
早く、傍に行かなきゃ。
傍で、独りにしない、と抱きしめなければ。
だから、泣かないでくれ。
すぐ傍に行くから。抱きしめるから。
泣かないで、白石――――――――――――。
「………」
気付くと、千歳の視界にはただの床。目覚めたばかりの思考で夢か、と思う。
しかし、身体は見知らぬ家の布団に包まれていた。
「……?」
起きあがると、じゃらと鎖の音が手元で鳴る。
両手は鎖の繋がった枷で拘束されていた。
枷は片手ごとに嵌められていて、腕自体は広げることが出来る。ただ腕がどこかに繋がれているのは間違いない。
(…ああ)
夢じゃなかった。
ここは、白石の生まれた里だ。
だから、彼が泣いている。
「起きたんか?」
聞き慣れた関西弁に、思わず顔を上げて、一瞬白石だと思った。
一間しかない小さな家の玄関をくぐってきた男が逆光で顔が見えない。
けれど男が近づくと、輪郭がはっきりして、彼が白石でないとわかった。
「…あんたは?」
「俺はこの里の住人や。お前の監視を任された。
この里に法期間はないから、誰かがそれにあたるわな」
「………」
「名前は聞きたくないやろ?」
「…え」
「キミが守ろうとしとる子を、生け贄にしようとしとる里の住人の名前なんかは」
妙に、さばさばした雰囲気の男だ。
とにかくついてきぃ、と千歳の鎖を引っ張っていくから、嫌でもついていくしかないのだが、男はどうしても白石を思い出させる。関西弁だからだ。
家から出ると、そこら中に見える、実った木々や金色の畑。そして、今もなお狂い咲く、何十本もの桜。
男は己の腕に枷をしていた。千歳のように両手ではなく、片手だけ。
その鎖が、千歳と繋がっている。監視役、とはこういう意味か、と理解した。
「よかとですか?」
「ん?」
「余所の人間、出歩かせて。それとも、牢屋にでも連れてくと?」
「まさか。入れる必要がない」
「…なして?」
「この里は法的機関がないと言ったやろ?
殺人を裁く人がおらん。キミが例えばあの子を返せって暴れたら、俺との鎖を切る前にそこら中から出てきた住人にリンチされてアッという間に殺されてまうよ。
やから、必要ない」
「……」
なら、何故生かしておく、と視線が語ったのが伝わったのだろう。男は笑った。
「俺が我が儘言うた。俺が監視するから、あの子が死ぬ日までは生かしてやってくれ、て」
「……なして?」
「……キミ、千歳くん言うたな」
「……はい」
「……俺の言葉、おかしいとか、思わん?」
男がそう言った時だ。傍の畑で着物姿の子供たちが楽しそうに花火をしているのが見えた。
自然、思い出すのは、あの花火だ。
「…なんで、花火」
「…祝い事やから」
「…」
「…あの子たちにとっては、儀式は生け贄が死ぬ日やのうて、神様が力を取り戻すお祝いの日やから」
「…そんな…っ」
「怒ったってしゃあないよ。あの子たちの誰か一人でも傷付けたら、キミ殺されるで?」
その言葉に、拳を握りしめた。
唇から殺しきれない呻きが漏れた。
「安心せえ」
男は背中を向けたまま言う。
「俺も、はらわた煮えくりかえっとるわ」
「…………」
驚いた千歳をそのまま引っ張って、男はまた歩く。
「…俺の言葉の話やな。…俺は、人から習ろたんや。
その人が、外で覚えてきた」
「……? 白石は、外に出る人はおらんて」
「出る人はおるやろ?」
男が振り返って笑う。
「キミの思い人と同じ、逃げた生け贄が」
「………」
「最初の時代こそ、逃げる人柱はおらんかったけど。
時代が過ぎると、流石に逃げ出す人柱は増えた。そいつらは結局あの子みたいに捕まって帰ってくる。そいつらが、教えるんや。…連れ戻されてから、死ぬまでの間に。
外で知った、言葉や、知識」
「……そんな」
「なぁ、キミは不思議に思わん?」
「……」
「あの子、なんで関西弁使うてるか」
白石のことだ。そういえば、何故。
「…俺と同じやな」
「…? 前の人柱から聞いた…なら、」
「あの子が産まれた年に死んだ、わな。
前の人柱は…十五歳で死んだ、俺の妻やった」
この里は、何歳でも結婚出来るしな。
「妻は俺に、息子を死ぬ前に遺してくれた。やけど」
―――――――――――――十五年前の儀式の年に生まれた、印を持つ子が。
「…その子は、次の人柱やった」
「…ま、さか」
「…蔵ノ介は、俺が大阪に逃がした、俺の息子や」
男は立ち止まると、気付けばそこにあった小さな洞穴を示した。
「ここや。人柱を誕生日まで保護する牢。
…鎖は長いから、蔵ノ介んとこまで届く。
会ってきてやってくれへんか」
「…よか、とですか…?」
「人柱の親は、多少贔屓されるから」
男が促せば、もう拒める筈がない。
桜は今も散っている。
彼が、泣いている。
「千歳くん」
「…え」
走り出そうとした背中にかかった声に振り返ると、男は泣きそうに嗤っていた。
「……蔵ノ介を…独りにせんでくれな」
「……はい」
答えて、振り返らず走り出した。
足下を鎖が這う音が響く。
どこだ。どこに。
視界を、桜がまた散った。
幾つも長い洞穴に並ぶ格子の穴。
その一つの前に、花弁が落ちる。
「…白石!?」
その前に駆け寄って、呼吸が止まった。
石畳の上に両手足を鎖で拘束されて倒れている、白い着物をまとった身体。
「白石!!」
「………、」
繰り返し、格子にしがみついて呼ぶと、瞼がうっすら開いた。
その肩が、血に染まっている。
手当すら、されないというのか。
嘆きに歪んだ千歳の顔を認識して、白石が弾かれたように起きあがった。
「千歳…ッ!」
肩の痛みに一瞬顔をしかめながら、格子にすがるように駆け寄った足がしゃがみ込んだ。
その手が格子に触れた瞬間、格子越しにその身体を千歳は抱きしめる。
格子を挟んで背中を包む腕に、白石は涙を零してしがみついた。
「千歳…!」
「…白石…」
着物一枚でこんな冷えた場所で、手当すらされずにいた身体は、既に死んだように冷たかった。
「…怪我しとらん?」
「お前がしとうよ」
「……うん」
「……白石」
酷く涙の滲む声で呼ぶと、彼がなに?と柔らかく言った。
「ごめん」
「…ちとせ?」
「…ごめん。…約束、…あん時に果たせばよかった…」
“…俺に、殺されたか、って…言葉”
あの日に。
「あの時、…殺せばよかった」
「……」
「俺の腕ん中におった。やから、俺の腕ん中に閉じこめられた。
俺のもんやった。独りやなかった。
…あの時、」
喉が嗚咽に鳴っても、逆らわなかった。
「俺が殺して、一生俺のもんにすればよかった…!」
「…とせ…っ」
肩に頬を寄せるようにした、白石の瞳から落ちた涙が、石畳に跡を作る。
「…ごめん。…約束、…守れなか。
独りにしてしまうと。…独りで、…死」
「……ちとせ」
「……俺の傍に、…縛り付けたかった。
傍に、いて欲しかった。…殺して…ずっとその身体、傍で抱いとればよかった…て、今、馬鹿みたいに強く思っとう…」
「……ち…」
「…ごめん、矛盾だらけたい。俺…。
ごめん。ごめん。ごめん…。こげん、…好きになって、…ごめん」
千歳の頬を伝った涙が、白石の手に落ちる。
「……ううん」
「…白石?」
「……嬉しい」
涙に濡れた千歳の瞳が、白石の瞳と格子越しに交わった。
「……嬉しい。…大阪行ってよかった。お前に…会えた」
「…しら…っ…白石…っ!」
「…お前が泣いても…桜散るやんか」
少し笑った声で白石が言った。
「……俺」
止まらない涙を拭わず、喉を鳴らして白石に話しかける。
「…俺、そげんでも…諦めたくなかよ」
「……」
白石の泣きそうな顔が微笑んで、手を伸ばして頬に触れた。
「…なぁ、…キスして…」
「…え」
「…頼む」
呼ぶように願われた。逆らえる筈がない。そんなの、自分だって一緒だと、千歳は抱きしめたまま唇を重ねた。
「……千歳…約束、してくれるか…?」
「…どげん、こと?」
「…俺が死んだら…、…」
言いかけて、こんな酷い、願うん間違ってるってわかる、と言った。
涙がまた、彼の頬を流れる。
「でも…、もう、…辛くて、堪えたりでけん…っ」
「…よか、言って?」
「…俺…死んだら……、…」
追って来てくれ
「…俺の傍で死んでくれへんか…。俺の後、追ってきて。あの世まで来てくれ。
…独りになりたない。…お前のおらん場所で、独りんなりたない…っ!」
怖いよ。
そう泣く身体を、一層強く抱きしめて、もう一度キスをした。
「…うん」
「…とせ?」
「…うん。…約束すっと」
「…やけ、ど」
「…願ってくれ。…叶えるから」
あの時、俺は願ったんだ。
「…なんでも叶えるけん…」
白石が願うなら、どんな願いでも叶えると。
「…どげん願いごとでも…一緒におるための願いなら」
一緒に死んでくれ、でも、一緒に生きてくれでも。
どちらでも構わないから。俺に彼の願いを叶える力をくれと。
叶えるから、と。
「…叶える」
「……ち…とせ」
「…約束…する」
ああ、また、桜が散る。
今だけ、散らないでくれと、涙を流したまま千歳は願った。
今だけは、散らないでくれ。
彼が傍で泣いている時だけは、…散らないでくれ。
許された時間は僅かしかなく、後ろ髪を引かれるように外に戻った千歳を待っていた男が、何故か悲しそうにした。
「……?」
まだ溢れそうになる涙を拭いながら見ると、彼は行こうかと背中を向けた。
助けようとしないのだろうか、彼は。
いや、彼が助けようとしても無理だとわかる。ここには、殺人を裁く人がいない。
彼が死ぬ数に加わるだけだ。
「……約束をしてたな」
「…あ、ああ」
「…叶わないお願いやな」
「………」
あの世とかのことかと思う。馬鹿にされた気は、なかった。
「…やけど、俺もしたことあるわ。…叶わないお願い」
振り返った男に、思わず聞いていた。
「…息子と一緒に、生きられますように…て」
男は、笑っていた。
「…なぁ、キミまで諦めんでくれんか?
あの子を、諦めんでくれ。あの世の約束なんかせんで、生きて傍おってくれへんか。
……あの子は、こんな陰鬱な里で死ぬん、似合わんよ」
「……あんた」
「…あの子がいた屋敷、あれな」
からんと、足下で鳴る下駄は、彼のものだ。
「…昔から、大阪に逃げた人柱が使っとった屋敷なんや。他の地方にもある。
大阪に逃げた最初の人が建てた。何人目かが、ここから持ってった桜を植えた。
…一年中咲く桜。
蔵ノ介に、ならあそこに行けって俺が言うた。…どっかで、あの子だけ逃れられんかって一日、一日願っとった。…俺は、諦めたない」
「…………」
「…な」
微笑む顔が、誰に似てるかなんて愚問だ。
いつだって気高くて、強くて、綺麗な心の、白石だ。
あの子に似てなくて、誰に似てるんだ。
「……そう、たいね」
そうだ。
諦めて堪るか。
彼が生きることを、諦めないと謙也に言った。
白石に言った。だから。
諦めて堪るか。
白石と一緒に今を生きると、願う。
だから、諦めて堪るか。
…諦めない。
例え、その先で白石を失っても。
その瞬間が過ぎるまで、諦めないと誓ったのは自分だ。
だから、
諦められるわけないじゃないか。
決意したように顔を上げた千歳を、男は嬉しそうに見遣ってくれた。
→NEXT