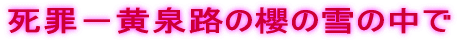
第五話−【白い櫻が閑かに散った】
―――――――――――――白石は、一体どんな気持ちだったのだろう。
生まれてすぐ母が人柱として死に、母を知らず、そして生まれた時から十五で死ぬ人柱と決められて、そして十一で里の外へ、大阪へ逃げて、たった一人残った家族の父と離れなければならなかった気持ちは。
十五で死ぬと決められて、彼はどんな気持ちで十五年を生きたのか。
どんな気持ちでテニスを始めて、どんな思いを、全国制覇にこめていたのか。
自分には、わからない。
「……わかっても、やれなか」
男が気付いて顔をあげた。
「…俺は、…父親になんか禁止されたこと、なかです。
父は俺の決めたこと、一度も咎めなかった。
…俺は、いつだって好きなことを、望む通りにやれてきた。
……やけん、白石の気持ちが、…わからなかです」
生まれた時から、どうしようもない運命に道を縛られた彼の気持ちを、わかってやることもできない。
想像すら、出来ない。
「それでええんやないかな」
「…?」
「やから、キミはこれから、楽しいことをあの子に与えられるんやから」
無駄なことない、と言われて少し笑えた。
白石は、きっと俺達を少しも妬んだりしなかった。
何故自分は死ぬのに、何故彼らはこんなに自由なんだと。
妬むことすらしなかった。
彼は、そういう、とても綺麗な人だから。
とても、優しい人だから。
きっと、彼は里の人々すら憎まない。
生きたいと、死にたくないと願いながら、それでも。
誰かを憎まず、願えるのが、彼だから。
鳥の鳴き声がする。
夜が、明ける。二十八日の夜が。
朝が来る。
二十九日の、彼の誕生日の、朝が来る。
桜の木々が囲う大きな、花弁が散る緑の祭壇の間は抜けるような青空が見えた。
もう既に、石の祭壇に寝かされた身体は、痛みを訴えなかった。
左肩は、出血が止まっている。
懐かしいな、と白石はぼんやりと瞼を開けて思った。
幼い頃は、それでもまだ、ずっと未来のことと信じて、この場所の空を見に来た。
祭壇を遠目に囲む人々の中には幼い子供も多くいた。
今更驚くことでもない。
それより、もう。
もう、…時間だと知るから。
逃げられるわけはなく。なら、決められる決意は、死の覚悟しかない。
―――――――――――――死にたない。
独りに、なりたない。
うっすら開いた瞳に、剣を持った祭司が見える。
独りは、嫌だ。
(死にたない)
瞳から、ぽつりと涙が零れた。そのまま頬を伝って祭壇に落ちる。
(独りに、なりたない…)
雫で滲んだ視界を、不意に動かした時、人々の合間に、見知った長身を見た。
唇が、安堵に綻んだ。
(…ああ、そやった)
俺には、約束がある。
死んでも、千歳が追ってきてくれる。
独りになんて、ならなくてよかったんだ。
独りに、ならずに済むんだった。
そっと、瞳を閉じた。
もう、願うことは、なにもなかった。
空に響いた銃声は、酷く場違いだった。
祭司が、胸を血に染めて倒れる。
「……」
千歳が背後の男を見て、一度だけ驚いた顔をした。
すぐ男に行きなさいと顎で示される。迷いなんて、あるはずがなかった。
「待て! …“白石”、お前…!」
背後で響く銃声は、実際自分の耳には聞こえていないかもしれない。
ただ、彼の傍に行くことしか、頭になかった。
「…ち」
瞳を開けて驚いたように自分を見た白石を抱きかかえて、踵をすぐ返した。
その千歳の前に男たちが立ちふさがった。
白石の父も同じように囲まれている。
「……と、せ」
弱く呼ぶ声に、それでも大丈夫だと言いたくて抱きしめる手を強くした。
「…白石、気が違ったか?」
里の住人が呼ぶ“白石”は、白石の父親のことだろう。
「人柱には、価値ある死を与えたいと、お前なら望むだろう?」
彼は答えない。
「無価値な死を、息子に与えたくはなかろう?」
「………なんね、それ」
「…、人柱が妻だった白石なら知っているだろう。神に捧げられなかった人柱の運命を」
一度、男に視線をやった住人が、千歳の方を見て言った。
「人柱は生まれる前に印を神様から授かる。それは、十五年の命の証だ。
…神に捧げられずとも、人柱は十五で死ぬ。
神に捧げられず十五歳の誕生日を過ぎた人柱は…」
「ただの骨となって死ぬ」
掠れた声でも、なんだそれはと言った筈だった。
実際は、千歳の口から声は零れなかった。
住人の声を聞いた、頭が痛い。
抱きしめている身体が、冷たいのは、気のせいじゃないのか?
…死ぬ?
何もしなくても、人柱にならなくても。
白石は、―――――――――十五歳の年を、生きられない?
十五年以上を生きられない、十五年の命の期限を運命に決められたのが、人柱だというなら。
今自分の服を掴む白い手が、必死に願った思いは、どうあっても叶わないコトだと言うのだろうか。
願うことすら、許されず生まれたのか。
世界の誰も、それを叶えることが出来ない、そんな無惨な命を、与えられたと。
「…それでも」
男が言った。
「それでもええやないか」
その瞳は自分の息子を、静かに見つめる。
「無価値でもなんでも。…価値ある死が、世界に一体何人ある?
…無価値でええ。褒められる価値なんかなくてええ。
一番大事な人の傍におられる。…それ以上に、なにがある?」
独りやない、それ以上の幸福がどこにあると彼は言った。
千歳の服を掴む、白石の手が強くなった。
思わずその顔を見下ろした千歳に、数度涙を流した白石が、それでも微笑んで言う。
「…無価値でええわ、俺」
「しら…」
「…なんもなくてええ。ただ、死んだって命でええ。…ええから」
震えて伸ばされた手が、首筋に触れてまた服を必死に掴んだ。
一瞬だけ触れた手は、驚く程に、冷たい。
「…独りやないならええ。
連れてって千歳…。
死ぬなら、お前の腕ん中がええ…っ」
「…し」
胸が熱いのは、嬉しくて、それ以上に辛くて、寂しくて、悲しいからだ。
逆らわずにきつく抱くと、自分の頬をも涙が流れた。
だって、誓ったんだ。
「おい…!」
迷わず、白石を抱きしめたまま走り出した千歳を止めようとした全ての手が弾かれた。
「…な!」
千歳の周囲を舞うのは、桜だった。
桜の、花弁だ。花弁が、千歳を守るように、空を舞っている。
何故という顔を見ずに、駆け出す。背後で銃声がまた響いた。
彼もまだ、諦めていない。
諦めることなど、出来ないのだ。俺も彼も。
ほんの少しでも、ただ、長く生きていて欲しいと願う。
愛しい命を、諦められる筈がない。
例え、それに自分の命さえかかっても。
鎖は既に男が切っていたのだろう。引き留められることはなかった。
思えば裸足だったが、痛みは感じなかった。
畑の広がる道を抜けて、森に入り、それでも止まる気はなかった。
背後の声が叫んだ。何故、里の出口がわかるのだ、と。
自分でも不思議だった。
白石に聞いているわけでもないのに、進む道がわかる。
桜が散るからだ。
進む道はこっちだよ、と桜が散って千歳に教える。
それが、何故見えるのかもどうでもいい。
今、自分の腕の中で服を掴む手を、離さずに済むなら、どんなに遠くても走る。
体力がいつから限界なのかもわからない。身体が痛いから、もう限界はとっくに来ているとはわかる。
それでも、それを意志が上回っていた。
だから、走ることが出来た。
ふと木々の隙間が視界に映る。そこを抜けると傷だらけの裸足が踏みしめたのは、線路だった。
すぐ、数メートル向こうに、駅のホームがある。
すがるように、願うようにホームに走った。
ホームの駅名を見て、一気に限界を教える震えが上った。
駅名は知らない駅名だが、県名は“熊本”。
里から、出た証だった。
すぐホームに上がって、すぐ倒れそうになる足を叱咤して停まっていた三両しかない電車に乗り込む。
座席に座る力も最早なく、電車の中に入った瞬間その場にしゃがみ込んだ千歳が、繰り返し荒く呼吸を吐いて、軋む全身を無視するように腕の中の身体を見て、言葉を失った。
服を掴む手だけはそのままに、既に全身は、熱がなかった。
光なく、開かれたままの瞳に、喉が鳴って、涙が瞳を破ろうとした時だ。
「…と……せ」
掠れた、本当に小さな声は、間違いなく白石の声だ。
「…しらいし…っ……」
「…………せ………」
もう、既に動かす力すらない腕が、それでもなにかを伝えようとぴくりと指先を動かした。
「…なに? …なんでも、言うて?」
声は滲んで、すぐ涙になったけれど、白石に向けて言った。必死で作った千歳の笑顔は、泣きそうに歪んだ。
「……………あり…がとな」
「……うん」
そんなことはどうでもいいと言おうとして、やめた。
彼の最期の言葉を、一言たりとも無駄なものにしたくなくて。
「……………もの…そう………うれし…い。……な…して……ぎゅ…て…し…」
息絶える前の声が願うままに、その身体を抱きしめた。
抱きしめる腕の震えは、どうか白石に伝わらないで欲しい。
「……ちとせ」
自分を見上げる顔が、涙を一筋零して、微笑んだ。
「すき」
電車の発車のベルが鳴る。扉が閉まる。
その瞬間、眼前を散った桜は、彼の涙ではなかった。
一瞬にして、腕の中でその身体はただの骨となった。
柔らかい肉も、髪も、瞳も欠片も遺さずに。
骨を覆う白い着物についた血液の染みだけが鮮やかで。
「…」
声なんて、出る筈はない。
「…っ―――――――――――――…!!!」
ただ、声にならない程泣いて、ただその骨を抱くように腕に閉じこめて。
走り出した電車の揺れの中で。
桜は、もう彼の涙じゃない。
桜は、彼が泣くから散るんじゃない。
桜は、彼の命が散るから、―――――――――――――散る花びらだ。
約束なんて、一個も守れなかった。
独りにしない。
それだけしかなかった。
それだけしか、彼に渡せなかった。
電車の窓から、流れる景色の中に桜は見えない。
今は、夏の終わりだ。
すぐ秋になって、雪が降る、冬になる。
それでももうあの声はない。
『なあそこのでっかいお前、俺と雪合戦してくれへん?』
→epilogue-[冬の桜でもう一度]